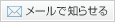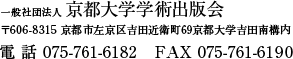ホーム > 書籍詳細ページ
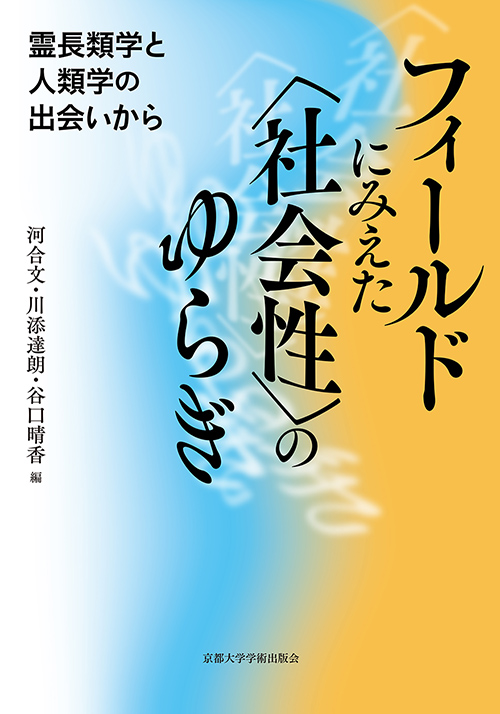
私たちが想い描く「社会」は本当にあるのか?――群れているように「見えるだけ」のサル。関わりから遠のくヒト。これらのフィールドからの報告によって、あるものとして考えてきた社会性やつながりがゆらぎはじめる。気鋭の人類学者・霊長類学者らの応答からみえてきた、組み変わる境界とゆらぎ。
(掲載順)*は編者
河合文(かわい あや)*
東京外国語大学・准教授.博士(学術).
◎主な著作
『川筋の遊動民バテッ——マレー半島の熱帯林を生きる狩猟採集民』(生態人類学は挑むMONOGRAPH5)京都大学学術出版会,2021.
“Searching for Status in the National Sphere: Among Religions and Ethnicities,” In Ikuya Tokoro & Hisao Tomizawa (eds.) Islam and Cultural Diversity in Southeast Asia (Vol.4). ILCAA. 2024.
川添達朗(かわぞえ たつろう)*
特定非営利活動法人里地里山問題研究所・特任研究員/東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・フェロー.博士(理学).
◎主な著作
「群れの「外」の関わり合い——ニホンザルの互恵性からみる社会」河合香吏(編)『生態人類学は挑むSESSION5関わる・認める』京都大学学術出版会,2022年.
「オスの生活史ならびに社会構造の共通性と多様性」辻大和・中川尚史(編)『日本のサル——哺乳類学としてのニホンザル研究』東京大学出版会,2017年.
岩瀬裕子(いわせ ゆうこ)
東京都立大学人文科学研究科・博士研究員/東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・共同研究員/スペイン国立ルビラ・イ・ビルジリ大学(カタルーニャ州)・訪問研究員/東洋大学健康スポーツ科学部・非常勤講師.博士(社会人類学).
◎主な著作
「「基盤的コミュニズム」のゆらぎと調整——スペイン・カタルーニャ州バイスにある「人間の塔」の継承集団を事例に」『社会人類学年報』弘文堂,2023年.
「こわれるモノが創る〈共〉としての「人間の塔」——安全のための物理的・文化的な技術的実践に着目して」『物質文化』102,2022年.
田島知之(たじま ともゆき)
大阪大学COデザインセンター・特任講師(常勤)/NPO法人日本オランウータンリサーチセンター・理事.博士(理学).
◎主な著作
「群れない類人猿オランウータンの関わり合いから見える「集まらない」社会性」河合香吏(編)『生態人類学は挑むSESSION5関わる・認める』京都大学学術出版会,2022年.
「空飛ぶトカゲと森の人」『はじめてのフィールドワーク1アジア・アフリカの哺乳類編』東海大学出版部,2016年.
八塚春名(やつか はるな)
津田塾大学学芸学部多文化・国際協力学科・准教授.博士(地域研究).
◎主な著作
「タンザニアの狩猟採集民ハッザによる食料獲得戦略の多様化——民族観光と他民族の影響に着目して」『農耕の技術と文化』30,2022年.
“Farming Practices among African Hunter-gatherers: Diversifying without Loss of the Past,” In: Hyden, Goran, Sugimura, Kazuhiko. and Tadasu Tsuruta (eds.) Rethinking African Agriculture: How non-Agrarian Factors Shape Peasant Livelihoods. Routledge, 2020 (Co-author: Ikeya, Kazunobu).
貝ヶ石優(かいがいし ゆう)
京都大学高等研究院・特定研究員.博士(人間科学).
◎主な著作
Yu Kaigaishi, Masayuki Nakamichi, Kazunori Yamada. 2019. “High but not low tolerance populations of Japanese macaques solve a novel cooperative task,” Primates 60(4).
Yu Kaigaishi, Shinya Yamamoto. 2024. “Higher eigenvector centrality in grooming network is linked to better inhibitory control task performance but not orher cognitive tasks in free-ranging Japanese macaques,” Scientific Reports.
藤井真一(ふじい しんいち)
国立民族学博物館・助教.博士(人間科学).
◎主な著作
「暴力の連鎖を断ち切るための術——ソロモン諸島における紛争処理の文化」『季刊民族学』186,2023年.
『生成される平和の民族誌——ソロモン諸島における「民族紛争」と日常性』大阪大学出版会,2021年.
松本卓也(まつもと たくや)
信州大学理学部生物学コース・助教.博士(理学).
◎主な著作
“Opportunistic Feeding Strategy in Wild Immature Chimpanzees: Implications for Children as Active Foragers in Human Evolution,” Journal of Human Evolution 133, 2019.
「医療診断なきチンパンジー社会の「障害」について」稲岡司(編)『生態人類学は挑む SESSION3病む・癒す』京都大学学術出版会,2021年.
園田浩司(そのだ こうじ)
新潟大学人文学部・准教授.博士(地域研究).
◎主な著作
『教示の不在——カメルーン狩猟採集社会における「教えない教育」』明石書店,2021年.
「狩猟採集民は教えているか——「教示の不在」という観点から」安藤寿康(編)『教育の起源を探る——進化と文化の視点から』ちとせプレス,2023年.
西川真理(にしかわ まり)
人間環境大学・准教授.博士(理学).
◎主な著作
Nishikawa, M., Suzuki, M., and Sprague, D. S. 2014. “Activity and social factors affect cohesion among individuals in female Japanese macaques: A simultaneous focal-follow study,” American Journal of Primatology, 76(7).
「群れの維持メカニズム」辻大和・中川尚史(編)『日本のサル——哺乳類学としてのニホンザル研究』東京大学出版会,2017年.
鈴木佑記(すずき ゆうき)
国士舘大学・准教授.博士(地域研究).
◎主な著作
『現代の〈漂海民〉——津波後を生きる海民モーケンの民族誌』めこん,2016年.
「海のフロンティア——タイ領アンダマン海における国家・資本・海民の関係性を探る」佐川徹・大澤隆将・池谷和信・岡野英之(編)『フロンティア空間の人類学——統治をめぐる実行力と想像力』ナカニシヤ出版,2025年.
谷口晴香(たにぐち はるか)*
公立鳥取環境大学・講師.博士(理学).
◎主な著作
「ニホンザルのアカンボウの集まり——地域間比較の試み」河合香吏(編)『社会性の起原と進化始論——種と性を越えた比較研究のために』京都大学学術出版会,2025年.
“How the physical properties of food influence its selection by infant Japanese macaques inhabiting a snowcovered area,” American Journal of Primatology 77, 2015.
後藤健志(ごとう たけし)
立命館大学衣笠リサーチオフィス・専門研究員/独立行政法人日本学術振興会・特別研究員(RPD).博士(文学).
◎主な著作
「熱帯ダイズ産業がもたらす世界の単純化——遺伝子組換え種子の内部性と外部性に着目して」『ラテンアメリカ研究年報』43,2023年.
「アマゾニア植民者による空間への知覚と従事——統治の工学にみられる官僚的実践の美学」佐川徹・大澤隆将・池谷和信・岡野英之(編)『フロンティア空間の人類学——統治をめぐる実行力と想像力』ナカニシヤ出版,2025年.
河合文(かわい あや)*
東京外国語大学・准教授.博士(学術).
◎主な著作
『川筋の遊動民バテッ——マレー半島の熱帯林を生きる狩猟採集民』(生態人類学は挑むMONOGRAPH5)京都大学学術出版会,2021.
“Searching for Status in the National Sphere: Among Religions and Ethnicities,” In Ikuya Tokoro & Hisao Tomizawa (eds.) Islam and Cultural Diversity in Southeast Asia (Vol.4). ILCAA. 2024.
川添達朗(かわぞえ たつろう)*
特定非営利活動法人里地里山問題研究所・特任研究員/東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・フェロー.博士(理学).
◎主な著作
「群れの「外」の関わり合い——ニホンザルの互恵性からみる社会」河合香吏(編)『生態人類学は挑むSESSION5関わる・認める』京都大学学術出版会,2022年.
「オスの生活史ならびに社会構造の共通性と多様性」辻大和・中川尚史(編)『日本のサル——哺乳類学としてのニホンザル研究』東京大学出版会,2017年.
岩瀬裕子(いわせ ゆうこ)
東京都立大学人文科学研究科・博士研究員/東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・共同研究員/スペイン国立ルビラ・イ・ビルジリ大学(カタルーニャ州)・訪問研究員/東洋大学健康スポーツ科学部・非常勤講師.博士(社会人類学).
◎主な著作
「「基盤的コミュニズム」のゆらぎと調整——スペイン・カタルーニャ州バイスにある「人間の塔」の継承集団を事例に」『社会人類学年報』弘文堂,2023年.
「こわれるモノが創る〈共〉としての「人間の塔」——安全のための物理的・文化的な技術的実践に着目して」『物質文化』102,2022年.
田島知之(たじま ともゆき)
大阪大学COデザインセンター・特任講師(常勤)/NPO法人日本オランウータンリサーチセンター・理事.博士(理学).
◎主な著作
「群れない類人猿オランウータンの関わり合いから見える「集まらない」社会性」河合香吏(編)『生態人類学は挑むSESSION5関わる・認める』京都大学学術出版会,2022年.
「空飛ぶトカゲと森の人」『はじめてのフィールドワーク1アジア・アフリカの哺乳類編』東海大学出版部,2016年.
八塚春名(やつか はるな)
津田塾大学学芸学部多文化・国際協力学科・准教授.博士(地域研究).
◎主な著作
「タンザニアの狩猟採集民ハッザによる食料獲得戦略の多様化——民族観光と他民族の影響に着目して」『農耕の技術と文化』30,2022年.
“Farming Practices among African Hunter-gatherers: Diversifying without Loss of the Past,” In: Hyden, Goran, Sugimura, Kazuhiko. and Tadasu Tsuruta (eds.) Rethinking African Agriculture: How non-Agrarian Factors Shape Peasant Livelihoods. Routledge, 2020 (Co-author: Ikeya, Kazunobu).
貝ヶ石優(かいがいし ゆう)
京都大学高等研究院・特定研究員.博士(人間科学).
◎主な著作
Yu Kaigaishi, Masayuki Nakamichi, Kazunori Yamada. 2019. “High but not low tolerance populations of Japanese macaques solve a novel cooperative task,” Primates 60(4).
Yu Kaigaishi, Shinya Yamamoto. 2024. “Higher eigenvector centrality in grooming network is linked to better inhibitory control task performance but not orher cognitive tasks in free-ranging Japanese macaques,” Scientific Reports.
藤井真一(ふじい しんいち)
国立民族学博物館・助教.博士(人間科学).
◎主な著作
「暴力の連鎖を断ち切るための術——ソロモン諸島における紛争処理の文化」『季刊民族学』186,2023年.
『生成される平和の民族誌——ソロモン諸島における「民族紛争」と日常性』大阪大学出版会,2021年.
松本卓也(まつもと たくや)
信州大学理学部生物学コース・助教.博士(理学).
◎主な著作
“Opportunistic Feeding Strategy in Wild Immature Chimpanzees: Implications for Children as Active Foragers in Human Evolution,” Journal of Human Evolution 133, 2019.
「医療診断なきチンパンジー社会の「障害」について」稲岡司(編)『生態人類学は挑む SESSION3病む・癒す』京都大学学術出版会,2021年.
園田浩司(そのだ こうじ)
新潟大学人文学部・准教授.博士(地域研究).
◎主な著作
『教示の不在——カメルーン狩猟採集社会における「教えない教育」』明石書店,2021年.
「狩猟採集民は教えているか——「教示の不在」という観点から」安藤寿康(編)『教育の起源を探る——進化と文化の視点から』ちとせプレス,2023年.
西川真理(にしかわ まり)
人間環境大学・准教授.博士(理学).
◎主な著作
Nishikawa, M., Suzuki, M., and Sprague, D. S. 2014. “Activity and social factors affect cohesion among individuals in female Japanese macaques: A simultaneous focal-follow study,” American Journal of Primatology, 76(7).
「群れの維持メカニズム」辻大和・中川尚史(編)『日本のサル——哺乳類学としてのニホンザル研究』東京大学出版会,2017年.
鈴木佑記(すずき ゆうき)
国士舘大学・准教授.博士(地域研究).
◎主な著作
『現代の〈漂海民〉——津波後を生きる海民モーケンの民族誌』めこん,2016年.
「海のフロンティア——タイ領アンダマン海における国家・資本・海民の関係性を探る」佐川徹・大澤隆将・池谷和信・岡野英之(編)『フロンティア空間の人類学——統治をめぐる実行力と想像力』ナカニシヤ出版,2025年.
谷口晴香(たにぐち はるか)*
公立鳥取環境大学・講師.博士(理学).
◎主な著作
「ニホンザルのアカンボウの集まり——地域間比較の試み」河合香吏(編)『社会性の起原と進化始論——種と性を越えた比較研究のために』京都大学学術出版会,2025年.
“How the physical properties of food influence its selection by infant Japanese macaques inhabiting a snowcovered area,” American Journal of Primatology 77, 2015.
後藤健志(ごとう たけし)
立命館大学衣笠リサーチオフィス・専門研究員/独立行政法人日本学術振興会・特別研究員(RPD).博士(文学).
◎主な著作
「熱帯ダイズ産業がもたらす世界の単純化——遺伝子組換え種子の内部性と外部性に着目して」『ラテンアメリカ研究年報』43,2023年.
「アマゾニア植民者による空間への知覚と従事——統治の工学にみられる官僚的実践の美学」佐川徹・大澤隆将・池谷和信・岡野英之(編)『フロンティア空間の人類学——統治をめぐる実行力と想像力』ナカニシヤ出版,2025年.
序論
第Ⅰ部 まとまりのゆらぎ
第1章 〈経済〉が変える親族・家族のかたち―狩猟採集民バテッの「つながり」 [河合文]
はじめに
1 環境・モティリティ・「経済」の変化
2 やり取りの場に立ち現れる関係
おわりに
第2章 組みかわる境界―ニホンザルのオスの空間的まとまりと相互行為 [川添達朗]
はじめに
1 霊長類の社会の類型化
2 調査対象
3 群れの境界
4 オスグループの離合集散と相互行為
おわりに
第3章 協働における「適切な距離」―スペイン・カタルーニャ州の「人間の塔」造りを事例に[岩瀬裕子]
1 協働のなかの「適切な距離」
2 「人間の塔」とその担い手達
3 塔造りの場での工夫
4 ベリャというグループを維持する営み
5 揺れの中で、揺れとともに
第4章 「分かちあい」の進化―オランウータンの雌雄における分配ダイナミクス [田島知之]
はじめに
1 非ヒト霊長類における食物分配行動
2 オランウータンにおける非血縁異性間の食物分配
3 ヒトとその他の霊長類の食物分配の境界
第5章 わけるトウモロコシ、わけない肉―観光に従事する狩猟採集民ハッザの食物分配 [八塚春名]
はじめに
1 ハッザ社会の食物分配―先行研究から
2 調査地の概要とハッザの暮らし
3 マンゴーラに暮らすハッザの食事
4 分配をする/しない
5 現金を消えモノに変える
おわりに
第Ⅱ部 ゆらぐかかわり
第6章 霊長類学における「寛容社会」とは何か? [貝ヶ石優]
はじめに
1 霊長類学において「寛容性」という語はどのように用いられてきたか
2 ニホンザルにおける「寛容性」の地域間変異
3 淡路島のサルに見られる「寛容性」の行動学的評価
4 淡路島集団の「寛容性」に関する考察
おわりに
第7章 もめごとを避ける技、他者を赦す術―ソロモン諸島ガダルカナル島における利害調整と関係操作 [藤井真一]
はじめに
1 調査対象の概要
2 贈与財の授受を伴う関係操作
3 もめごとを避ける技、「他者」を許す術
おわりに
第8章 「生き方」を捉えるものさし―ヒトとチンパンジーの生活史の種間比較を目指して[松本卓也]
1 本章の理論的背景と課題設定
2 トピック①―生活史の要素の抽出方法を統一することの困難さ
3 トピック②―生活史を個体に閉じない社会の中で捉える困難さ
4 トピック③―個体間の生活史の比較に伴う恣意性
5 結びに代えて―「生き方」を描き出す営為
第9章 同化するサル、教示を操るヒト [園田浩司]
1 誰からも教わらない学習
2 狩猟採集民バカ
3 教示を操る学習者
4 考察
第Ⅲ部 環境のゆらぎ
第10章 離れて集まるニホンザルの日常 [西川真理]
はじめに―群れは見つかれど、あの子が見つからない
1 霊長類の群れ
2 霊長類社会の特徴と離合集散性
3 ニホンザルの生態
4 調査地と調査対象
5 小集団のサイズと構成
6 群れメンバーの空間的・時間的な凝集性
7 離れて集まる
おわりに
第11章 狩猟採集民モーケンの離合集散 [鈴木佑記]
1 ホモ・モビリタスとしての人類
2 狩猟採集民のバンド
3 バンドとしてのモーケンの家船集団
4 モーケンの家船移動の背景(1)海賊
5 モーケンの家船移動の背景(2)仲買人
6 定住後における移動の実態
7 霊長類学との対話に向けて
第12章 環境としての他者―ニホンザルのアカンボウの伴食相手の変化を事例に [谷口晴香]
はじめに
1 他者と生きる
2 調査対象・調査地・調査方法
3 誰と伴食するか
4 食べる場所と伴食相手
5 伴食ネットワークの狭まりと拡がり
6 環境としての他者
おわりに
第13章 生態・生理・認知が交わるところ―サイケデリック宗教の観点から考える社会性の進化 [後藤健志]
はじめに
1 象徴をめぐる生命記号論
2 サイケデリックの生理・生態的側面
3 アマゾニアのサイケデリック宗教
4 社会性の調整と維持
おわりに
終章 〈社会性〉の諸相―人類学と霊長類学の接続可能性と特異性 [河合文・川添達朗・谷口晴香]
フィールドの科学としての人類学と霊長類学
〈社会性〉のゆらぎ
おわりに
あとがき
索引
執筆者一覧
第Ⅰ部 まとまりのゆらぎ
第1章 〈経済〉が変える親族・家族のかたち―狩猟採集民バテッの「つながり」 [河合文]
はじめに
1 環境・モティリティ・「経済」の変化
2 やり取りの場に立ち現れる関係
おわりに
第2章 組みかわる境界―ニホンザルのオスの空間的まとまりと相互行為 [川添達朗]
はじめに
1 霊長類の社会の類型化
2 調査対象
3 群れの境界
4 オスグループの離合集散と相互行為
おわりに
第3章 協働における「適切な距離」―スペイン・カタルーニャ州の「人間の塔」造りを事例に[岩瀬裕子]
1 協働のなかの「適切な距離」
2 「人間の塔」とその担い手達
3 塔造りの場での工夫
4 ベリャというグループを維持する営み
5 揺れの中で、揺れとともに
第4章 「分かちあい」の進化―オランウータンの雌雄における分配ダイナミクス [田島知之]
はじめに
1 非ヒト霊長類における食物分配行動
2 オランウータンにおける非血縁異性間の食物分配
3 ヒトとその他の霊長類の食物分配の境界
第5章 わけるトウモロコシ、わけない肉―観光に従事する狩猟採集民ハッザの食物分配 [八塚春名]
はじめに
1 ハッザ社会の食物分配―先行研究から
2 調査地の概要とハッザの暮らし
3 マンゴーラに暮らすハッザの食事
4 分配をする/しない
5 現金を消えモノに変える
おわりに
第Ⅱ部 ゆらぐかかわり
第6章 霊長類学における「寛容社会」とは何か? [貝ヶ石優]
はじめに
1 霊長類学において「寛容性」という語はどのように用いられてきたか
2 ニホンザルにおける「寛容性」の地域間変異
3 淡路島のサルに見られる「寛容性」の行動学的評価
4 淡路島集団の「寛容性」に関する考察
おわりに
第7章 もめごとを避ける技、他者を赦す術―ソロモン諸島ガダルカナル島における利害調整と関係操作 [藤井真一]
はじめに
1 調査対象の概要
2 贈与財の授受を伴う関係操作
3 もめごとを避ける技、「他者」を許す術
おわりに
第8章 「生き方」を捉えるものさし―ヒトとチンパンジーの生活史の種間比較を目指して[松本卓也]
1 本章の理論的背景と課題設定
2 トピック①―生活史の要素の抽出方法を統一することの困難さ
3 トピック②―生活史を個体に閉じない社会の中で捉える困難さ
4 トピック③―個体間の生活史の比較に伴う恣意性
5 結びに代えて―「生き方」を描き出す営為
第9章 同化するサル、教示を操るヒト [園田浩司]
1 誰からも教わらない学習
2 狩猟採集民バカ
3 教示を操る学習者
4 考察
第Ⅲ部 環境のゆらぎ
第10章 離れて集まるニホンザルの日常 [西川真理]
はじめに―群れは見つかれど、あの子が見つからない
1 霊長類の群れ
2 霊長類社会の特徴と離合集散性
3 ニホンザルの生態
4 調査地と調査対象
5 小集団のサイズと構成
6 群れメンバーの空間的・時間的な凝集性
7 離れて集まる
おわりに
第11章 狩猟採集民モーケンの離合集散 [鈴木佑記]
1 ホモ・モビリタスとしての人類
2 狩猟採集民のバンド
3 バンドとしてのモーケンの家船集団
4 モーケンの家船移動の背景(1)海賊
5 モーケンの家船移動の背景(2)仲買人
6 定住後における移動の実態
7 霊長類学との対話に向けて
第12章 環境としての他者―ニホンザルのアカンボウの伴食相手の変化を事例に [谷口晴香]
はじめに
1 他者と生きる
2 調査対象・調査地・調査方法
3 誰と伴食するか
4 食べる場所と伴食相手
5 伴食ネットワークの狭まりと拡がり
6 環境としての他者
おわりに
第13章 生態・生理・認知が交わるところ―サイケデリック宗教の観点から考える社会性の進化 [後藤健志]
はじめに
1 象徴をめぐる生命記号論
2 サイケデリックの生理・生態的側面
3 アマゾニアのサイケデリック宗教
4 社会性の調整と維持
おわりに
終章 〈社会性〉の諸相―人類学と霊長類学の接続可能性と特異性 [河合文・川添達朗・谷口晴香]
フィールドの科学としての人類学と霊長類学
〈社会性〉のゆらぎ
おわりに
あとがき
索引
執筆者一覧