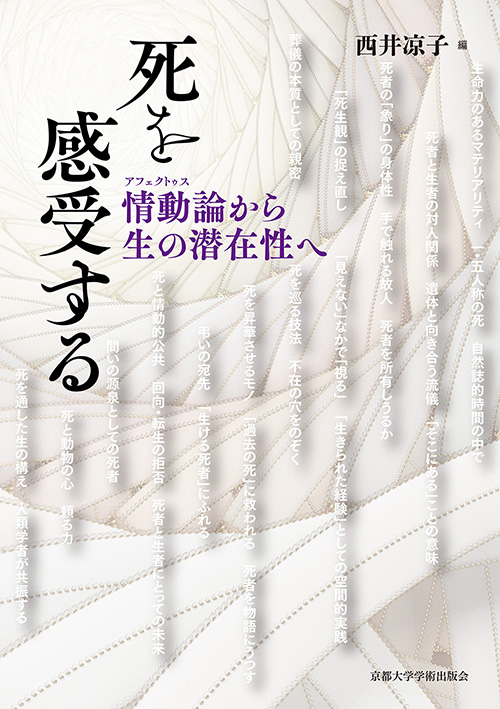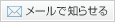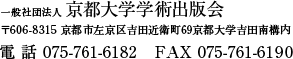ホーム > 書籍詳細ページ
私たちの生は、目の前にはいない「不在」の存在を感受し、彼らとアフェクトしあいつつ生成されている。死という根源的な経験を見据えることで、生を新たな視線から捉えなおし、葬儀の変化、デスマスク、死者をめぐる記憶の語り等の民族誌から、確固としたものにみえていた生から、「こうありえたかもしれない」という別様の生に迫る。
西井 凉子(にしい りょうこ 編者 序章・終章・エッセイ2)
東京外国語大学名誉教授
1959年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程中途退学。博士(文学)。専門は文化人類学、南タイを中心に東南アジア大陸部の社会関係を人々の情動に注目して研究。
主な著作に、『情動のエスノグラフィ』(京都大学学術出版会、2013年)、『アフェクトゥス』(共編著、京都大学学術出版会、2020年)、Community Movemnts in Southeast Asia(共編著、Silkworm Books、2022年)など。
磯野 真穂(いその まほ 第8章)
東京科学大学リベラルアーツ研究教育院教授・一般社団法人De-Silo理事・応用人類学研究所ANTHRO所長
長野県安曇野市出身。早稲田大学人間科学部スポーツ科学科を卒業後、トレーナーの資格を取るべく、オレゴン州立大学スポーツ科学部に学士編入するが自然科学のアプローチに違和感を覚え、文化人類学に専攻を変更。同大学大学院にて応用人類学修士号、早稲田大学にて博士(文学)取得。
単著に、『なぜふつうに食べられないのか』(春秋社、2015年、多文化間精神医学会奨励賞等受賞)、『コロナ禍と出会い直す』(柏書房、2024年、第33回山本七平賞受賞)、共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社、2019年、共著者宮野真生子)などがある。
瓜生 大輔(うりう だいすけ 第4章)
芝浦工業大学デザイン工学部准教授
1983年生まれ。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科博士課程修了。博士(メディアデザイン学)。ヒューマン・コンピューター・インタラクション(HCI)デザイン研究を主軸に、宗教学、文化人類学などの視座を取り入れながら死者祭祀・弔いのためのデザインに取り組む。国際会議ACM CHIフルペーパーで3度のHonorable Mention受賞。
主な著作に、「デジタル故人情報リテラシー」(『世界』984号、2024年)など。
加賀谷 真梨(かがや まり 第3章)
上智大学文学部特任准教授
お茶の水女子大学大学院現代社会文化研究科博士後期課程修了。博士(社会科学)。専門は文化人類学、民俗学。南西諸島を中心にケアを切り口に家族と地域社会の関係に注目して研究。
主な著作に、『現代日本の「看取り文化」を構想する』(分担執筆、東京大学出版会、2022年)、「地域福祉が変える死のかたち」(『比較家族史研究』35号、2021年)など。
金 セッピョル(きむ せっぴょる 第5章)
甲南大学文学部社会学科講師
1983年生まれ。総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門は文化人類学、映像人類学。日本と韓国を中心に、現代の死生観と葬送儀礼について研究。
主な著作に、『現代日本における自然葬の民族誌』(刀水書房、2019年)、『葬いとカメラ』(共編著、左右社、2021年)、展示に「死を肖像する」(共催、2024年)など。
黒田 末寿(くろだ すえひさ 第9章)
滋賀県立大学名誉教授。
1947年生まれ、専門は人類学、霊長類学。地域学。ボノボ研究のパイオニア。近年は焼畑の実践研究に打ち込んでいる。
主な著作に『人類進化再考』(以文社、1999年)、『自然学の未来』(弘文堂、2002年)、Affectus: A Journey on the Outside of Life(分担執筆、Kyoto Univ. Press & Trans Pacific Press、2023)など。
田井 みのり(たい みのり エッセイ1)
東京都立大学大学院人文科学研究科博士後期課程。
専門は文化人類学や音楽人類学。日本や台湾の儀礼、特に葬儀における音楽実践について研究している。
主な著作に、「現代日本における音楽葬の布置」(『文化人類学』90―2号、2025年)、「愛着の技術としての音楽」(『白山人類学』27号、2024年)、『客家と日本』(分担執筆、風響社、2024年)など。
高木 良子(たかぎ りょうこ 第2章)
東京科学大学JST「ケアが根づく社会システム」研究開発領域「人間と非人間の惑星的ケア」研究開発プロジェクト博士研究員
1975年生まれ。東京科学大学博士後期課程在籍。専門は文化人類学、「弔いとテクノロジー」をテーマに、AI故人や遺人形などのテクノロジーを用いた死者の表象への心性を研究。
主な著作に、「故人を模した人形における死者の見顕し――AI美空ひばりとの比較において」(『コモンズ』3号、2024年)、『死者とテクノロジー』(共著、ミシマ社、2025年)など。
田中 大介(たなか だいすけ 第1章)
自治医科大学医学部教授
1972年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門は人類学。日本を中心とする葬制および葬儀業の調査を通じて「死をめぐる現代文化」を研究。
主な著作に、『葬儀業のエスノグラフィ』(東京大学出版会、2017年)など。
土佐 桂子(とさ けいこ 第7章)
東京外国語大学名誉教授
1957年生まれ。総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門は文化人類学。ミャンマーの宗教、宗教を基盤とした福祉活動、それらから派生する運動に関心を持つ。
主な著作に、『ビルマのウェイザー信仰』(勁草書房、2000年)、『転換期のミャンマーを生きる』(共編著、風響社、2020年)、Champions of Buddhism : Weikza Cults in Contemporary Burma(共著、National University of Singapore Press、2014年)など。
丹羽 朋子(にわ ともこ 第6章)
国際ファッション専門職大学准教授
東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。専門は文化人類学。災厄の記憶をめぐる表現活動、中国や日本のものづくり文化、映像・展示等を用いた民族誌の方法論を研究。
震災表現や映像活用に関する著作に、『〈動物をえがく〉人類学』(分担執筆、岩波書店、2024年)、『わざの人類学』(分担執筆、京都大学学術出版会、2021年)、『災害文化の継承と創造』(分担執筆、臨川書店、2016年)など。
東京外国語大学名誉教授
1959年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程中途退学。博士(文学)。専門は文化人類学、南タイを中心に東南アジア大陸部の社会関係を人々の情動に注目して研究。
主な著作に、『情動のエスノグラフィ』(京都大学学術出版会、2013年)、『アフェクトゥス』(共編著、京都大学学術出版会、2020年)、Community Movemnts in Southeast Asia(共編著、Silkworm Books、2022年)など。
磯野 真穂(いその まほ 第8章)
東京科学大学リベラルアーツ研究教育院教授・一般社団法人De-Silo理事・応用人類学研究所ANTHRO所長
長野県安曇野市出身。早稲田大学人間科学部スポーツ科学科を卒業後、トレーナーの資格を取るべく、オレゴン州立大学スポーツ科学部に学士編入するが自然科学のアプローチに違和感を覚え、文化人類学に専攻を変更。同大学大学院にて応用人類学修士号、早稲田大学にて博士(文学)取得。
単著に、『なぜふつうに食べられないのか』(春秋社、2015年、多文化間精神医学会奨励賞等受賞)、『コロナ禍と出会い直す』(柏書房、2024年、第33回山本七平賞受賞)、共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社、2019年、共著者宮野真生子)などがある。
瓜生 大輔(うりう だいすけ 第4章)
芝浦工業大学デザイン工学部准教授
1983年生まれ。慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科博士課程修了。博士(メディアデザイン学)。ヒューマン・コンピューター・インタラクション(HCI)デザイン研究を主軸に、宗教学、文化人類学などの視座を取り入れながら死者祭祀・弔いのためのデザインに取り組む。国際会議ACM CHIフルペーパーで3度のHonorable Mention受賞。
主な著作に、「デジタル故人情報リテラシー」(『世界』984号、2024年)など。
加賀谷 真梨(かがや まり 第3章)
上智大学文学部特任准教授
お茶の水女子大学大学院現代社会文化研究科博士後期課程修了。博士(社会科学)。専門は文化人類学、民俗学。南西諸島を中心にケアを切り口に家族と地域社会の関係に注目して研究。
主な著作に、『現代日本の「看取り文化」を構想する』(分担執筆、東京大学出版会、2022年)、「地域福祉が変える死のかたち」(『比較家族史研究』35号、2021年)など。
金 セッピョル(きむ せっぴょる 第5章)
甲南大学文学部社会学科講師
1983年生まれ。総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門は文化人類学、映像人類学。日本と韓国を中心に、現代の死生観と葬送儀礼について研究。
主な著作に、『現代日本における自然葬の民族誌』(刀水書房、2019年)、『葬いとカメラ』(共編著、左右社、2021年)、展示に「死を肖像する」(共催、2024年)など。
黒田 末寿(くろだ すえひさ 第9章)
滋賀県立大学名誉教授。
1947年生まれ、専門は人類学、霊長類学。地域学。ボノボ研究のパイオニア。近年は焼畑の実践研究に打ち込んでいる。
主な著作に『人類進化再考』(以文社、1999年)、『自然学の未来』(弘文堂、2002年)、Affectus: A Journey on the Outside of Life(分担執筆、Kyoto Univ. Press & Trans Pacific Press、2023)など。
田井 みのり(たい みのり エッセイ1)
東京都立大学大学院人文科学研究科博士後期課程。
専門は文化人類学や音楽人類学。日本や台湾の儀礼、特に葬儀における音楽実践について研究している。
主な著作に、「現代日本における音楽葬の布置」(『文化人類学』90―2号、2025年)、「愛着の技術としての音楽」(『白山人類学』27号、2024年)、『客家と日本』(分担執筆、風響社、2024年)など。
高木 良子(たかぎ りょうこ 第2章)
東京科学大学JST「ケアが根づく社会システム」研究開発領域「人間と非人間の惑星的ケア」研究開発プロジェクト博士研究員
1975年生まれ。東京科学大学博士後期課程在籍。専門は文化人類学、「弔いとテクノロジー」をテーマに、AI故人や遺人形などのテクノロジーを用いた死者の表象への心性を研究。
主な著作に、「故人を模した人形における死者の見顕し――AI美空ひばりとの比較において」(『コモンズ』3号、2024年)、『死者とテクノロジー』(共著、ミシマ社、2025年)など。
田中 大介(たなか だいすけ 第1章)
自治医科大学医学部教授
1972年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門は人類学。日本を中心とする葬制および葬儀業の調査を通じて「死をめぐる現代文化」を研究。
主な著作に、『葬儀業のエスノグラフィ』(東京大学出版会、2017年)など。
土佐 桂子(とさ けいこ 第7章)
東京外国語大学名誉教授
1957年生まれ。総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門は文化人類学。ミャンマーの宗教、宗教を基盤とした福祉活動、それらから派生する運動に関心を持つ。
主な著作に、『ビルマのウェイザー信仰』(勁草書房、2000年)、『転換期のミャンマーを生きる』(共編著、風響社、2020年)、Champions of Buddhism : Weikza Cults in Contemporary Burma(共著、National University of Singapore Press、2014年)など。
丹羽 朋子(にわ ともこ 第6章)
国際ファッション専門職大学准教授
東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。専門は文化人類学。災厄の記憶をめぐる表現活動、中国や日本のものづくり文化、映像・展示等を用いた民族誌の方法論を研究。
震災表現や映像活用に関する著作に、『〈動物をえがく〉人類学』(分担執筆、岩波書店、2024年)、『わざの人類学』(分担執筆、京都大学学術出版会、2021年)、『災害文化の継承と創造』(分担執筆、臨川書店、2016年)など。
序章 死という経験
——情動論からの探求
[西井凉子]
1 死という根源的経験
2 死の人類学研究における本書の位置づけ
3 情動(アフェクトゥス)論的視座から
4 本書の構成
I 死のマテリアリティ
1章 そのご遺体はナマです
——葬儀業の仕事にみるナマ感覚のアンビヴァレンス
[田中大介]
1 ナマの遺体
2 予察
3 遺体と向き合う流儀
4 死者の人格
5 身体とモノの境界線
6 そこにある、ということ
2章 死者の「顔」と出会い直す
——現代のデスマスクをめぐって
[高木良子]
1 デスマスクの歴史と顔
2 現代日本のデスマスク
3 調査の対象と方法
4 現代のデスマスクをめぐる人々
5 デスマスクの身体性
6 死者の所有
II 身体と生きる場
3章 なぜ住み慣れた地域で最期を迎えたいのか
——沖縄・池間島における生と死の潜在性
[加賀谷真梨]
1 「住み慣れた地域でいつまでも」をめぐる問い
2 島で暮らし続けるための仕組みづくり
3 「見えない」なかで「視る」くらし
4 大気の問いかけ――空間的実践としての禁忌
5 住み慣れた地域で最期を迎えるとは
4章 家族水入らずのバーチャル葬儀
[瓜生大輔]
1 祖母との「対面」
2 バーチャル葬儀の動向
3 S家葬儀の背景
4 S家のバーチャル葬儀
5 バーチャル葬儀のゆくえ
6 遺族と事業者の協働によるバーチャル葬儀
エッセイ1 死と音楽のアフェクト
[田井みのり]
1 ある葬儀について
2 生者と死者を媒介する音楽のアフェクト
3 セレモニプレイヤーの紡ぐ音と死者とのアフェクトの連鎖
III 死をめぐる個と集合性
5章 喪輿小屋で「昇華」される死
——死の集合性と物質性に関する考察
[金セッピョル]
1 喪輿小屋がある風景
2 喪輿小屋とアフェクトする
3 喪輿小屋にみる死の集合性と物質性
6章 津波による〈死者〉とともに創りつなぐ表現の形
[丹羽朋子]
1 遠い死/死者をめぐる問い
2 津波による〈死者〉との隔たりに向き合う
3 災禍の〈死者〉をうつす表現の課題
4 死者と生者の生きる世界の切り分けに抗して
5 見えざる〈死者〉にふれる弔いの形
6 〈死者〉とともに綴る手紙
7 「生ける死者」とともに創りつなぐ表現の形
7章 民主化運動における「死」
——ソーシャルメディアと情動
[土佐桂子]
1 死を伝えること、そして情動的公共
2 抗議運動における死と弔い方、そして暴力
3 死者を記憶する、死者と向き合う
4 慣習仏教実践の否定、あるいは延期
5 死者によりそうこと
エッセイ2 カオ・トムの記憶
――現在に潜在する死者たち
[西井凉子]
1 パタニ事件とカオ・トム287
2 「不在の穴」290
3 タイ社会における事件の位置づけ291
4 その後のウィットの来歴293
5 トラウマと時間性298
6 現在に潜在する死者たち299
Ⅳ 死と時間性——死者とともにあること
8章 言葉が言葉でなくなる時
——語りを引き継ぎ、死者とともに生きることについての一考察
[磯野真穂]
1 心に残る言葉とは何か――本章の立ち位置
2 宮野の生前――言葉に打ちのめされる時
3 意図から考える心に残る言葉――文脈共有の不可能性
4 宮野の死後――心に残る言葉の不可知性とその価値
5 死者とともに生きるということ
9章 悲嘆の自然誌
[黒田末寿]
1 喪失による悲嘆の普遍性
2 悲嘆にならない悲嘆
3 悲嘆の共有の言葉
4 動物たちの喪失の悲嘆
5 進む動物の理解と人獣の境界の解消
6 悲嘆の歯止め
7 ボノボの子どもの感覚遮断
8 悲嘆を生き延びる「ひとなつっこさ」ないし「頼る力」
終章 死を感受する
——情動論から生の潜在性へ
[西井凉子]
1 情動(アフェクト)論的視座から
2 死のマテリアリティ
3 身体とバーチャリティ
4 死をめぐる個と集合性
5 死と時間性
6 死者とともにあること――生きる世界における死者
あとがき
索引
——情動論からの探求
[西井凉子]
1 死という根源的経験
2 死の人類学研究における本書の位置づけ
3 情動(アフェクトゥス)論的視座から
4 本書の構成
I 死のマテリアリティ
1章 そのご遺体はナマです
——葬儀業の仕事にみるナマ感覚のアンビヴァレンス
[田中大介]
1 ナマの遺体
2 予察
3 遺体と向き合う流儀
4 死者の人格
5 身体とモノの境界線
6 そこにある、ということ
2章 死者の「顔」と出会い直す
——現代のデスマスクをめぐって
[高木良子]
1 デスマスクの歴史と顔
2 現代日本のデスマスク
3 調査の対象と方法
4 現代のデスマスクをめぐる人々
5 デスマスクの身体性
6 死者の所有
II 身体と生きる場
3章 なぜ住み慣れた地域で最期を迎えたいのか
——沖縄・池間島における生と死の潜在性
[加賀谷真梨]
1 「住み慣れた地域でいつまでも」をめぐる問い
2 島で暮らし続けるための仕組みづくり
3 「見えない」なかで「視る」くらし
4 大気の問いかけ――空間的実践としての禁忌
5 住み慣れた地域で最期を迎えるとは
4章 家族水入らずのバーチャル葬儀
[瓜生大輔]
1 祖母との「対面」
2 バーチャル葬儀の動向
3 S家葬儀の背景
4 S家のバーチャル葬儀
5 バーチャル葬儀のゆくえ
6 遺族と事業者の協働によるバーチャル葬儀
エッセイ1 死と音楽のアフェクト
[田井みのり]
1 ある葬儀について
2 生者と死者を媒介する音楽のアフェクト
3 セレモニプレイヤーの紡ぐ音と死者とのアフェクトの連鎖
III 死をめぐる個と集合性
5章 喪輿小屋で「昇華」される死
——死の集合性と物質性に関する考察
[金セッピョル]
1 喪輿小屋がある風景
2 喪輿小屋とアフェクトする
3 喪輿小屋にみる死の集合性と物質性
6章 津波による〈死者〉とともに創りつなぐ表現の形
[丹羽朋子]
1 遠い死/死者をめぐる問い
2 津波による〈死者〉との隔たりに向き合う
3 災禍の〈死者〉をうつす表現の課題
4 死者と生者の生きる世界の切り分けに抗して
5 見えざる〈死者〉にふれる弔いの形
6 〈死者〉とともに綴る手紙
7 「生ける死者」とともに創りつなぐ表現の形
7章 民主化運動における「死」
——ソーシャルメディアと情動
[土佐桂子]
1 死を伝えること、そして情動的公共
2 抗議運動における死と弔い方、そして暴力
3 死者を記憶する、死者と向き合う
4 慣習仏教実践の否定、あるいは延期
5 死者によりそうこと
エッセイ2 カオ・トムの記憶
――現在に潜在する死者たち
[西井凉子]
1 パタニ事件とカオ・トム287
2 「不在の穴」290
3 タイ社会における事件の位置づけ291
4 その後のウィットの来歴293
5 トラウマと時間性298
6 現在に潜在する死者たち299
Ⅳ 死と時間性——死者とともにあること
8章 言葉が言葉でなくなる時
——語りを引き継ぎ、死者とともに生きることについての一考察
[磯野真穂]
1 心に残る言葉とは何か――本章の立ち位置
2 宮野の生前――言葉に打ちのめされる時
3 意図から考える心に残る言葉――文脈共有の不可能性
4 宮野の死後――心に残る言葉の不可知性とその価値
5 死者とともに生きるということ
9章 悲嘆の自然誌
[黒田末寿]
1 喪失による悲嘆の普遍性
2 悲嘆にならない悲嘆
3 悲嘆の共有の言葉
4 動物たちの喪失の悲嘆
5 進む動物の理解と人獣の境界の解消
6 悲嘆の歯止め
7 ボノボの子どもの感覚遮断
8 悲嘆を生き延びる「ひとなつっこさ」ないし「頼る力」
終章 死を感受する
——情動論から生の潜在性へ
[西井凉子]
1 情動(アフェクト)論的視座から
2 死のマテリアリティ
3 身体とバーチャリティ
4 死をめぐる個と集合性
5 死と時間性
6 死者とともにあること――生きる世界における死者
あとがき
索引