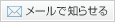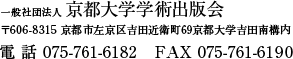ホーム > 書籍詳細ページ
「法に触れる」という言葉に象徴されるように,我々日本人は,極力,法と関わらないで生きることを良しとしてきた.しかし,グローバルスタンダードが日常生活の中でも求められる今日,そうした法意識を大きく変えることが求められている.中小企業の現場を舞台に日本人の法意識と法の実効性を明らかにする.<国際化>時代の法のあり方を示す,日欧共同研究の成果.
編 者
O. Univ. -Prof. Dr. Theodor Tomandl(テオドール・トーマンドル)
ウィーン大学法学部教授(第5章)
1933年1月24日生まれ 1955年ウィーン大学にて法学博士の学位を取得後、連邦商工会議所研究部の部長を経て、1968年からウィーン大学法学部労働法・社会保障法講座の主任教授となり現在に至る。
以下の他、多数の著作がある。 Streik und Aussperrung als Mittel des Arbeitskampfes, 1965 Wesensmerkmale des Arbeitsvertrages, 1971 Rechtsstaat Osterreich : Illusion oder Realitat ? 1997
村中孝史
京都大学大学院法学研究科教授(序章、第4章、第9章)
1957年5月3日生まれ
1986年京都大学大学院法学研究科博士後期過程単位取得認定退学後、京都大学法学部助手、同助教授を経て、1995年より現職。
最近の論文として、次のようなものがある。
「個別的人事処遇の法的問題点」日本労働研究雑誌460号(1998年) 「日本的雇用慣行の変容と解雇制限法理」民商法雑誌119巻4-5号(1999年) 「労働契約概念について」『京都大学法学部創立百周年記念論文集第3巻』(1999年)
執筆者
服部高宏 岡山大学法学部教授(第1章)
田中成明 京都大学大学院法学研究科教授(第2章)
O. Univ. -Prof. Dr. Gerhard Luf(ゲルハルト・ルーフ) ウィーン大学法学部教授(第3章)
荒山裕行 名古屋大学経済学部助教授(第6章)
瀧 敦弘 広島大学経済学部助教授(第4章、第7章)
Hon. Prof. Dr. Gottfried Winkler(ゴットフリート・ヴィンクラー) オーストリア連邦商工会議所教育政策・科学部部員 ウィーン大学法学部名誉教授(非常勤)(第8章)
下井隆史 大阪学院大学法学部教授(第10章)
Univ. -Prof. Mag. Dr. Wolfgang Mazal(ヴォルフガング・マーツァール) ウィーン大学法学部教授(第11章)
西村健一郎 京都大学総合人間学部教授(第12章)
o. Univ. -Prof. Dr. Franz Schrank(フランツ・シュランク)シュタイヤーマルク商工会議所社会政策部部長 ウィーン大学法学部教授(非常勤)(第13章)
訳 者
皆川宏之 京都大学大学院法学研究科博士後期過程院生(第5章)
高畠淳子 京都大学大学院人間環境学研究科博士後期過程院生(第8章)
津田小百合 京都大学大学院人間環境学研究科博士後期過程院生(第13章))
カールフーバー=吉田万里子 ウィーン大学法学部学生(第13章)
O. Univ. -Prof. Dr. Theodor Tomandl(テオドール・トーマンドル)
ウィーン大学法学部教授(第5章)
1933年1月24日生まれ 1955年ウィーン大学にて法学博士の学位を取得後、連邦商工会議所研究部の部長を経て、1968年からウィーン大学法学部労働法・社会保障法講座の主任教授となり現在に至る。
以下の他、多数の著作がある。 Streik und Aussperrung als Mittel des Arbeitskampfes, 1965 Wesensmerkmale des Arbeitsvertrages, 1971 Rechtsstaat Osterreich : Illusion oder Realitat ? 1997
村中孝史
京都大学大学院法学研究科教授(序章、第4章、第9章)
1957年5月3日生まれ
1986年京都大学大学院法学研究科博士後期過程単位取得認定退学後、京都大学法学部助手、同助教授を経て、1995年より現職。
最近の論文として、次のようなものがある。
「個別的人事処遇の法的問題点」日本労働研究雑誌460号(1998年) 「日本的雇用慣行の変容と解雇制限法理」民商法雑誌119巻4-5号(1999年) 「労働契約概念について」『京都大学法学部創立百周年記念論文集第3巻』(1999年)
執筆者
服部高宏 岡山大学法学部教授(第1章)
田中成明 京都大学大学院法学研究科教授(第2章)
O. Univ. -Prof. Dr. Gerhard Luf(ゲルハルト・ルーフ) ウィーン大学法学部教授(第3章)
荒山裕行 名古屋大学経済学部助教授(第6章)
瀧 敦弘 広島大学経済学部助教授(第4章、第7章)
Hon. Prof. Dr. Gottfried Winkler(ゴットフリート・ヴィンクラー) オーストリア連邦商工会議所教育政策・科学部部員 ウィーン大学法学部名誉教授(非常勤)(第8章)
下井隆史 大阪学院大学法学部教授(第10章)
Univ. -Prof. Mag. Dr. Wolfgang Mazal(ヴォルフガング・マーツァール) ウィーン大学法学部教授(第11章)
西村健一郎 京都大学総合人間学部教授(第12章)
o. Univ. -Prof. Dr. Franz Schrank(フランツ・シュランク)シュタイヤーマルク商工会議所社会政策部部長 ウィーン大学法学部教授(非常勤)(第13章)
訳 者
皆川宏之 京都大学大学院法学研究科博士後期過程院生(第5章)
高畠淳子 京都大学大学院人間環境学研究科博士後期過程院生(第8章)
津田小百合 京都大学大学院人間環境学研究科博士後期過程院生(第13章))
カールフーバー=吉田万里子 ウィーン大学法学部学生(第13章)
序章 「法化」の進行と中小企業(村中孝史)
序-1 中小企業に見られる法とのつきあい方
序-2 本書の出発点
序-3 グローバリゼーションと法化
序-4 グローバリゼーションと雇用慣行
序-5 中小企業の労使関係と法化の進行
序-6 法化がもたらす問題点
序-7 オーストリアとの比較
第1部 法意識と法知識
第1章 日本社会における法意識と法の実効性(服部高宏)
1-1 はじめに
1-2 日本人の法意識と紛争処理方式
1-3 日本社会と法システム
1-4 法の実効性と妥当性
1-5 法化社会における法の実効性
第2章 日本人の法観念 ——その過去,現在,そして将来(田中成明)
2-1 はじめに
2-2 日本と西欧の法観念の比較のためのモデル
2-3 日本の伝統的な法の見方
2-4 日本における法の近代化
2-5 最近の法観念・法実務の動向
2-6 むすび
第3章 現代法治国家・社会国家における法の実効性(ゲルハルト・ルーフ)
第4章 中小企業における労働法の実施状況と当事者の意識
——アンケート調査の結果から(村中孝史・瀧 敦弘)
4-1 調査の目的と調査対象
4-2 回答者の属性
4-3 集団的労使関係について
4-4 無組合企業における労働条件決定
4-5 個別法上のルールに関する知識
4-6 労働法に対する全般的評価
4-7 オーストリアでの調査結果との比較
4-8 おわりに
第5章 オーストリアの中小事業所における労働法の知識(テオドール・トーマンドル)
5-1 はじめに
5-2 主な結果
5-3 結論
第2部 中小企業における労使関係と法運用
第6章 日本経済の発展と中小企業政策
——「格差是正」から「ダイナミズムの源泉」へ(荒山裕行)
6-1 中小企業の何が問題であったのか
6-2 中小企業政策の展開
6-3 中小企業の現状
6-4 経済の活性化と雇用の創出
第7章 日本における中小企業の雇用と労使関係(瀧 敦弘)
7-1 労働移動
7-2 賃金
7-3 労働時間制度の規模間比較
7-4 中小企業の労使関係
第8章 中小企業の経済的意義とヨーロッパ法(ゴットフリート・ヴィンクラー)
8-1 中小企業の経済的意義
8-2 ヨーロッパ労働・社会法と中小企業
8-3 総括
第9章 日本における中小企業と労働法(村中孝史)
9-1 はじめに
9-2 制定法における中小企業
9-3 判例法理における中小企業
9-4 中小企業における労働法をめぐっての検討課題
9-5 おわりに
第10章 中小企業と労働法
——近時の法改正を契機として(下井隆史)
10-1 はじめに
10-2 個別的労働関係法の改革と中小企業労働関係
10-3 中小企業労使における労働法知識の問題
第11章 中小企業をめぐる労働法上の問題点(ヴォルフガング・マーツァール)
11-1 はじめに
11-2 オーストリアにおける中小企業概念と意義
11-3 労働法における中小企業
11-4 当事者からみた中小企業における労働法上の諸問題
11-5 法的議論の手がかり
第12章 中小企業労働者の社会保障
——とくに社会保険の適用について(西村健一郎)
12-1 はじめに
12-2 問題意識——中小企業労働者と社会保険
12-3 医療保険
12-4 年金保険の適用
12-5 雇用保険
12-6 労災保険
12-7 結びにかえて
第13章 中小企業における社会保障(フランツ・シュランク)
13-1 被用者社会保険と労働法の実施
13-2 自営業者の強制保険——「小規模自営業者」に対する負担軽減
13-3 年金保険——「小規模自営業者」に対して(のみ)の職業保護
13-4 特定の「小規模自営業者」に対する保護の欠如
13-5 まとめ
あとがき
索引
附 「企業実務における労働法実施状況調査」票
序-1 中小企業に見られる法とのつきあい方
序-2 本書の出発点
序-3 グローバリゼーションと法化
序-4 グローバリゼーションと雇用慣行
序-5 中小企業の労使関係と法化の進行
序-6 法化がもたらす問題点
序-7 オーストリアとの比較
第1部 法意識と法知識
第1章 日本社会における法意識と法の実効性(服部高宏)
1-1 はじめに
1-2 日本人の法意識と紛争処理方式
1-3 日本社会と法システム
1-4 法の実効性と妥当性
1-5 法化社会における法の実効性
第2章 日本人の法観念 ——その過去,現在,そして将来(田中成明)
2-1 はじめに
2-2 日本と西欧の法観念の比較のためのモデル
2-3 日本の伝統的な法の見方
2-4 日本における法の近代化
2-5 最近の法観念・法実務の動向
2-6 むすび
第3章 現代法治国家・社会国家における法の実効性(ゲルハルト・ルーフ)
第4章 中小企業における労働法の実施状況と当事者の意識
——アンケート調査の結果から(村中孝史・瀧 敦弘)
4-1 調査の目的と調査対象
4-2 回答者の属性
4-3 集団的労使関係について
4-4 無組合企業における労働条件決定
4-5 個別法上のルールに関する知識
4-6 労働法に対する全般的評価
4-7 オーストリアでの調査結果との比較
4-8 おわりに
第5章 オーストリアの中小事業所における労働法の知識(テオドール・トーマンドル)
5-1 はじめに
5-2 主な結果
5-3 結論
第2部 中小企業における労使関係と法運用
第6章 日本経済の発展と中小企業政策
——「格差是正」から「ダイナミズムの源泉」へ(荒山裕行)
6-1 中小企業の何が問題であったのか
6-2 中小企業政策の展開
6-3 中小企業の現状
6-4 経済の活性化と雇用の創出
第7章 日本における中小企業の雇用と労使関係(瀧 敦弘)
7-1 労働移動
7-2 賃金
7-3 労働時間制度の規模間比較
7-4 中小企業の労使関係
第8章 中小企業の経済的意義とヨーロッパ法(ゴットフリート・ヴィンクラー)
8-1 中小企業の経済的意義
8-2 ヨーロッパ労働・社会法と中小企業
8-3 総括
第9章 日本における中小企業と労働法(村中孝史)
9-1 はじめに
9-2 制定法における中小企業
9-3 判例法理における中小企業
9-4 中小企業における労働法をめぐっての検討課題
9-5 おわりに
第10章 中小企業と労働法
——近時の法改正を契機として(下井隆史)
10-1 はじめに
10-2 個別的労働関係法の改革と中小企業労働関係
10-3 中小企業労使における労働法知識の問題
第11章 中小企業をめぐる労働法上の問題点(ヴォルフガング・マーツァール)
11-1 はじめに
11-2 オーストリアにおける中小企業概念と意義
11-3 労働法における中小企業
11-4 当事者からみた中小企業における労働法上の諸問題
11-5 法的議論の手がかり
第12章 中小企業労働者の社会保障
——とくに社会保険の適用について(西村健一郎)
12-1 はじめに
12-2 問題意識——中小企業労働者と社会保険
12-3 医療保険
12-4 年金保険の適用
12-5 雇用保険
12-6 労災保険
12-7 結びにかえて
第13章 中小企業における社会保障(フランツ・シュランク)
13-1 被用者社会保険と労働法の実施
13-2 自営業者の強制保険——「小規模自営業者」に対する負担軽減
13-3 年金保険——「小規模自営業者」に対して(のみ)の職業保護
13-4 特定の「小規模自営業者」に対する保護の欠如
13-5 まとめ
あとがき
索引
附 「企業実務における労働法実施状況調査」票