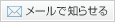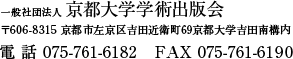ホーム > 書籍詳細ページ

ユーロへの挑戦
四六上製・396頁
ISBN: 9784876987269
発行年月: 2007/09
小島 明氏(日本経済研究センター会長)推薦
地域統合の実現には,これまでの市場主導を超えた,政治的なビジョンと意志が不可欠である。東アジアでは1997年通貨危機を起点として飛躍的に連帯意識を高めるなか「共同体」への構想が議論され始めた。他方,ヨーロッパでは当初から政治が通貨統合を主導し,単一通貨「ユーロ」を生み出すに至った。ヨーロッパ統合という,半世紀に及ぶ歴史的なドラマの主役の1人であるティートマイヤー氏の証言は,我々の選択に得がたい示唆を与えてくれる。
共通通貨・ユーロはいかにして成立したか。通貨名,交換レート,首脳人事……ことごとく対立するフランスとドイツ。その舞台裏では,主導権を巡る激しい駆け引きが繰り広げられていた。ドイツ連邦銀行の元総裁ハンス・ティートマイヤーが明かす通貨統合の交渉史。将来,アジア通貨統合の一翼を担う日本にとって最上の教訓がここにある。
『週刊エコノミスト』’07年10月16日号、66頁、評者:榊原英資氏
『日本経済新聞』'07年10月28日朝刊、25面、評者:滝田洋一氏
『週刊ダイヤモンド』'07年11月17日号、79頁、評者:行天豊雄氏
『金融財政事情』'07年11月19日号、64頁、評者:渡辺博史氏
『日本経済研究センター会報』'07年12月号、90頁、評者:清野一治氏
『日本経済新聞』'07年10月28日朝刊、25面、評者:滝田洋一氏
『週刊ダイヤモンド』'07年11月17日号、79頁、評者:行天豊雄氏
『金融財政事情』'07年11月19日号、64頁、評者:渡辺博史氏
『日本経済研究センター会報』'07年12月号、90頁、評者:清野一治氏
[著者紹介]
ハンス・ティートマイヤー(Hans Tietmeyer)
1931年生まれ。1960年政治学博士(ケルン大学)。1962年にドイツ連邦経済省入省。1982—89年ドイツ連邦大蔵省次官。1990年ドイツ連邦銀行理事となり、1993年総裁就任。1999年に総裁職を退任してのち、現在は欧州ビジネス・スクール学長、国際決済銀行副総裁、IMF金融安定フォーラム委員など役職多数。ほぼ40年間にわたって欧州通貨統合問題を直接担当する。ドイツ連邦共和国大功労十字章、わが国の旭日大綬章を授与される。
[監訳者紹介]
財団法人 国際通貨研究所
1995年に東京銀行(現三菱東京UFJ銀行)によって設立された公益法人。国際金融・国際通貨について、シンポジウムの開催、出版物の刊行や調査研究の実施を通じて、国内外での質の高い情報提供と政策提言のための活動を行っている。理事長は大蔵省財務官、東京銀行会長などを歴任した三菱東京UFJ銀行特別顧問の行天豊雄。
ホームページURL:http://www.iima.or.jp
村瀬 哲司(むらせ・てつじ)
1945年生まれ。1968年、一橋大学商学部卒業。東京銀行、東京三菱銀行調査部長を経て、現在京都大学国際交流センター教授。2001年、京都大学学位取得(経済学博士)。
著 書:『アジア安定通貨圏—ユーロに学ぶ円の役割—』勁草書房、2000年
『東アジアの通貨・金融協力—欧州の経験を未来に活かす—』勁草書房、2007年
A Zone of Asian Monetary Stability, Asia Pacific Press, 2002. 他共著多数
翻 訳:『マルクの幻想—ドイツ連銀の栄光と苦悩』D.バルクハウゼン著、日本経済新聞社、1993年
[訳者紹介]
山木 一之(やまき・かずゆき)
1949年生まれ。1974年、岡山大学中退、外務省入省。ドイツキール大学で研修後、在東ドイツ日本国大使館、在フランクフルト日本国総領事館などに勤務。2005年病気のため退職。現在ドイツ関係のアクチュアルなテーマの翻訳に従事。
論 文:「独仏関係は大西洋関係にいかに影響するか」(『外交フォーラム』1993年8月号)
ハンス・ティートマイヤー(Hans Tietmeyer)
1931年生まれ。1960年政治学博士(ケルン大学)。1962年にドイツ連邦経済省入省。1982—89年ドイツ連邦大蔵省次官。1990年ドイツ連邦銀行理事となり、1993年総裁就任。1999年に総裁職を退任してのち、現在は欧州ビジネス・スクール学長、国際決済銀行副総裁、IMF金融安定フォーラム委員など役職多数。ほぼ40年間にわたって欧州通貨統合問題を直接担当する。ドイツ連邦共和国大功労十字章、わが国の旭日大綬章を授与される。
[監訳者紹介]
財団法人 国際通貨研究所
1995年に東京銀行(現三菱東京UFJ銀行)によって設立された公益法人。国際金融・国際通貨について、シンポジウムの開催、出版物の刊行や調査研究の実施を通じて、国内外での質の高い情報提供と政策提言のための活動を行っている。理事長は大蔵省財務官、東京銀行会長などを歴任した三菱東京UFJ銀行特別顧問の行天豊雄。
ホームページURL:http://www.iima.or.jp
村瀬 哲司(むらせ・てつじ)
1945年生まれ。1968年、一橋大学商学部卒業。東京銀行、東京三菱銀行調査部長を経て、現在京都大学国際交流センター教授。2001年、京都大学学位取得(経済学博士)。
著 書:『アジア安定通貨圏—ユーロに学ぶ円の役割—』勁草書房、2000年
『東アジアの通貨・金融協力—欧州の経験を未来に活かす—』勁草書房、2007年
A Zone of Asian Monetary Stability, Asia Pacific Press, 2002. 他共著多数
翻 訳:『マルクの幻想—ドイツ連銀の栄光と苦悩』D.バルクハウゼン著、日本経済新聞社、1993年
[訳者紹介]
山木 一之(やまき・かずゆき)
1949年生まれ。1974年、岡山大学中退、外務省入省。ドイツキール大学で研修後、在東ドイツ日本国大使館、在フランクフルト日本国総領事館などに勤務。2005年病気のため退職。現在ドイツ関係のアクチュアルなテーマの翻訳に従事。
論 文:「独仏関係は大西洋関係にいかに影響するか」(『外交フォーラム』1993年8月号)
監訳者はしがき
日本の読者の皆様へ
序
第1章 欧州復興期における各国の通貨・経済政策
第1節 政治的なプロセスとその転換点
第2節 独仏で異なる経験と優先順位
第3節 欧州共同体において重要性を増す通貨政策
第2章 ブレトンウッズ体制の崩壊と欧州通貨
第1節 一九六九年のデンハーグ欧州理事会とヴェルナー・グループ
第2節 一部合意にしか至らなかった閣僚理事会
第3節 多くの失敗を抱えた「トンネルの中の蛇」
第3章 通貨政策における独仏の相克と協調
第1節 新しい独仏イニシアティブ—一九七八—七九年の欧州通貨制度
第2節 新しいフランスの安定政策の展開
第3節 単一欧州議定書による新しい発展
第4節 一層の対称性を求める新たな要求
第4章 通貨統合実現への青写真
第1節 ハノーバー欧州理事会を前にした新しいシグナル
第2節 ドロール・グループとドロール報告書(一九八九年)
第3節 東欧諸国の解放(一九八九—一九九〇年)と欧州の転換点
第4節 経済通貨同盟に関する条約の基本原則
第5節 最後のコーナーを回った困難なマーストリヒトへの道
第5章 経済通貨同盟の産みの苦しみ
第1節 一九九二年に起こった通貨の激震
第2節 一九九三年の激しい余震とゆっくりした回復
第3節 一九九四年に始まった第二段階への移行
第4節 安定・成長協定とユーロ・グループ
第5節 一九九八年の収斂レポート
第6節 人事問題で揺れた欧州通貨同盟の出発
第7節 ECBにおける最初の方針決定
第6章 単一通貨の発足と残された課題
第1節 中間評価は合格点
第2節 低い経済成長と雇用問題
第3節 財政規律に関する問題
終章 一層の政治的な統合が必要か
訳者あとがき
本書に関連する主な出来事
人名索引
事項索引
日本の読者の皆様へ
序
第1章 欧州復興期における各国の通貨・経済政策
第1節 政治的なプロセスとその転換点
第2節 独仏で異なる経験と優先順位
第3節 欧州共同体において重要性を増す通貨政策
第2章 ブレトンウッズ体制の崩壊と欧州通貨
第1節 一九六九年のデンハーグ欧州理事会とヴェルナー・グループ
第2節 一部合意にしか至らなかった閣僚理事会
第3節 多くの失敗を抱えた「トンネルの中の蛇」
第3章 通貨政策における独仏の相克と協調
第1節 新しい独仏イニシアティブ—一九七八—七九年の欧州通貨制度
第2節 新しいフランスの安定政策の展開
第3節 単一欧州議定書による新しい発展
第4節 一層の対称性を求める新たな要求
第4章 通貨統合実現への青写真
第1節 ハノーバー欧州理事会を前にした新しいシグナル
第2節 ドロール・グループとドロール報告書(一九八九年)
第3節 東欧諸国の解放(一九八九—一九九〇年)と欧州の転換点
第4節 経済通貨同盟に関する条約の基本原則
第5節 最後のコーナーを回った困難なマーストリヒトへの道
第5章 経済通貨同盟の産みの苦しみ
第1節 一九九二年に起こった通貨の激震
第2節 一九九三年の激しい余震とゆっくりした回復
第3節 一九九四年に始まった第二段階への移行
第4節 安定・成長協定とユーロ・グループ
第5節 一九九八年の収斂レポート
第6節 人事問題で揺れた欧州通貨同盟の出発
第7節 ECBにおける最初の方針決定
第6章 単一通貨の発足と残された課題
第1節 中間評価は合格点
第2節 低い経済成長と雇用問題
第3節 財政規律に関する問題
終章 一層の政治的な統合が必要か
訳者あとがき
本書に関連する主な出来事
人名索引
事項索引