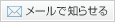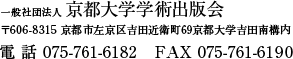ホーム > 書籍詳細ページ
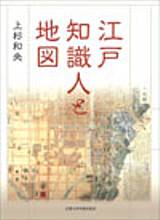
江戸知識人と地図
A5上製・320頁
ISBN: 9784876987955
発行年月: 2010/02
- 本体: 4,200円(税込 4,620円)
-
在庫なし
大国学者・本居宣長と,「ナゾのカルトグラファー」と呼ばれる正体未詳の人物・森幸安.18世紀日本のこの二人の知識人は,地図への驚くべきコミットメントをなしていた.彼らの営為を丹念に跡づけることを通じて,当時の教養における地理的知識の重要性,彼らの知的ネットワークが鮮やかに浮かび上がる,知的興奮に満ちた書.
『測量』'11年12月号、29頁、評者:山岡光治氏
『日本歴史』’14年8月号、107-110頁、評者:杉本史子氏
『日本歴史』’14年8月号、107-110頁、評者:杉本史子氏
上杉 和央(うえすぎ かずひろ)
1975年香川県生まれ.京都大学博士(文学).
現在,京都府立大学文学部講師.
研究テーマは,地理的知識の歴史地理学.
主要業績
「近世における浪速古図の作製と受容」史林85-2, 2002年.
「一七世紀の名所案内記に見える大坂の名所観」地理学評論77-9, 2004年.
『地図出版の四百年-京都・日本・世界』ナカニシヤ出版, 2007年(分担執筆).
「宇治の景観認識の変遷について-平等院・茶を中心に」, 菱田哲郎編『南山城・宇治地域を中心とする歴史遺産・文化的景観の研究』2009年.
1975年香川県生まれ.京都大学博士(文学).
現在,京都府立大学文学部講師.
研究テーマは,地理的知識の歴史地理学.
主要業績
「近世における浪速古図の作製と受容」史林85-2, 2002年.
「一七世紀の名所案内記に見える大坂の名所観」地理学評論77-9, 2004年.
『地図出版の四百年-京都・日本・世界』ナカニシヤ出版, 2007年(分担執筆).
「宇治の景観認識の変遷について-平等院・茶を中心に」, 菱田哲郎編『南山城・宇治地域を中心とする歴史遺産・文化的景観の研究』2009年.
口 絵
序 章 知識人たちの森へいざなう地図
凡 例
第一部 本居宣長の地理的知識
第一章 青年期宣長と地図
一 青年期宣長の位置づけ
1 情報の受容、知識の形成
2 研究対象としての宣長
二 稀代の空想都市図-「端原氏城下絵図」
1 系図と地図
2 京都図の影響-都市の構図
3 京都への傾倒
4「端原絵図」記載都市の形態
5 松坂の経験・松坂の発見/6江戸の一年
三 「大日本天下四海画図」の作製
1 日本の「かたち」-流宣日本図と「大日本天下四海画図」
2 地名・人名の情報-道中図と「大日本天下四海画図」
3 『大増補日本道中行程記』以外からの地名挿入
4 『大増補日本道中行程記』に見える情報の取捨
四 青年期宣長の地理的知識
第二章 宣長の教育と地図
一 地図の教育的利用
二 宣長の修学-その全体像
1 初等教育としての手習い
2 謡曲の舞台
3 青年期宣長の知的関心の推移
三 宣長の教育観
四 春庭の修学
1 春庭の手習い
2 春庭の修学
3 「大日本天下四海画図」から「日本分域指掌図」へ
五 春庭の目覚め-自律的な書写活動
1 署名の時期差
2 春庭の地図作製
六 宣長と春庭-修学過程の違い
1 親・師の関与
2 知の受容、知の表現
七 地図好きな宣長と春庭のそれから
第三章 宣長と世界図-地図貸借と利用の観点から
一 宣長と地図
二 宣長の地図貸借のネットワーク
三 宣長の手にした世界図-秋成との論争より
1 秋成の世界図利用
2 宣長の世界図利用
四 世界図への接近
1 世界図の画期
2 知のネットワークと世界図
五 宣長の知的関心と世界図
第二部 江戸期最大の地図作製者、森幸安
第四章 「ナゾのカルトグラファー」の実像
一 森幸安をめぐって
1 「ナゾのカルトグラファー」
2 「ナゾ」解明の第一歩
3 新たな森幸安像にむけて
4 幸安の著した地誌
二 京都居住時代の実像
1 幸安の職業
2 幸安の御所体験
3 各地の巡視
4 図的関心の萌芽
5 山州から摂州へ
三 「山州撰」に見る幸安
1 「山州撰」執筆の契機
2 「山州撰」の構成と既存書物との関係
3 「再撰」の具体相
四 もう一つの京都地誌「皇州緒餘撰」
1 「皇州緒餘撰」の構成
2 「後撰」の意味
五 幸安実像の一端
第五章 森幸安の地誌と地図
一 幸安との再会
二 京都関係の地図・地誌
1 幸安作製の京都・山城国関係地図
2 地誌と地図
三 幸安の京都歴史地図の情報源
1 「皇城大内裏地図」の建物配置と文字注記
2 『山城名勝志』と京都歴史地図
四 京都歴史地図作製における幸安の姿勢
1 本能寺域南辺の確定
2 幸安による本能寺周辺の復原作業
3 幸安の京都に関する地誌と地図の関係
4 幸安の「時の断面」-歴史アトラス構想
五 地誌作成から地図作製へ
第三部 地図と一八世紀の社会
第六章 地図貸借から見える知識人社会
一 知識人の地図収集
二 吉賢と地図
1 渡辺吉賢について
2 地図資料について
三 吉賢の地図の収集206
1 久保重宜、並河誠所
2 宇野宗明(奈良屋九郎兵衛)
3 橘守国
4 武士との交流
5 吉賢の旅行と他の地図収集家
四 吉賢所蔵図の利用
1 幸安との関係
2 吉賢の知名度
五 地図収集ネットワークの広がり
1 空間的広がり
2 身分・職業的広がり
3 時間・世代的広がり
六 「図を好む」者たちのネットワーク
第七章 博物学と地図収集ネットワーク
一 文化としての地図収集
二 地図収集家の別の顔
1 渡辺吉賢の薬物会出品
2 「いとこのめる人」
三 知識人の博物学的関心と地図
1 博物文化の牽引者たちの収集品
2 地図を好んだ弄銭家
3 博物学的探究と地図
四 宝暦の博物ネットワーク
1 博物収集ネットワークの構造
2 中心に位置する人物の個性
3 紀行文「東海濟勝記」に見える博物収集ネットワーク
五 博物収集の文化と地図
第八章 三才須知-地図収集の政治・思想的背景
一 「地」「図」の重要性
1 産地理解にむけた地理的知識の希求
2 「正しさ」を求めた視覚文化
3 収集文化の時代
二 享保期の廻村政策と地域社会
三 収集文化の思想的背景
1 ベストセラー作家、貝原益軒
2 天地人
3 天地人の受容
四 収集文化を生み出した環境
注
あとがき
図表一覧
索 引
序 章 知識人たちの森へいざなう地図
凡 例
第一部 本居宣長の地理的知識
第一章 青年期宣長と地図
一 青年期宣長の位置づけ
1 情報の受容、知識の形成
2 研究対象としての宣長
二 稀代の空想都市図-「端原氏城下絵図」
1 系図と地図
2 京都図の影響-都市の構図
3 京都への傾倒
4「端原絵図」記載都市の形態
5 松坂の経験・松坂の発見/6江戸の一年
三 「大日本天下四海画図」の作製
1 日本の「かたち」-流宣日本図と「大日本天下四海画図」
2 地名・人名の情報-道中図と「大日本天下四海画図」
3 『大増補日本道中行程記』以外からの地名挿入
4 『大増補日本道中行程記』に見える情報の取捨
四 青年期宣長の地理的知識
第二章 宣長の教育と地図
一 地図の教育的利用
二 宣長の修学-その全体像
1 初等教育としての手習い
2 謡曲の舞台
3 青年期宣長の知的関心の推移
三 宣長の教育観
四 春庭の修学
1 春庭の手習い
2 春庭の修学
3 「大日本天下四海画図」から「日本分域指掌図」へ
五 春庭の目覚め-自律的な書写活動
1 署名の時期差
2 春庭の地図作製
六 宣長と春庭-修学過程の違い
1 親・師の関与
2 知の受容、知の表現
七 地図好きな宣長と春庭のそれから
第三章 宣長と世界図-地図貸借と利用の観点から
一 宣長と地図
二 宣長の地図貸借のネットワーク
三 宣長の手にした世界図-秋成との論争より
1 秋成の世界図利用
2 宣長の世界図利用
四 世界図への接近
1 世界図の画期
2 知のネットワークと世界図
五 宣長の知的関心と世界図
第二部 江戸期最大の地図作製者、森幸安
第四章 「ナゾのカルトグラファー」の実像
一 森幸安をめぐって
1 「ナゾのカルトグラファー」
2 「ナゾ」解明の第一歩
3 新たな森幸安像にむけて
4 幸安の著した地誌
二 京都居住時代の実像
1 幸安の職業
2 幸安の御所体験
3 各地の巡視
4 図的関心の萌芽
5 山州から摂州へ
三 「山州撰」に見る幸安
1 「山州撰」執筆の契機
2 「山州撰」の構成と既存書物との関係
3 「再撰」の具体相
四 もう一つの京都地誌「皇州緒餘撰」
1 「皇州緒餘撰」の構成
2 「後撰」の意味
五 幸安実像の一端
第五章 森幸安の地誌と地図
一 幸安との再会
二 京都関係の地図・地誌
1 幸安作製の京都・山城国関係地図
2 地誌と地図
三 幸安の京都歴史地図の情報源
1 「皇城大内裏地図」の建物配置と文字注記
2 『山城名勝志』と京都歴史地図
四 京都歴史地図作製における幸安の姿勢
1 本能寺域南辺の確定
2 幸安による本能寺周辺の復原作業
3 幸安の京都に関する地誌と地図の関係
4 幸安の「時の断面」-歴史アトラス構想
五 地誌作成から地図作製へ
第三部 地図と一八世紀の社会
第六章 地図貸借から見える知識人社会
一 知識人の地図収集
二 吉賢と地図
1 渡辺吉賢について
2 地図資料について
三 吉賢の地図の収集206
1 久保重宜、並河誠所
2 宇野宗明(奈良屋九郎兵衛)
3 橘守国
4 武士との交流
5 吉賢の旅行と他の地図収集家
四 吉賢所蔵図の利用
1 幸安との関係
2 吉賢の知名度
五 地図収集ネットワークの広がり
1 空間的広がり
2 身分・職業的広がり
3 時間・世代的広がり
六 「図を好む」者たちのネットワーク
第七章 博物学と地図収集ネットワーク
一 文化としての地図収集
二 地図収集家の別の顔
1 渡辺吉賢の薬物会出品
2 「いとこのめる人」
三 知識人の博物学的関心と地図
1 博物文化の牽引者たちの収集品
2 地図を好んだ弄銭家
3 博物学的探究と地図
四 宝暦の博物ネットワーク
1 博物収集ネットワークの構造
2 中心に位置する人物の個性
3 紀行文「東海濟勝記」に見える博物収集ネットワーク
五 博物収集の文化と地図
第八章 三才須知-地図収集の政治・思想的背景
一 「地」「図」の重要性
1 産地理解にむけた地理的知識の希求
2 「正しさ」を求めた視覚文化
3 収集文化の時代
二 享保期の廻村政策と地域社会
三 収集文化の思想的背景
1 ベストセラー作家、貝原益軒
2 天地人
3 天地人の受容
四 収集文化を生み出した環境
注
あとがき
図表一覧
索 引