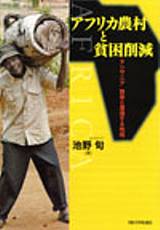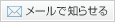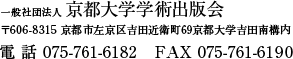ホーム > 書籍詳細ページ
国家や大陸レベルで見る経済学者はアフリカは貧しいという。しかし、実際の農村に焦点を当てると、そこには社会や生態環境の変化に巧みに対応する農民社会がある。このギャップを埋めること無しに、世界はアフリカと正しく向き合うことはできない。緻密なフィールドワークと開発経済学を組み合わせ、地域研究の新しい地平を開く意欲作。
『アジア・アフリカ地域研究』2010年第10-1号、74-78頁、評者:上田 元氏
『アジア経済』Vol.52 No.1 (2011.1)、77-80頁、評者:高根 務氏
『アジア経済』Vol.52 No.1 (2011.1)、77-80頁、評者:高根 務氏
池野 旬(いけの じゅん)
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 教授
1955年 大阪府生まれ
1978年 東京大学経済学部経済学科卒業
2008年 京都大学博士(地域研究)
アジア経済研究所研究職員(1978年より),京都大学大学院人間・環境学研究科助教授(1997年より),京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科助教授(1998年より),同准教授(2007年より)を経て,2008年より現職
主要著書・論文
『ウカンバニ―東部ケニアの小農経営―』 アジア経済研究所,1989年.
『アフリカの食糧問題―ガーナ・ナイジェリア・タンザニアの事例―』(共著) アジア経済研究所,1996年.
『アフリカのインフォーマル・セクター再考』(共編著) アジア経済研究所,1998年.
『アフリカ農村像の再検討』(編著) アジア経済研究所,1999年.
「独立後タンザニア経済と構造調整政策」秋元英一編『グローバリゼーションと国民経済の選択』東京大学出版会,2001年.
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 教授
1955年 大阪府生まれ
1978年 東京大学経済学部経済学科卒業
2008年 京都大学博士(地域研究)
アジア経済研究所研究職員(1978年より),京都大学大学院人間・環境学研究科助教授(1997年より),京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科助教授(1998年より),同准教授(2007年より)を経て,2008年より現職
主要著書・論文
『ウカンバニ―東部ケニアの小農経営―』 アジア経済研究所,1989年.
『アフリカの食糧問題―ガーナ・ナイジェリア・タンザニアの事例―』(共著) アジア経済研究所,1996年.
『アフリカのインフォーマル・セクター再考』(共編著) アジア経済研究所,1998年.
『アフリカ農村像の再検討』(編著) アジア経済研究所,1999年.
「独立後タンザニア経済と構造調整政策」秋元英一編『グローバリゼーションと国民経済の選択』東京大学出版会,2001年.
口 絵
まえがき
序 章 アフリカ農村研究の残された課題
ミクロ―マクロ・ギャップの架橋
1 開発をめぐる国家と地域
1―1.生存戦略を模索する「地域」
1―2.アフリカ農村・農業研究のミクロ―マクロ・ギャップ
1―3.重層する「地域」―2つの研究対象―
1―4.タンザニア農村分析の前提
2 事例とする北東部タンザニアの2つの地域
2―1.キリマンジャロ州ムワンガ県
2―2.キルル・ルワミ村ヴドイ村区キリスィ集落
3 本書の構成
4 ミクロ―マクロ・ギャップを埋める手法
第2章 タンザニアの国家開発政策の変遷
アフリカ社会主義の夢から世銀・IMF主導の開発体制へ
1 アフリカ社会主義体制の挫折
1―1.民間主導の近代化路線―第1期―
1―2.ウジャマー社会主義下の国家開発―第2期―
1―3.ウジャマー社会主義の行き詰まり
2 グローバル化のもとでの国家開発体制の転換
2―1.世銀・IMF主導の構造調整政策―第3期―
2―2.構造調整政策は成功したか?
2―3.開発思想のパラダイム・シフト
2―4.タンザニアの貧困削減政策―第4期―
3 国家開発体制の政治経済学
第3章 ムワンガ県の農業・食糧問題
併存する換金作物の不振と食糧不足
1 ムワンガ県のコーヒー経済の低迷
1―1.タンザニア全体と北部高地のコーヒー経済
1―2.ムワンガ県のコーヒー経済
1―3.山地村2村の事例
2 ムワンガ県の食糧問題
2―1.タンザニアの食糧事情
2―2.ムワンガ県の食糧不足の創造
2―3.食糧配給と農村世帯の自衛策
第4章 キリスィ集落での乾季灌漑作
生活自衛のための新たな営農活動
1 在来灌漑施設―溜池と用水路
1―1.山間部に設置された小さな溜池
1―2.巧みに張り巡らされた用水路
1―3.在来灌漑施設の建造者と管理者
2 灌漑作圃場と圃場耕作者
2―1.灌漑作圃場の耕地保有者
2―2.灌漑作を実践する圃場耕作者
3 開放的な組織化と柔軟な用水利用
3―1.乾季灌漑作全般に関わる組織
3―2.山地村の用水利用者集団との取り決め
3―3.同一日に用水を利用する番水グループ
3―4.柔軟な用水利用
4 在来灌漑施設改良計画(TIP)の試み
第5章 ムワンガ町の拡大と懸案
地域経済の牽引を期待される地方都市
1 ムワンガ県経済の中心地移動
1―1.ムワンガ県の人口動態からの検証
1―2.ムワンガ町の拡大とキリスィ集落への波及
2 地域経済の方向性―農村インフォーマル・セクターに着目
して―
2―1.農村インフォーマル・セクターの概念規定
2―2.農村におけるインフォーマル・セクターの存在形態
2―3.農村インフォーマル・セクター振興の必要性と検討課題
3 対抗的な社会資本整備―ヴドイ村区の水道新設事業―
3―1.ムワンガ町周辺の水道施設
3―2.クワ・トゥガ水道計画
終 章 地域と開発の交接点を求めて
1 地域の主体性―事例からの示唆―
2 ミクロ―マクロ・ギャップを架橋するために
2―1.地域研究と開発諸学の協業は可能か?
2―2.地域理解の共通認識
2―3.ミクロ―マクロをつなぐ試み
2―4.国際的な開発理念の見直し
2―5.地域独自の論理
3 ミクロ―マクロ・ギャップの架橋―まとめと課題―
あとがき
文献リスト
まえがき
序 章 アフリカ農村研究の残された課題
ミクロ―マクロ・ギャップの架橋
1 開発をめぐる国家と地域
1―1.生存戦略を模索する「地域」
1―2.アフリカ農村・農業研究のミクロ―マクロ・ギャップ
1―3.重層する「地域」―2つの研究対象―
1―4.タンザニア農村分析の前提
2 事例とする北東部タンザニアの2つの地域
2―1.キリマンジャロ州ムワンガ県
2―2.キルル・ルワミ村ヴドイ村区キリスィ集落
3 本書の構成
4 ミクロ―マクロ・ギャップを埋める手法
第2章 タンザニアの国家開発政策の変遷
アフリカ社会主義の夢から世銀・IMF主導の開発体制へ
1 アフリカ社会主義体制の挫折
1―1.民間主導の近代化路線―第1期―
1―2.ウジャマー社会主義下の国家開発―第2期―
1―3.ウジャマー社会主義の行き詰まり
2 グローバル化のもとでの国家開発体制の転換
2―1.世銀・IMF主導の構造調整政策―第3期―
2―2.構造調整政策は成功したか?
2―3.開発思想のパラダイム・シフト
2―4.タンザニアの貧困削減政策―第4期―
3 国家開発体制の政治経済学
第3章 ムワンガ県の農業・食糧問題
併存する換金作物の不振と食糧不足
1 ムワンガ県のコーヒー経済の低迷
1―1.タンザニア全体と北部高地のコーヒー経済
1―2.ムワンガ県のコーヒー経済
1―3.山地村2村の事例
2 ムワンガ県の食糧問題
2―1.タンザニアの食糧事情
2―2.ムワンガ県の食糧不足の創造
2―3.食糧配給と農村世帯の自衛策
第4章 キリスィ集落での乾季灌漑作
生活自衛のための新たな営農活動
1 在来灌漑施設―溜池と用水路
1―1.山間部に設置された小さな溜池
1―2.巧みに張り巡らされた用水路
1―3.在来灌漑施設の建造者と管理者
2 灌漑作圃場と圃場耕作者
2―1.灌漑作圃場の耕地保有者
2―2.灌漑作を実践する圃場耕作者
3 開放的な組織化と柔軟な用水利用
3―1.乾季灌漑作全般に関わる組織
3―2.山地村の用水利用者集団との取り決め
3―3.同一日に用水を利用する番水グループ
3―4.柔軟な用水利用
4 在来灌漑施設改良計画(TIP)の試み
第5章 ムワンガ町の拡大と懸案
地域経済の牽引を期待される地方都市
1 ムワンガ県経済の中心地移動
1―1.ムワンガ県の人口動態からの検証
1―2.ムワンガ町の拡大とキリスィ集落への波及
2 地域経済の方向性―農村インフォーマル・セクターに着目
して―
2―1.農村インフォーマル・セクターの概念規定
2―2.農村におけるインフォーマル・セクターの存在形態
2―3.農村インフォーマル・セクター振興の必要性と検討課題
3 対抗的な社会資本整備―ヴドイ村区の水道新設事業―
3―1.ムワンガ町周辺の水道施設
3―2.クワ・トゥガ水道計画
終 章 地域と開発の交接点を求めて
1 地域の主体性―事例からの示唆―
2 ミクロ―マクロ・ギャップを架橋するために
2―1.地域研究と開発諸学の協業は可能か?
2―2.地域理解の共通認識
2―3.ミクロ―マクロをつなぐ試み
2―4.国際的な開発理念の見直し
2―5.地域独自の論理
3 ミクロ―マクロ・ギャップの架橋―まとめと課題―
あとがき
文献リスト