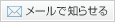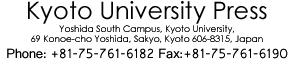Home > Book Detail Page
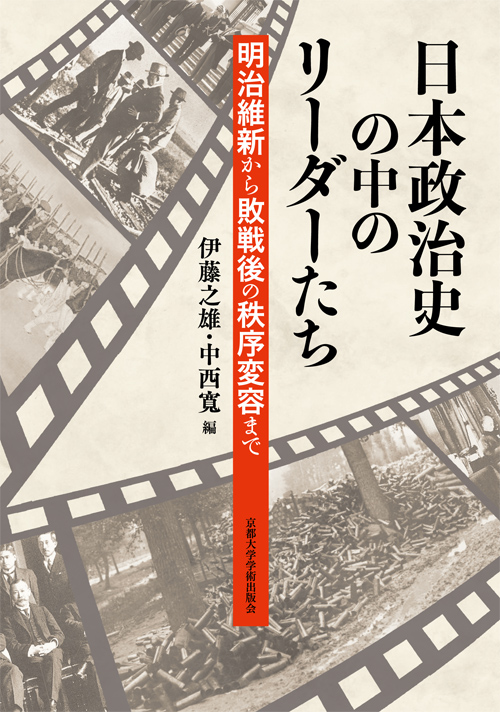
冷戦後の一見安定した秩序の中で「資源の配分」としての性格を強めた政治は,テロや武力行使が頻発し激しい対立が顕在化した今日には,通用し得ない。そこで秩序変容の時代のリーダー像が求められる。しかし近代日本においてリーダーはリーダーたりえたのか。彼らの生い立ちから性格まで,そして彼らを取り巻く国際的な事象の拡がりに注目して,指導者達の成功と失敗の要因を炙り出す。
『日本経済新聞』2018年5月5日付朝刊 読書面
『読売新聞』2018年7月1日付朝刊、評者:三浦瑠麗氏
『読売新聞』2018年7月1日付朝刊、評者:三浦瑠麗氏
■編者
伊藤 之雄(いとう ゆきお)
京都大学大学院法学研究科教授
1952年生まれ,京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学,博士(文学)。
主な著書に,『昭和天皇と立憲君主制の崩壊――睦仁・嘉仁から裕仁へ』(名古屋大学出版会,2005年),『「大京都」の誕生――都市改造と公共性の時代 1895~1931年』(ミネルヴァ書房,2018年),『元老――近代日本の真の指導者たち』(中公新書,2016年)など。
中西 寬(なかにし ひろし)
京都大学公共政策大学院教授
1962年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士課程退学,法学修士。
主な著書に,『国際政治とは何か――地球社会における人間と秩序』(単著,中公新書,2003),『歴史の桎梏を越えて』(共編著,千倉書房,2011),『国際政治学』(共著,有斐閣,2013),『高坂正堯と戦後日本』(共編著,中央公論新社,2016)など。
■著者(50音順)
井上 正也(いのうえ まさや)
成蹊大学法学部教授
1979年生まれ,神戸大学大学院法学研究科博士後期課程修了,博士(政治学)。
主な著書に,『日中国交正常化の政治史』(名古屋大学出版会,2010年)など。
小林 道彦(こばやし みちひこ)
北九州市立大学基盤教育センター教授
1956年生まれ,中央大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学,博士(法学)。
主な著書に,『桂太郎――予が生命は政治である』(ミネルヴァ書房,2006年),『歴史の桎梏を越えて――20世紀日中関係への新視点』(共編著,千倉書房,2010年),『政党内閣の崩壊と満州事変』(ミネルヴァ書房,2010年),『児玉源太郎――そこから旅順港は見えるか』(ミネルヴァ書房,2012年),『日本政治史のなかの陸海軍』(共編著,ミネルヴァ書房,2013年),『大正政変――国家経営構想の分裂』(千倉書房,2015年)など。
小山 俊樹(こやま としき)
帝京大学文学部教授
1976年生まれ,京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了,人間・環境学博士。
主な著書に,『憲政常道と政党政治――近代日本二大政党制の構想と挫折』(思文閣出版,2012年),『近代機密費史料集成Ⅰ――外交機密費編』(全7巻,編著,ゆまに書房,2014-2015年),『評伝森恪――日中対立の焦点』(ウエッジ,2017年)など。
齊藤 紅葉(さいとう もみじ)
京都大学大学院法学研究科研修員
1982年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学,法学博士。
主な業績に,「幕末期木戸孝允の国家構想と政治指導――長州藩の統制から倒幕へ(一八三三―一八六五)」(1)~(3)(『法学論叢』第179巻第4号・6号・第180巻第3号,2016年7月・9月・12月),「木戸孝允と中央集権国家の成立――西洋列強と対峙し得る新国家の樹立(一八六五―一八七一)」(1)~(3)(『法学論叢』第181巻第1-3号,2017年4-6月)など。
スピルマン,クリストファー・W・A
帝京大学文学部日本文化学科教授
1951年生まれ,1993年エール大学大学院歴史学研究科博士課程修了,博士(PhD,日本史)。
主な著書に,『満川亀太郎書簡集――北一輝・大川周明・西田税らの書簡』(共編著,論創社,2012)『近代日本の革新論とアジア主義――北一輝,大川周明,満川亀太郎らの思想と行動』(芦書房,2015年),Routledge Handbook of Modern Japanese History(coed., Routledge, 2018)など。
瀧井 一博(たきい かずひろ)
国際日本文化研究センター教授
1967年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学,博士(法学)。
主な著書に,『文明史のなかの明治憲法』(講談社,2003年),『伊藤博文』(中公新書,2010年),『渡邉洪基』(ミネルヴァ書房,2016年)など。
等松 春夫(とうまつ はるお)
防衛大学校人文社会科学群国際関係学科教授
1962年生まれ,オックスフォード大学社会科学大学院修了,D. Phil。
主な著書に,『日本帝国と委任統治――南洋群島をめぐる国際政治1914-1947』(名古屋大学出版会,2011),『昭和史講義』(共著,筑摩書房,2015),『日中戦争の軍事的展開』(共著,慶應義塾大学出版会,2006)など。
中谷 直司(なかたに ただし)
三重大学教養教育機構特任准教授(教育担当)
1978年生まれ,同志社大学大学院法学研究科博士後期課程修了,博士(政治学)。
主な業績に,『強いアメリカと弱いアメリカの狭間で――第一次世界大戦後の東アジア秩序をめぐる日米英関係』(千倉書房,2016年),「同盟はなぜ失われたのか――日英同盟の終焉過程の再検討1919-1921」(『国際政治』第180号,2015年3月)など。
西田 敏宏(にしだ としひろ)
椙山女学園大学現代マネジメント学部准教授
1975年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士後期課程修了,博士(法学)。
主な著書に,『20世紀日米関係と東アジア』(共著,風媒社,2002年),『20世紀日本と東アジアの形成――1867~2006』(共著,ミネルヴァ書房,2007年),『内田康哉関係資料集成』全3巻(共編,柏書房,2012年),『昭和史講義3――リーダーを通して見る戦争への道』(共著,筑摩書房,2017年)など。
西山 由理花(にしやま ゆりか)
京都大学大学院法学研究科特定助教
1987年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士後期課程修了,博士(法学)。
主な著作に,『松田正久と政党政治の発展――原敬・星亨との連携と競合』(ミネルヴァ書房,2017年),『原敬と政党政治の確立』(分担執筆,千倉書房,2014年)など。
萩原 淳(はぎはら あつし)
三重大学人文学部非常勤講師
1987年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士後期課程修了,博士(法学)。
主な著作に,『平沼騏一郎と近代日本――官僚の国家主義と太平洋戦争への道』(京都大学学術出版会,2016年),「昭和初期の枢密院運用と政党内閣――憲法解釈をめぐる先例と顧問官統制を中心に」(『年報政治学』2017年第Ⅱ号)など。
森 靖夫(もり やすお)
同志社大学法学部准教授
1978年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士課程修了,法学博士。
主な著書に,『日本陸軍と日中戦争への道――軍事統制システムをめぐる攻防』(ミネルヴァ書房,2010年),『永田鉄山』(ミネルヴァ書房,2011年)など。
伊藤 之雄(いとう ゆきお)
京都大学大学院法学研究科教授
1952年生まれ,京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学,博士(文学)。
主な著書に,『昭和天皇と立憲君主制の崩壊――睦仁・嘉仁から裕仁へ』(名古屋大学出版会,2005年),『「大京都」の誕生――都市改造と公共性の時代 1895~1931年』(ミネルヴァ書房,2018年),『元老――近代日本の真の指導者たち』(中公新書,2016年)など。
中西 寬(なかにし ひろし)
京都大学公共政策大学院教授
1962年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士課程退学,法学修士。
主な著書に,『国際政治とは何か――地球社会における人間と秩序』(単著,中公新書,2003),『歴史の桎梏を越えて』(共編著,千倉書房,2011),『国際政治学』(共著,有斐閣,2013),『高坂正堯と戦後日本』(共編著,中央公論新社,2016)など。
■著者(50音順)
井上 正也(いのうえ まさや)
成蹊大学法学部教授
1979年生まれ,神戸大学大学院法学研究科博士後期課程修了,博士(政治学)。
主な著書に,『日中国交正常化の政治史』(名古屋大学出版会,2010年)など。
小林 道彦(こばやし みちひこ)
北九州市立大学基盤教育センター教授
1956年生まれ,中央大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学,博士(法学)。
主な著書に,『桂太郎――予が生命は政治である』(ミネルヴァ書房,2006年),『歴史の桎梏を越えて――20世紀日中関係への新視点』(共編著,千倉書房,2010年),『政党内閣の崩壊と満州事変』(ミネルヴァ書房,2010年),『児玉源太郎――そこから旅順港は見えるか』(ミネルヴァ書房,2012年),『日本政治史のなかの陸海軍』(共編著,ミネルヴァ書房,2013年),『大正政変――国家経営構想の分裂』(千倉書房,2015年)など。
小山 俊樹(こやま としき)
帝京大学文学部教授
1976年生まれ,京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了,人間・環境学博士。
主な著書に,『憲政常道と政党政治――近代日本二大政党制の構想と挫折』(思文閣出版,2012年),『近代機密費史料集成Ⅰ――外交機密費編』(全7巻,編著,ゆまに書房,2014-2015年),『評伝森恪――日中対立の焦点』(ウエッジ,2017年)など。
齊藤 紅葉(さいとう もみじ)
京都大学大学院法学研究科研修員
1982年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学,法学博士。
主な業績に,「幕末期木戸孝允の国家構想と政治指導――長州藩の統制から倒幕へ(一八三三―一八六五)」(1)~(3)(『法学論叢』第179巻第4号・6号・第180巻第3号,2016年7月・9月・12月),「木戸孝允と中央集権国家の成立――西洋列強と対峙し得る新国家の樹立(一八六五―一八七一)」(1)~(3)(『法学論叢』第181巻第1-3号,2017年4-6月)など。
スピルマン,クリストファー・W・A
帝京大学文学部日本文化学科教授
1951年生まれ,1993年エール大学大学院歴史学研究科博士課程修了,博士(PhD,日本史)。
主な著書に,『満川亀太郎書簡集――北一輝・大川周明・西田税らの書簡』(共編著,論創社,2012)『近代日本の革新論とアジア主義――北一輝,大川周明,満川亀太郎らの思想と行動』(芦書房,2015年),Routledge Handbook of Modern Japanese History(coed., Routledge, 2018)など。
瀧井 一博(たきい かずひろ)
国際日本文化研究センター教授
1967年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学,博士(法学)。
主な著書に,『文明史のなかの明治憲法』(講談社,2003年),『伊藤博文』(中公新書,2010年),『渡邉洪基』(ミネルヴァ書房,2016年)など。
等松 春夫(とうまつ はるお)
防衛大学校人文社会科学群国際関係学科教授
1962年生まれ,オックスフォード大学社会科学大学院修了,D. Phil。
主な著書に,『日本帝国と委任統治――南洋群島をめぐる国際政治1914-1947』(名古屋大学出版会,2011),『昭和史講義』(共著,筑摩書房,2015),『日中戦争の軍事的展開』(共著,慶應義塾大学出版会,2006)など。
中谷 直司(なかたに ただし)
三重大学教養教育機構特任准教授(教育担当)
1978年生まれ,同志社大学大学院法学研究科博士後期課程修了,博士(政治学)。
主な業績に,『強いアメリカと弱いアメリカの狭間で――第一次世界大戦後の東アジア秩序をめぐる日米英関係』(千倉書房,2016年),「同盟はなぜ失われたのか――日英同盟の終焉過程の再検討1919-1921」(『国際政治』第180号,2015年3月)など。
西田 敏宏(にしだ としひろ)
椙山女学園大学現代マネジメント学部准教授
1975年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士後期課程修了,博士(法学)。
主な著書に,『20世紀日米関係と東アジア』(共著,風媒社,2002年),『20世紀日本と東アジアの形成――1867~2006』(共著,ミネルヴァ書房,2007年),『内田康哉関係資料集成』全3巻(共編,柏書房,2012年),『昭和史講義3――リーダーを通して見る戦争への道』(共著,筑摩書房,2017年)など。
西山 由理花(にしやま ゆりか)
京都大学大学院法学研究科特定助教
1987年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士後期課程修了,博士(法学)。
主な著作に,『松田正久と政党政治の発展――原敬・星亨との連携と競合』(ミネルヴァ書房,2017年),『原敬と政党政治の確立』(分担執筆,千倉書房,2014年)など。
萩原 淳(はぎはら あつし)
三重大学人文学部非常勤講師
1987年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士後期課程修了,博士(法学)。
主な著作に,『平沼騏一郎と近代日本――官僚の国家主義と太平洋戦争への道』(京都大学学術出版会,2016年),「昭和初期の枢密院運用と政党内閣――憲法解釈をめぐる先例と顧問官統制を中心に」(『年報政治学』2017年第Ⅱ号)など。
森 靖夫(もり やすお)
同志社大学法学部准教授
1978年生まれ,京都大学大学院法学研究科博士課程修了,法学博士。
主な著書に,『日本陸軍と日中戦争への道――軍事統制システムをめぐる攻防』(ミネルヴァ書房,2010年),『永田鉄山』(ミネルヴァ書房,2011年)など。
はしがき
第Ⅰ部 近代国家日本の軌跡――「文明標準」とその解体の中で
総 論………中西 寛
第一章 危機の連鎖と近代軍の建設………小林道彦
――明治六年政変から西南戦争へ
一 士族反乱と外征論
二 徴兵制軍隊をめぐる権力状況
三 危機の切迫と大久保内務卿による兵権掌握――佐賀の乱
四 大久保のリーダーシップの動揺と恢復――台湾出兵の失敗
五 挙国一致への動き――山県陸軍卿の復権
六 西南戦争と琉球処分
七 徴兵制反対論の消滅――板垣退助と自由党土佐派
第二章 明治日本の危機と帝国大学の〈結社の哲学〉………瀧井一博
――初代総長渡邉洪基と帝国大学創設の思想的背景
一 忘れられた初代〝東京大学〟総長
二 その生涯
三 帝国大学への道
四 帝国大学創設の思想的背景
五 渡邉の見た「夢」――帝国大学体制の虚実
第三章 東アジア「新外交」の開始………中谷直司
――第一次世界大戦後の新四国借款団交渉と「旧制度」の解体
一 大戦後の国際政治と日本
二 新四国借款団をめぐる二つの論点
三 日本外交は旧秩序を守ろうとしたのか
四 首相・原敬の強硬論
五 イギリスの政策――「旧外交」のチャンピオンが目指したもの
六 決着――何が保証されたのか
七 一九二〇年後――新四国借款団交渉がもたらしたもの
第四章 北昤吉の戦間期………クリストファー・W・A・スピルマン
――日本的ファシズムへの道
一 大正デモクラシーへの批判
二 日本外交への批判と戦争論
三 アジア主義論
四 ファシズムへの傾倒
五 おわりに
第五章 戦間期における国家建設………等松春夫
――「満洲国」とイラク
一 はじめに
二 戦間期の国際秩序と国家建設
三 イギリスとイラクの建国(一九一九~三二年)
四 日本と満洲国の建国(一九〇五~三二年)
五 分析的な結論
第六章 総力戦・衆民政・アメリカ………森 靖夫
――松井春生の国家総動員体制構想
一 統帥権独立をいかに克服するか
二 松井春生の国家総動員体制構想
三 構想の修正――政党内閣制の崩壊と永田鉄山の死
四 松井春生と日中戦争――国家総動員法制定へ
五 松井春生の国家総動員体制構想とは何だったのか
第七章 高碕達之助と日印鉄鋼提携構想………井上正也
――アジア・シューマン・プランの夢
一 朝鮮戦争と東南アジア開発
二 高碕達之助と鉄鋼業
三 インド鉄鋼開発計画の浮上
四 高炉建設と鉄鉱資源開発
五 日印交渉
六 高碕構想の挫折
七 経済開発とナショナリズム
第Ⅱ部 リーダーシップを見る視点
総 論………伊藤之雄
一 近代日本のリーダー研究の意義――はじめに
二 五論文(五人)のリーダーシップの概要
三 公共性のある日本独自のビジョンと現実性
四 精神的強さ
五 人間関係と気配り
第一章 木戸孝允と薩長同盟………齊藤紅葉
――慶応元年から慶応三年
一 薩長同盟と木戸孝允の関係――はじめに
二 ペリー来航による国家認識と薩長提携の意識
三 木戸の長州藩主導と、薩長主導の武力討幕
四 明治政府での薩長主導体制と木戸の影響力の喪失
五 薩長同盟と木戸のリーダーシップ――おわりに
第二章 第一次護憲運動と松田正久………西山由理花
――「松田内閣」への期待
一 栄光と忍耐の表れ――はじめに
二 松田正久の政治構想と政治指導の形成
三 護憲運動の盛り上がり
四 原敬に後事を託す
五 第一次護憲運動における公共性の表れ――おわりに
第三章 幣原喜重郎と国際協調………西田敏宏
――北京関税会議・北伐をめぐる外交再考
一 幣原外交に対する「自主外交」批判――はじめに
二 外交指導者としての幣原の個性の形成
三 自主的協調外交としての第一次幣原外交
四 幣原外交はなぜイギリスとの間で摩擦を招くことになったか
五 イギリスとの協調の失敗とその帰結
六 幣原の外交指導の特質とその後――おわりに
第四章 田中義一と山東出兵………小山俊樹
――政治主導の対外派兵とリーダーシップ
一 「おらが宰相」の失敗――はじめに
二 生い立ちと軌跡
三 陸相時代の「転換」から政党総裁へ
四 第一次山東出兵――政治主導の出兵過程
五 第二次・第三次山東出兵――軍事衝突とリーダーシップの崩壊
六 天皇・宮中との対立、張作霖爆殺事件の真相公表をめぐって――おわりに
第五章 平沼騏一郎と政権獲得構想………萩原 淳
――平沼内閣の模索と挫折 一九二四~三四年
一 政権獲得構想に見る平沼のリーダーシップ――はじめに
二 司法官僚としての台頭と政治的性格の形成
三 政治基盤の形成と「田・平沼」内閣構想
四 政権獲得構想の一時的退潮と田中内閣との協調
五 平沼待望論の高まりと平沼内閣運動
六 平沼のリーダーシップの特質とその限界――おわりに
あとがき
索引
第Ⅰ部 近代国家日本の軌跡――「文明標準」とその解体の中で
総 論………中西 寛
第一章 危機の連鎖と近代軍の建設………小林道彦
――明治六年政変から西南戦争へ
一 士族反乱と外征論
二 徴兵制軍隊をめぐる権力状況
三 危機の切迫と大久保内務卿による兵権掌握――佐賀の乱
四 大久保のリーダーシップの動揺と恢復――台湾出兵の失敗
五 挙国一致への動き――山県陸軍卿の復権
六 西南戦争と琉球処分
七 徴兵制反対論の消滅――板垣退助と自由党土佐派
第二章 明治日本の危機と帝国大学の〈結社の哲学〉………瀧井一博
――初代総長渡邉洪基と帝国大学創設の思想的背景
一 忘れられた初代〝東京大学〟総長
二 その生涯
三 帝国大学への道
四 帝国大学創設の思想的背景
五 渡邉の見た「夢」――帝国大学体制の虚実
第三章 東アジア「新外交」の開始………中谷直司
――第一次世界大戦後の新四国借款団交渉と「旧制度」の解体
一 大戦後の国際政治と日本
二 新四国借款団をめぐる二つの論点
三 日本外交は旧秩序を守ろうとしたのか
四 首相・原敬の強硬論
五 イギリスの政策――「旧外交」のチャンピオンが目指したもの
六 決着――何が保証されたのか
七 一九二〇年後――新四国借款団交渉がもたらしたもの
第四章 北昤吉の戦間期………クリストファー・W・A・スピルマン
――日本的ファシズムへの道
一 大正デモクラシーへの批判
二 日本外交への批判と戦争論
三 アジア主義論
四 ファシズムへの傾倒
五 おわりに
第五章 戦間期における国家建設………等松春夫
――「満洲国」とイラク
一 はじめに
二 戦間期の国際秩序と国家建設
三 イギリスとイラクの建国(一九一九~三二年)
四 日本と満洲国の建国(一九〇五~三二年)
五 分析的な結論
第六章 総力戦・衆民政・アメリカ………森 靖夫
――松井春生の国家総動員体制構想
一 統帥権独立をいかに克服するか
二 松井春生の国家総動員体制構想
三 構想の修正――政党内閣制の崩壊と永田鉄山の死
四 松井春生と日中戦争――国家総動員法制定へ
五 松井春生の国家総動員体制構想とは何だったのか
第七章 高碕達之助と日印鉄鋼提携構想………井上正也
――アジア・シューマン・プランの夢
一 朝鮮戦争と東南アジア開発
二 高碕達之助と鉄鋼業
三 インド鉄鋼開発計画の浮上
四 高炉建設と鉄鉱資源開発
五 日印交渉
六 高碕構想の挫折
七 経済開発とナショナリズム
第Ⅱ部 リーダーシップを見る視点
総 論………伊藤之雄
一 近代日本のリーダー研究の意義――はじめに
二 五論文(五人)のリーダーシップの概要
三 公共性のある日本独自のビジョンと現実性
四 精神的強さ
五 人間関係と気配り
第一章 木戸孝允と薩長同盟………齊藤紅葉
――慶応元年から慶応三年
一 薩長同盟と木戸孝允の関係――はじめに
二 ペリー来航による国家認識と薩長提携の意識
三 木戸の長州藩主導と、薩長主導の武力討幕
四 明治政府での薩長主導体制と木戸の影響力の喪失
五 薩長同盟と木戸のリーダーシップ――おわりに
第二章 第一次護憲運動と松田正久………西山由理花
――「松田内閣」への期待
一 栄光と忍耐の表れ――はじめに
二 松田正久の政治構想と政治指導の形成
三 護憲運動の盛り上がり
四 原敬に後事を託す
五 第一次護憲運動における公共性の表れ――おわりに
第三章 幣原喜重郎と国際協調………西田敏宏
――北京関税会議・北伐をめぐる外交再考
一 幣原外交に対する「自主外交」批判――はじめに
二 外交指導者としての幣原の個性の形成
三 自主的協調外交としての第一次幣原外交
四 幣原外交はなぜイギリスとの間で摩擦を招くことになったか
五 イギリスとの協調の失敗とその帰結
六 幣原の外交指導の特質とその後――おわりに
第四章 田中義一と山東出兵………小山俊樹
――政治主導の対外派兵とリーダーシップ
一 「おらが宰相」の失敗――はじめに
二 生い立ちと軌跡
三 陸相時代の「転換」から政党総裁へ
四 第一次山東出兵――政治主導の出兵過程
五 第二次・第三次山東出兵――軍事衝突とリーダーシップの崩壊
六 天皇・宮中との対立、張作霖爆殺事件の真相公表をめぐって――おわりに
第五章 平沼騏一郎と政権獲得構想………萩原 淳
――平沼内閣の模索と挫折 一九二四~三四年
一 政権獲得構想に見る平沼のリーダーシップ――はじめに
二 司法官僚としての台頭と政治的性格の形成
三 政治基盤の形成と「田・平沼」内閣構想
四 政権獲得構想の一時的退潮と田中内閣との協調
五 平沼待望論の高まりと平沼内閣運動
六 平沼のリーダーシップの特質とその限界――おわりに
あとがき
索引