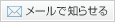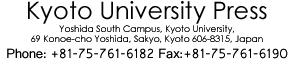Home > Book Detail Page
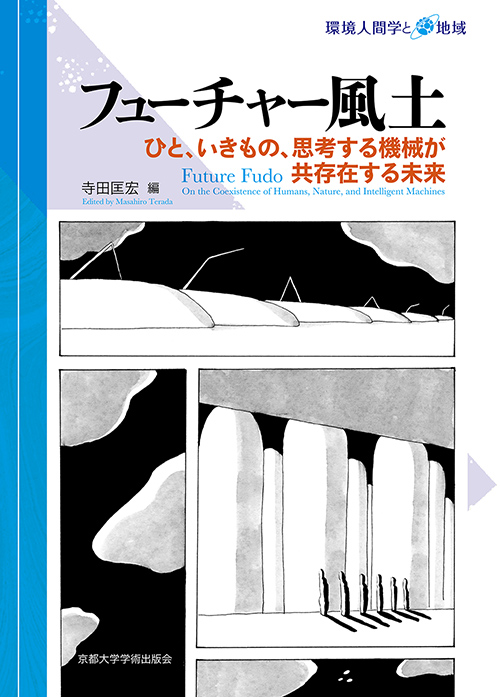
フューチャー風土
ひと、いきもの、思考する機械が共存在する未来
A5上製, 792 pages
ISBN: 9784814005833
pub. date: 03/25
地球の未来を見つめるための鍵は、「風土」である――。和辻哲郎やオギュスタン・ベルクが深化させた「風土」概念を拡張し、過去の枠を超えて、人間、生き物、AIを含む多元的主体が共存する地球の未来像を探る。人間中心の視点を離れ新たな地球環境のビジョンを構築するための、人文学、情報学、工学の専門家たちによる挑戦。
「神戸新聞」2025年7月5日付朝刊 読書面、評者:松岡健氏
寺田匡宏 Masahiro Terada
総合地球環境学研究所客員教授。人文地球環境学。ひと、いきもの、ものを包括した環境とはどのように論じられるべきなのか、科学に基づく二元論的世界観と生活世界の実感としての全体論的世界観はどう関係するかなどを研究。近年は、そのような視角から、未来可能性に資する学としての風土学の可能性を探求。著書に、『人新世の風土学——地球を〈読む〉ための本棚』(昭和堂、2023年)、『人文地球環境学——ひと、もの、いきものと世界/出来』(あいり出版、2021年)、『人新世を問う——環境、人文、アジアの視点』(ダニエル・ナイルズと共編、京都大学学術出版会、2021年)、『カタストロフと時間——記憶/語りと歴史の生成』(京都大学学術出版会、2018年)、『人は火山に何を見るのか——環境と記憶/歴史』(昭和堂、2015年)ほか。「叢書・地球のナラティブ」(あいり出版、2019年−)、「シリーズ よむかくくらすかんがえるの本棚」(あいり出版、2023年−)のシリーズ・エディターもつとめる。国立歴史民俗博物館COE研究員、国立民族学博物館外来研究員、総合地球環境学研究所特任准教授、マックスプランク科学史研究所客員研究員を歴任。
ジェイソン・リュス・パリー Jason Rhys Parry
ユバル・ノア・ハラリ財団「サピエンシップ」上級コンテンツ開発研究員。米国パドゥ大学客員教授、総合地球環境学研究所フェローシップ外国人研究員を歴任。技術と文化に関する論考を執筆。19世紀ブラジルの女性作家フリア・ロペス・アルメイダ『破綻』を英語に初訳(共訳)した(カリフォルニア大学出版局、2023年)。
ブレイズ・セールス Blaise Sales
英国リーズ大学大学院ホワイト・ローズ・カレッジ(芸術・人文学専攻)博士課程。ロンドン・キングズ・カレッジで英文学士、ヨーク大学で医療人文学修士を取得。博士論文では、認知の身体化とエコクリティシズムの視点から、新自由主義と個人主義を再考する試みを実践。先住民文学と日本文学を事例に、心身二元論の再構築と普遍的な認知科学モデルの超克を模索している。
ステファン・グルンバッハ Stephane Grumbach
フランス国立情報学オートメーション研究所(INRIA)上級研究員。グローバルな視点から、デジタル・トランスフォーメーションが、地球環境危機において、社会組織、地政学的均衡、地球のスチュワードシップをどう変容させるかについて研究。在北京フランス大使館の科学顧問として、国際関係にも携わる。自然科学、社会科学のディシプリン間を横断し、よりよいグローバル・ガバナンスの構築を目指す。
アンセルム・グルンバッハ Anselme Grumbach
ソフトウェア・エンジニアとして、分散型システムと分散コンピューティングの構築にとり組む。インターネット上での安全な情報保全とアクセスのためのウェブ上のネットワーク・システムである「セーフ・ネットワークSAFE Network」(アウトノミ)の開発の中心を担う。第188回地球研セミナー(2023年1月)で自身の経験をもとにデジタル上での分散型システムについて発表した。
熊澤 輝一 Terukazu Kumazawa
大阪経済大学国際共創学部教授。専門は、環境デザイン、知識情報学。東京工業大学大学院総合理工学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(工学)。大阪大学特任助教、立命館大学ポストドクトラルフェロー、総合地球環境学研究所准教授を経て、現在に至る。人間と自然との関係にかかわる分野横断型の知識を収集・蓄積し、編集して共有するための研究を進めてきた。特に、地球環境学や持続可能性科学にかかわるオントロジー開発を担う。現在は、沖縄本島を主なフィールドに、湧き水のアーカイブづくりを進める市民の活動を支援しながら、水場から地域を知るための情報ツール開発に取り組んでいる。
松井孝典 Takanori Matsui
現在、大阪大学大学院工学研究科の助教を務める。彼の専門は、持続可能性科学、環境学、情報学。彼は2005年に大阪大学大学院工学研究科で博士号(工学)を取得。人工知能、環境問題、持続可能性といった分野において、学際的な研究を精力的に行っている献身的な研究者である。これらの分野に関する多くの研究論文や書籍を執筆しており、その専門性を示した。特に、急速に進むデジタル化がもたらす環境問題や人間とデジタル空間の相互作用に関する研究は、大きな注目を集めており、テクノロジー、社会、環境の複雑な相互作用を探求し、現代社会が直面する多面的課題の理解と解決を目指している。研究と出版物に関する詳細情報については、ORCIDプロフィール(https://orcid.org/0000-0001-9441-7664)を参照。
小野聡 Satoru Ono
博士(工学)、千葉商科大学商経学部専任講師、立命館大学歴史都市防災研究所客員研究員。東京工業大学理学部卒業、東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程・博士後期課程修了。同大学院特別研究員、立命館大学政策科学部助教などを経て、現在に至る。専門は社会工学、環境計画、協働型計画。シミュレーションに基づく参加型計画決定支援を主たる研究フィールドとする。
山極壽一 Juichi Yamagiwa
総合地球環境学研究所所長。京都大学大学院理学研究科教授、同研究科長・理学部長を経て、2020年まで第26代京都大学総長。人類進化論専攻。屋久島で野生ニホンザル、アフリカ各地で野生ゴリラの社会生態学的研究に従事。日本霊長類学会会長、国際霊長類学会会長、日本学術会議会長、総合科学技術・イノベーション会議議員を歴任。南方熊楠賞、アカデミア賞受賞。著書に『ゴリラ』(東京大学出版会、2005年)、『家族進化論』(東京大学出版会、2012年)、『共感革命——社交する人類の進化と未来』(河出新書、2023年)など多数。
和出伸一 Shin-ichi Wade
美術家・デザイナー。象灯舎代表。絵画や映像、アニメーションの制作を中心に活動を続けている。総合地球環境学研究所広報室などを経て、現在フリー。ここ15年ほどは、描くこと、つくることを、一から手探りで捉え直そうと試みるも、現在遭難中。作品集に『身土¥文字(U+2014)¥文字(U+2014)人の世の底に触れる』(あいり出版、2022年)。マンガ作品に「至西方」(2020年¥文字(U+2014)、暮らしのモンタージュ・ウェブサイトで連載中)。主な展覧会に、「SIGNAL 和出伸一・2,000 のドローイング」(ギャラリーRAKU、2004年)、「Life/Painting」(ギャラリーRAKU、2005年)、「Art Court Frontier 2014 #12」(アートコートギャラリー、2014年)など。https://wadeshin.com/
黄桃 Ou Tou
小説家。日本語の物語・小説の文体の過去の蓄積(古語、文語、言文一致)を踏まえながら、現代という、英語によるグローバル化とAIなどの機械により生成される文章化の時代の日本語の小説の文体創出を実験的に実践。「物語の穴」の内と外や、小説の中のあなたとはだれかなどをめぐる形而上と形而下について物語的探究を行う。「星形の小説」、「城、城市」が、それぞれ、群像新人文学賞(講談社)と文學界新人賞(文藝春秋)の第二次選考の候補作になる。おもな作品に、「AKT II」、「MobyDickアメリカ——アメリカの中に書かれた小説」、「とぅ みーと こじき」、「Violettchenむらさきちゃん」、「インドに書かれる/花籠の中で」、「Das城」、「飛ぶ家」ほか。
総合地球環境学研究所客員教授。人文地球環境学。ひと、いきもの、ものを包括した環境とはどのように論じられるべきなのか、科学に基づく二元論的世界観と生活世界の実感としての全体論的世界観はどう関係するかなどを研究。近年は、そのような視角から、未来可能性に資する学としての風土学の可能性を探求。著書に、『人新世の風土学——地球を〈読む〉ための本棚』(昭和堂、2023年)、『人文地球環境学——ひと、もの、いきものと世界/出来』(あいり出版、2021年)、『人新世を問う——環境、人文、アジアの視点』(ダニエル・ナイルズと共編、京都大学学術出版会、2021年)、『カタストロフと時間——記憶/語りと歴史の生成』(京都大学学術出版会、2018年)、『人は火山に何を見るのか——環境と記憶/歴史』(昭和堂、2015年)ほか。「叢書・地球のナラティブ」(あいり出版、2019年−)、「シリーズ よむかくくらすかんがえるの本棚」(あいり出版、2023年−)のシリーズ・エディターもつとめる。国立歴史民俗博物館COE研究員、国立民族学博物館外来研究員、総合地球環境学研究所特任准教授、マックスプランク科学史研究所客員研究員を歴任。
ジェイソン・リュス・パリー Jason Rhys Parry
ユバル・ノア・ハラリ財団「サピエンシップ」上級コンテンツ開発研究員。米国パドゥ大学客員教授、総合地球環境学研究所フェローシップ外国人研究員を歴任。技術と文化に関する論考を執筆。19世紀ブラジルの女性作家フリア・ロペス・アルメイダ『破綻』を英語に初訳(共訳)した(カリフォルニア大学出版局、2023年)。
ブレイズ・セールス Blaise Sales
英国リーズ大学大学院ホワイト・ローズ・カレッジ(芸術・人文学専攻)博士課程。ロンドン・キングズ・カレッジで英文学士、ヨーク大学で医療人文学修士を取得。博士論文では、認知の身体化とエコクリティシズムの視点から、新自由主義と個人主義を再考する試みを実践。先住民文学と日本文学を事例に、心身二元論の再構築と普遍的な認知科学モデルの超克を模索している。
ステファン・グルンバッハ Stephane Grumbach
フランス国立情報学オートメーション研究所(INRIA)上級研究員。グローバルな視点から、デジタル・トランスフォーメーションが、地球環境危機において、社会組織、地政学的均衡、地球のスチュワードシップをどう変容させるかについて研究。在北京フランス大使館の科学顧問として、国際関係にも携わる。自然科学、社会科学のディシプリン間を横断し、よりよいグローバル・ガバナンスの構築を目指す。
アンセルム・グルンバッハ Anselme Grumbach
ソフトウェア・エンジニアとして、分散型システムと分散コンピューティングの構築にとり組む。インターネット上での安全な情報保全とアクセスのためのウェブ上のネットワーク・システムである「セーフ・ネットワークSAFE Network」(アウトノミ)の開発の中心を担う。第188回地球研セミナー(2023年1月)で自身の経験をもとにデジタル上での分散型システムについて発表した。
熊澤 輝一 Terukazu Kumazawa
大阪経済大学国際共創学部教授。専門は、環境デザイン、知識情報学。東京工業大学大学院総合理工学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(工学)。大阪大学特任助教、立命館大学ポストドクトラルフェロー、総合地球環境学研究所准教授を経て、現在に至る。人間と自然との関係にかかわる分野横断型の知識を収集・蓄積し、編集して共有するための研究を進めてきた。特に、地球環境学や持続可能性科学にかかわるオントロジー開発を担う。現在は、沖縄本島を主なフィールドに、湧き水のアーカイブづくりを進める市民の活動を支援しながら、水場から地域を知るための情報ツール開発に取り組んでいる。
松井孝典 Takanori Matsui
現在、大阪大学大学院工学研究科の助教を務める。彼の専門は、持続可能性科学、環境学、情報学。彼は2005年に大阪大学大学院工学研究科で博士号(工学)を取得。人工知能、環境問題、持続可能性といった分野において、学際的な研究を精力的に行っている献身的な研究者である。これらの分野に関する多くの研究論文や書籍を執筆しており、その専門性を示した。特に、急速に進むデジタル化がもたらす環境問題や人間とデジタル空間の相互作用に関する研究は、大きな注目を集めており、テクノロジー、社会、環境の複雑な相互作用を探求し、現代社会が直面する多面的課題の理解と解決を目指している。研究と出版物に関する詳細情報については、ORCIDプロフィール(https://orcid.org/0000-0001-9441-7664)を参照。
小野聡 Satoru Ono
博士(工学)、千葉商科大学商経学部専任講師、立命館大学歴史都市防災研究所客員研究員。東京工業大学理学部卒業、東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程・博士後期課程修了。同大学院特別研究員、立命館大学政策科学部助教などを経て、現在に至る。専門は社会工学、環境計画、協働型計画。シミュレーションに基づく参加型計画決定支援を主たる研究フィールドとする。
山極壽一 Juichi Yamagiwa
総合地球環境学研究所所長。京都大学大学院理学研究科教授、同研究科長・理学部長を経て、2020年まで第26代京都大学総長。人類進化論専攻。屋久島で野生ニホンザル、アフリカ各地で野生ゴリラの社会生態学的研究に従事。日本霊長類学会会長、国際霊長類学会会長、日本学術会議会長、総合科学技術・イノベーション会議議員を歴任。南方熊楠賞、アカデミア賞受賞。著書に『ゴリラ』(東京大学出版会、2005年)、『家族進化論』(東京大学出版会、2012年)、『共感革命——社交する人類の進化と未来』(河出新書、2023年)など多数。
和出伸一 Shin-ichi Wade
美術家・デザイナー。象灯舎代表。絵画や映像、アニメーションの制作を中心に活動を続けている。総合地球環境学研究所広報室などを経て、現在フリー。ここ15年ほどは、描くこと、つくることを、一から手探りで捉え直そうと試みるも、現在遭難中。作品集に『身土¥文字(U+2014)¥文字(U+2014)人の世の底に触れる』(あいり出版、2022年)。マンガ作品に「至西方」(2020年¥文字(U+2014)、暮らしのモンタージュ・ウェブサイトで連載中)。主な展覧会に、「SIGNAL 和出伸一・2,000 のドローイング」(ギャラリーRAKU、2004年)、「Life/Painting」(ギャラリーRAKU、2005年)、「Art Court Frontier 2014 #12」(アートコートギャラリー、2014年)など。https://wadeshin.com/
黄桃 Ou Tou
小説家。日本語の物語・小説の文体の過去の蓄積(古語、文語、言文一致)を踏まえながら、現代という、英語によるグローバル化とAIなどの機械により生成される文章化の時代の日本語の小説の文体創出を実験的に実践。「物語の穴」の内と外や、小説の中のあなたとはだれかなどをめぐる形而上と形而下について物語的探究を行う。「星形の小説」、「城、城市」が、それぞれ、群像新人文学賞(講談社)と文學界新人賞(文藝春秋)の第二次選考の候補作になる。おもな作品に、「AKT II」、「MobyDickアメリカ——アメリカの中に書かれた小説」、「とぅ みーと こじき」、「Violettchenむらさきちゃん」、「インドに書かれる/花籠の中で」、「Das城」、「飛ぶ家」ほか。
まえがき
序章 「風土」をアップデートする (寺田匡宏)
1 なぜ本書を刊行するのか1
未来と環境学
なぜ風土なのか
ひと、いきもの、思考する機械の共存在
地球環境と「風土」
2 風土をアップデートする
複数の主体が織りなす現象
地球、土地、ガイア
環世界、環境、風土
和辻哲郎とオギュスタン・ベルクの風土学
風土概念をめぐる困難とその克服——自然科学と生活世界の乖離の問題
一元論と二元論——意識をめぐる科学と形而上学
パンサイキズムとアニミズム
人間の不在のフューチャー風土
3 本書の構成
本書はだれが書いたか
本書に至る三つの流れ
論文と小説とアートによるマルチ・モーダルなコミットメント
風土概念の展開を探る第Ⅰ部
いきものと風土の未来を探る第II部
機械という自律システムの風土性を探る第III部
未来構想の方法を探る第IV部
マルチ・モーダルな未来像を提示する第V部
第I部 風土学の視界——理論と来歴、その射程
[総論]第1章 「風土学」史——東アジア二〇〇〇年の歴史から(寺田匡宏)
歴史を書くこととは
風土学の「転回」
未来の風土学
1 風土という語
フード、フントゥ、プント
古代中国における「風土」の用例
風気水土
2 中国古代・周処の『風土記』の風土学——民俗学転回
周処と『風土記』
宗懍の『荊楚歳時記』
周処『風土記』に見る長江流域の年中民俗行事
民俗としての風土
「史」へのオルタナティブとしての風土
3 日本の奈良時代の『風土記』の風土学——神話学的アニミズム的転回
奈良時代の国家的全国地誌調査
国家によるカミの編成
国家以前のカミの記憶
日本における風土学の神話学的転回
カミと神話とアニミズム
4 和辻哲郎の風土学——現象学的転回
「風土学」構想
哲学者・和辻哲郎
ハイデガー『存在と時間』への応答として
「風土は自然ではない」
三つの風土における人間類型——モンスーン、砂漠、牧場
西洋の学問世界と和辻「風土学」
5 オギュスタン・ベルクの風土学——記号学的存在論的転回
フランス語と日本語のあいだの「あいだ学」
トラジェクシオン、通態
トラジェクシオン・チェーン、あるいは通態の連鎖
ユクスキュルの環世界学、今西錦司の自然学、
山内得立のレンマ学の導入——存在論的転回
6 風土学の未来、未来の風土学
[各論]第2章 風土、モニズム、パンサイキズム(寺田匡宏)
1 風土の構造
実存が世界の中にあること
客観的世界とそれを見ている主観という構図
外に出ている自己
自己が自己を見る
自己が自己を見る場所——和辻と西田幾多郎
自己と絶対無
身体性と風土
風土における多と一の矛盾的自己同一
身体の位置
心身二元論批判、すなわちモニズムの提唱
2 環境モニズムとしての風土——和辻、ハイデガー、ユクスキュル、ラッセル
モニズムとは何か
二〇世紀初頭における「環境モニズム」
四つの環境モニズム
主体と内と外
二元論批判
排中律の「矛盾」の先へ
危機の時代とオルタナティブの世界観
3 パンサイキズム(汎精神論)と風土の倫理
パンサイキズムの現代的意味
歴史上のパンサイキストたち
心の哲学から意識の哲学へ
全体論としてのパンサイキズム
アニミズムとパンサイキズム
[各論]第3章 西田幾多郎と環境——風土学としての西田哲学(寺田匡宏)
1 風土学としての西田哲学
2 西田幾多郎の生涯とその思想
近代日本哲学の第一世代
西田哲学の発展の三区分
3 西田における「環境」
西田における「環境」の出現
「二にして一」の環境と個物——矛盾と弁証法
生命を可能にする場
環境と生命、歴史と主体の問題
4 西田、和辻、岩波書店——風土学を生んだ思考のトポス
『思想』編集人としての和辻哲郎
刊行直後の『善の研究』を読む二四歳の和辻
『思想』、和辻、西田
互いの論文を読み合う西田と和辻
5 『善の研究』と『ニイチェ研究』——西田と和辻の第一作に見るモニズム
「同期デビュー」の西田と和辻
和辻『ニイチェ研究』にみる主観客観の分離と統一
西田『善の研究』における「実在の分化発展」と「統一」
6 自然から環境へ
[各論]第4章 仙境と砂漠——精神の風土学(ジェイソン・リュス・パリー)
第II部 いきものと未来風土——アニマル、アニミズム、ハーモニー
[総論]第1章 調和と共存在の風土学——ユクスキュル、今西錦司、バイオセミオティクスにおけるいきものの位置(寺田匡宏)
風土学にいきものは含まれているか
バイオセミオティクスと風土学
1 ユクスキュルの環世界学と環境モニズム・風土
ユクスキュルの生涯
エストニアの貴族として
ドルパット(タルトゥ)からハイデルベルク、ナポリへ
環世界学の確立をめざして
ハンブルク大学「環世界学研究所」
環世界フィードバック・ループ——『生物の内的世界と環世界』
カント、全体プラン適合性、反ダーウィニズム——『理論生物学』
複数の世界観と永遠に不可知の自然——『生物から見た世界』
2 今西錦司からみる共存在・進化・風土
進化論と自然学
今西はユクスキュルを読んだか
一者からなる世界
棲み分け・シンビオジェネシス・共存在
立つべくして立つ——進化における主体性
進化論における今西とユクスキュルの相似
ハーモニーと調和
3 バイオセミオティクスと風土学
セミオティクス、記号学
バイオセミオティクス、生物記号学、生命記号学
記号の連鎖と「三」という数
記号の連鎖と進化、生命の出現
化学進化と生命
通態の連鎖とバイオセミオティクス
風土学といきもの、もの
[各論]第2章 記号の森——セミオダイバーシティ(記号多様性)から見る風土(ジェイソン・リュス・パリー)
1 揮発物質のブレンドと植物の文法
2 セミオダイバーシティ(記号多様性)概念の確立に向かって
3 セミオダイバーシティ(記号多様性)から風土を考える
[各論]第3章 流動の中で思考する——石牟礼道子とリンダ・ホーガンの アニミズムと環境の詩学(ブレイズ・セールス)
1 先住民、女性、自然から見る風土
2 「批判的アニミズム」と「知の帝国主義」
3 リンダ・ホーガン『太陽嵐』における皮膚と水の再記憶
4 石牟礼道子『天湖』における弦と音の波紋
5 多様で非均一な世界を想像する詩学へ
第III部 風土としての自律システム——AI、サイバー空間、デジタルエコロジー
[総論]第1章 断末期の地球でAIとの共生は可能か——複雑システム論と全体論(ホーリズム)的視座からの分析(ステファン・グルンバッハ)
1 現在とはどのような時代か
知性を持つ機械
プラネタリー・バウンダリー
歴史的に見た現在のトランスフォーメーションの特徴
複雑性の増大として過去を見る
複雑性が人間の対応能力を超えるとき
本章の構成
2 複雑性はいかにして人間のキャパシティの限界へと至ったか
人口増加と複雑性
複雑性と複雑システム
複雑システムにおける適応
歴史、すなわち複雑性の増大
人口、複雑性、歴史
食糧生産と人口
現在の人口減少に見るトランスフォーメーション
危機と臨界点
構造的人口動態理論
社会の崩壊の諸相
全体論的視座からの逃走
全体論としての複雑システム論
宗教という全体論から、科学という全体論へ
科学の無力と全体論への希求
3 複雑性の超克と情報のコントロール
情報処理とフィードバック・ループ
全体論として見る地球の情報処理システム
自然という地球規模の「情報スフィア」
社会と自然の間での情報の交換
AIへの道(1)——ガバナンスの進化
ガバナンスと自由——ポランニー・ハイエク論争、デューイ・リップマン論争
複雑性の理解はいかに可能か
社会の複雑性と法、情報処理
パーソナライズされるガバナンス
AIへの道(2)——知識の進化
既知、既知の未知、未知、未知の未知
現代における科学の困難
科学における生産性の低下
知識生産と経済成長
AIの出現
AI小史
AIを可能にした二つの革命
生成AIの登場
4 人間の理性という幻想
人間の限界(1)認知能力の限界
経験的観察と精密化
認知特性と行動
認知の多様性と文化の多様性
人間の限界(2)バイアス
バイアスと文化
世界と自然のコントロールという幻想
科学技術の発展と全能という幻想——一九世紀
戦争による幻滅と技術の未来への悲観論——二〇世紀
物質主義の隆盛と魂への蔑視
5 西洋の限界を超えて
新たな哲学の必要
人類進化と危機
西洋パラダイムの世界支配
自然の支配という西洋パラダイム
人類全体のレジリエンスを考える哲学の必要
[各論]第2章 デジタル空間における分散的システムの出現——ビットコインとブロックチェーンがひらく未来(アンセルム・グルンバッハ)
1 集中化と分散化
2 システムから見る集中と分散
3 ビットコインというシンギュラリティ(特異点)
4 ポスト・ビットコインの世界
5 AIの出現と分散型システム
[各論]第3章 デジタルの中のクオリア(松井孝典)
1 サイバー空間へと向かう道
2 二つの風土で生じる環境問題
3 デノイズ・デフェイク
4 デジタル資源循環と継承
5 デジタルエコシステムの調律
6 デジタルの中のクオリア
[各論]第4章 アニミズム・マシーン(寺田匡宏)
1 なぜ、どのように自律的システムとしての機械がフューチャー風土にくみこまれるのか
デジタル構想の地政学
ソサエティ五・〇における主体としてのAI
2 機械とは何か、非=人間とは何か
政治的主体概念の拡張
ハイデガーのひと、いきもの、ものの三区分
世界の制作と言語による構築
心の哲学と二元論、その批判
コンピュータにおける知性とはなにか
グラデーションとしての存在論
3 自然観のグラデーション
自然を文化と区分するもの
アニミズム、トーテミズム、ナチュラリズム、アナロジズム
もの、妖怪、アニミズム
デジタルネイチャー
[各論]第5章 アウトスαὐτός——「自」の発生と宇宙の開始、あるいは個物と全体の同時生成について(寺田匡宏)
「自」と「アウトス」
自己が自己を見る——和辻哲郎
境界にあらわれる自己——ヴィトゲンシュタイン
自己の限界と視野の限界
自己の中にすでに存在する世界——エルンスト・マッハ
知覚の問題としての個物と全体——オートポイエシス
個物と全体が構成する「超有機体」——ガイア理論
運動を通じた個物と全体の関係——ヴァイツゼッカーのゲシュタルト・クライス
自己を見る自己と自己に見られる自己をメタレベルで統御する自己——木村敏
縁起という円環——ゴータマ・ブッダ
純粋経験という全体——ウィリアム・ジェームズ
ものと精神のカップリングから来る自己——リン・マルギュリス
実在と自己同一性——西田幾多郎
分化と統一、意識
ビッグバン理論と認識の問題、「自」の発生
「アウトス」と「自」のアクチュアリティ
第IV部 未来風土とそのカテゴリー——計算機言語、予測、不確実性から考える
[総論]第1章 未来風土とそのカテゴリー——だれが〈非=人間〉のフューチャー風土を語るのか(寺田匡宏)
1 風土と宇宙、時間
2 持続可能性と未来
3 歴史、予言、未来史
4 プレゼンティズム——マクタガート
5 可能態と現実態——アリストテレスとプラトン
6 兆候、手がかり、存在のグラデーション、ナチュラリズム
7 未来の確からしさと制度
8 だれが〈非=人間〉のフューチャー風土を語るのか
[各論]第2章 風土を構造的知識として記述する——オントロジー工学はいかに風土にアプローチするか(熊澤輝一)
1 オントロジー工学で風土を記述すること
2 構造的知識(オントロジー工学)という道具
風土と道具
オントロジー工学とは
3 概念を記述する——「寒さ」をオントロジー工学で記述する
「寒さ」とは何かを記述するにはどうすればよいか
寒さと気温五℃を区別する
4 関係を記述する——連関の中で「寒さ」を捉える523
連関の中で「寒さ」を捉える
時間軸の観点から関係記述を考える
5 風土における背景の解釈に向けて
[各論]第3章 予測社会の風土論——「不確実性」への関心は人間に何をもたらすか(小野聡)
1 「不確実性」への関心と「予測」
2 不確実性の「動態的な表象」——「台風の上陸」にまつわる試論
3 先端技術は不確定性の表象を提供する「眼」であり続けるのか
4 先端技術が提供する表象と自己——一〇個のクラスターが問いかけるもの
信頼する予測情報と年齢の相関
各クラスターにおける信頼する予測情報の特徴
リスク判断の場面を想定した信頼する予測情報とクラスター1の特色
クラスター1の存在は何を物語るのか
動態的な表象の向こうに映る自己
5 自らの価値観の反映としての「予測」への態度——風土論と社会システムに対する示唆
[各論]第4章 火星風土記(寺田匡宏)
1 二酸化炭素の風、酸化した赤い砂——火星の風気水土
2 土地の名、産物——火星探査
3 名所、聖地、ロボット
4 「ホモ・マルシアンHomo martian」、あるいは人類の新たなタクソノミー
5 一万年後の火星地図——なぜ宇宙が未来なのか
第V部 想像と創造のフューチャー風土——イマジネーションとアートによるコミットメント
[インタビュー]力の文明から慈悲と利他の文明へ——山極壽一、地球と人類の未来を語る (山極壽一)
1 人類進化史的過去を振り返る——我々の現代はいかにしてこのようになったか579
直立二足歩行の開始——七〇〇万年前
集団の拡大と脳の容量の増大——二〇〇万年前
言語の出現——一〇—七万年前
農耕の開始——一万年前
都市の開始——四〇〇〇年前
産業革命——四〇〇年前
2 現在とはどんな時代か——AIと自然観の視点から見る
デカルトの思想が行きついたAI
力の文明から慈悲と利他の文明へ
ひと、山、川、いきものが一体となった美しい風景
第二のジャポニスム
村上春樹のパラレル・ワールド
機械論と結びついたパラレル・ワールドのディストピア
3 コモンズ、シェアと未来の地球588
知識の外部化、中枢神経系から分散神経系へ
中央集中型から、分散型社会へ
第二のノマド時代と社交
ウィルス、細菌と人間
4 一〇〇万年後の未来の地球
力の文明の終焉——一〇〇年後の未来
生態系と都市の調和——一万年後のユートピア・シナリオ
二分化された世界というディストピア——一万年後の惑星移住
人類が滅びた後の地球——一〇万年後の未来
大絶滅を超えて——一〇〇万年後の未来
生物の多様化の方向性と、譲るという人間の本質
共感という人間の精神性の復活に向かって
[写真ギャラリー]身土(和出伸一)
身土と風土
[対談]〈非=人間〉的身土・景——現実、外部、言語 (和出伸一×寺田匡宏)
外に触れたい
人のいない世界
境界と内と外
ものの世界とアレゴリー、メタファー
時間と物語
〈非=人間〉の未来
物語という罪
他者をどうとらえるか
自己以前の自己
科学の言語、メタファーの言語
[特論]風土、身土、国土、浄土——不二とモニズム(寺田匡宏)
1 仏教における浄土と国土
浄土と浄土教
浄土経典
国土と浄土
風土、国土、浄土を横断する和辻の著書たち
2 日本中世における「身土」——親鸞と日蓮
真のブッダにどうアクセスするか——親鸞
身土不二——日蓮/中世日本におけるエンボディメント(身体化)
3 モニズムと「不二」——『善の研究』以前の西田幾多郎と鈴木大拙
西田幾多郎における「見仏性」
寸心幾多郎と大拙貞太郎
オープン・コート社と雑誌『モニスト』
モニズムからの仏教への期待
西田の書斎のスピノザとブッダ
[掌編小説]砂の上のコレオグラフィー(ジェイソン・リュス・パリー、マンガ=和出伸一)
[掌編小説]電気羊はアンドロイドの夢を見るのか(ステファン・グルンバッハ、マンガ=和出伸一)
[掌編小説]とぅ みーと ふどき(黄桃、マンガ=和出伸一)
[掌編小説]火星の穴(黄桃、マンガ=和出伸一)
[掌編小説]天空の蜘蛛の網(ブレイズ・セールス、マンガ=和出伸一)
[掌編小説]粘菌とアストロサイコロジー(黄桃、マンガ=和出伸一)
終章 フューチャー風土学綱領(寺田匡宏)
1 フューチャー風土学の論理
2 ひと、いきもの、もの、機械を含む学としての
フューチャー風土学
3 未来への学としてのフューチャー風土学
4 コミットメントと運動体としてのフューチャー風土学
助成一覧
索引
英文著者紹介・英文要旨
著者紹介
序章 「風土」をアップデートする (寺田匡宏)
1 なぜ本書を刊行するのか1
未来と環境学
なぜ風土なのか
ひと、いきもの、思考する機械の共存在
地球環境と「風土」
2 風土をアップデートする
複数の主体が織りなす現象
地球、土地、ガイア
環世界、環境、風土
和辻哲郎とオギュスタン・ベルクの風土学
風土概念をめぐる困難とその克服——自然科学と生活世界の乖離の問題
一元論と二元論——意識をめぐる科学と形而上学
パンサイキズムとアニミズム
人間の不在のフューチャー風土
3 本書の構成
本書はだれが書いたか
本書に至る三つの流れ
論文と小説とアートによるマルチ・モーダルなコミットメント
風土概念の展開を探る第Ⅰ部
いきものと風土の未来を探る第II部
機械という自律システムの風土性を探る第III部
未来構想の方法を探る第IV部
マルチ・モーダルな未来像を提示する第V部
第I部 風土学の視界——理論と来歴、その射程
[総論]第1章 「風土学」史——東アジア二〇〇〇年の歴史から(寺田匡宏)
歴史を書くこととは
風土学の「転回」
未来の風土学
1 風土という語
フード、フントゥ、プント
古代中国における「風土」の用例
風気水土
2 中国古代・周処の『風土記』の風土学——民俗学転回
周処と『風土記』
宗懍の『荊楚歳時記』
周処『風土記』に見る長江流域の年中民俗行事
民俗としての風土
「史」へのオルタナティブとしての風土
3 日本の奈良時代の『風土記』の風土学——神話学的アニミズム的転回
奈良時代の国家的全国地誌調査
国家によるカミの編成
国家以前のカミの記憶
日本における風土学の神話学的転回
カミと神話とアニミズム
4 和辻哲郎の風土学——現象学的転回
「風土学」構想
哲学者・和辻哲郎
ハイデガー『存在と時間』への応答として
「風土は自然ではない」
三つの風土における人間類型——モンスーン、砂漠、牧場
西洋の学問世界と和辻「風土学」
5 オギュスタン・ベルクの風土学——記号学的存在論的転回
フランス語と日本語のあいだの「あいだ学」
トラジェクシオン、通態
トラジェクシオン・チェーン、あるいは通態の連鎖
ユクスキュルの環世界学、今西錦司の自然学、
山内得立のレンマ学の導入——存在論的転回
6 風土学の未来、未来の風土学
[各論]第2章 風土、モニズム、パンサイキズム(寺田匡宏)
1 風土の構造
実存が世界の中にあること
客観的世界とそれを見ている主観という構図
外に出ている自己
自己が自己を見る
自己が自己を見る場所——和辻と西田幾多郎
自己と絶対無
身体性と風土
風土における多と一の矛盾的自己同一
身体の位置
心身二元論批判、すなわちモニズムの提唱
2 環境モニズムとしての風土——和辻、ハイデガー、ユクスキュル、ラッセル
モニズムとは何か
二〇世紀初頭における「環境モニズム」
四つの環境モニズム
主体と内と外
二元論批判
排中律の「矛盾」の先へ
危機の時代とオルタナティブの世界観
3 パンサイキズム(汎精神論)と風土の倫理
パンサイキズムの現代的意味
歴史上のパンサイキストたち
心の哲学から意識の哲学へ
全体論としてのパンサイキズム
アニミズムとパンサイキズム
[各論]第3章 西田幾多郎と環境——風土学としての西田哲学(寺田匡宏)
1 風土学としての西田哲学
2 西田幾多郎の生涯とその思想
近代日本哲学の第一世代
西田哲学の発展の三区分
3 西田における「環境」
西田における「環境」の出現
「二にして一」の環境と個物——矛盾と弁証法
生命を可能にする場
環境と生命、歴史と主体の問題
4 西田、和辻、岩波書店——風土学を生んだ思考のトポス
『思想』編集人としての和辻哲郎
刊行直後の『善の研究』を読む二四歳の和辻
『思想』、和辻、西田
互いの論文を読み合う西田と和辻
5 『善の研究』と『ニイチェ研究』——西田と和辻の第一作に見るモニズム
「同期デビュー」の西田と和辻
和辻『ニイチェ研究』にみる主観客観の分離と統一
西田『善の研究』における「実在の分化発展」と「統一」
6 自然から環境へ
[各論]第4章 仙境と砂漠——精神の風土学(ジェイソン・リュス・パリー)
第II部 いきものと未来風土——アニマル、アニミズム、ハーモニー
[総論]第1章 調和と共存在の風土学——ユクスキュル、今西錦司、バイオセミオティクスにおけるいきものの位置(寺田匡宏)
風土学にいきものは含まれているか
バイオセミオティクスと風土学
1 ユクスキュルの環世界学と環境モニズム・風土
ユクスキュルの生涯
エストニアの貴族として
ドルパット(タルトゥ)からハイデルベルク、ナポリへ
環世界学の確立をめざして
ハンブルク大学「環世界学研究所」
環世界フィードバック・ループ——『生物の内的世界と環世界』
カント、全体プラン適合性、反ダーウィニズム——『理論生物学』
複数の世界観と永遠に不可知の自然——『生物から見た世界』
2 今西錦司からみる共存在・進化・風土
進化論と自然学
今西はユクスキュルを読んだか
一者からなる世界
棲み分け・シンビオジェネシス・共存在
立つべくして立つ——進化における主体性
進化論における今西とユクスキュルの相似
ハーモニーと調和
3 バイオセミオティクスと風土学
セミオティクス、記号学
バイオセミオティクス、生物記号学、生命記号学
記号の連鎖と「三」という数
記号の連鎖と進化、生命の出現
化学進化と生命
通態の連鎖とバイオセミオティクス
風土学といきもの、もの
[各論]第2章 記号の森——セミオダイバーシティ(記号多様性)から見る風土(ジェイソン・リュス・パリー)
1 揮発物質のブレンドと植物の文法
2 セミオダイバーシティ(記号多様性)概念の確立に向かって
3 セミオダイバーシティ(記号多様性)から風土を考える
[各論]第3章 流動の中で思考する——石牟礼道子とリンダ・ホーガンの アニミズムと環境の詩学(ブレイズ・セールス)
1 先住民、女性、自然から見る風土
2 「批判的アニミズム」と「知の帝国主義」
3 リンダ・ホーガン『太陽嵐』における皮膚と水の再記憶
4 石牟礼道子『天湖』における弦と音の波紋
5 多様で非均一な世界を想像する詩学へ
第III部 風土としての自律システム——AI、サイバー空間、デジタルエコロジー
[総論]第1章 断末期の地球でAIとの共生は可能か——複雑システム論と全体論(ホーリズム)的視座からの分析(ステファン・グルンバッハ)
1 現在とはどのような時代か
知性を持つ機械
プラネタリー・バウンダリー
歴史的に見た現在のトランスフォーメーションの特徴
複雑性の増大として過去を見る
複雑性が人間の対応能力を超えるとき
本章の構成
2 複雑性はいかにして人間のキャパシティの限界へと至ったか
人口増加と複雑性
複雑性と複雑システム
複雑システムにおける適応
歴史、すなわち複雑性の増大
人口、複雑性、歴史
食糧生産と人口
現在の人口減少に見るトランスフォーメーション
危機と臨界点
構造的人口動態理論
社会の崩壊の諸相
全体論的視座からの逃走
全体論としての複雑システム論
宗教という全体論から、科学という全体論へ
科学の無力と全体論への希求
3 複雑性の超克と情報のコントロール
情報処理とフィードバック・ループ
全体論として見る地球の情報処理システム
自然という地球規模の「情報スフィア」
社会と自然の間での情報の交換
AIへの道(1)——ガバナンスの進化
ガバナンスと自由——ポランニー・ハイエク論争、デューイ・リップマン論争
複雑性の理解はいかに可能か
社会の複雑性と法、情報処理
パーソナライズされるガバナンス
AIへの道(2)——知識の進化
既知、既知の未知、未知、未知の未知
現代における科学の困難
科学における生産性の低下
知識生産と経済成長
AIの出現
AI小史
AIを可能にした二つの革命
生成AIの登場
4 人間の理性という幻想
人間の限界(1)認知能力の限界
経験的観察と精密化
認知特性と行動
認知の多様性と文化の多様性
人間の限界(2)バイアス
バイアスと文化
世界と自然のコントロールという幻想
科学技術の発展と全能という幻想——一九世紀
戦争による幻滅と技術の未来への悲観論——二〇世紀
物質主義の隆盛と魂への蔑視
5 西洋の限界を超えて
新たな哲学の必要
人類進化と危機
西洋パラダイムの世界支配
自然の支配という西洋パラダイム
人類全体のレジリエンスを考える哲学の必要
[各論]第2章 デジタル空間における分散的システムの出現——ビットコインとブロックチェーンがひらく未来(アンセルム・グルンバッハ)
1 集中化と分散化
2 システムから見る集中と分散
3 ビットコインというシンギュラリティ(特異点)
4 ポスト・ビットコインの世界
5 AIの出現と分散型システム
[各論]第3章 デジタルの中のクオリア(松井孝典)
1 サイバー空間へと向かう道
2 二つの風土で生じる環境問題
3 デノイズ・デフェイク
4 デジタル資源循環と継承
5 デジタルエコシステムの調律
6 デジタルの中のクオリア
[各論]第4章 アニミズム・マシーン(寺田匡宏)
1 なぜ、どのように自律的システムとしての機械がフューチャー風土にくみこまれるのか
デジタル構想の地政学
ソサエティ五・〇における主体としてのAI
2 機械とは何か、非=人間とは何か
政治的主体概念の拡張
ハイデガーのひと、いきもの、ものの三区分
世界の制作と言語による構築
心の哲学と二元論、その批判
コンピュータにおける知性とはなにか
グラデーションとしての存在論
3 自然観のグラデーション
自然を文化と区分するもの
アニミズム、トーテミズム、ナチュラリズム、アナロジズム
もの、妖怪、アニミズム
デジタルネイチャー
[各論]第5章 アウトスαὐτός——「自」の発生と宇宙の開始、あるいは個物と全体の同時生成について(寺田匡宏)
「自」と「アウトス」
自己が自己を見る——和辻哲郎
境界にあらわれる自己——ヴィトゲンシュタイン
自己の限界と視野の限界
自己の中にすでに存在する世界——エルンスト・マッハ
知覚の問題としての個物と全体——オートポイエシス
個物と全体が構成する「超有機体」——ガイア理論
運動を通じた個物と全体の関係——ヴァイツゼッカーのゲシュタルト・クライス
自己を見る自己と自己に見られる自己をメタレベルで統御する自己——木村敏
縁起という円環——ゴータマ・ブッダ
純粋経験という全体——ウィリアム・ジェームズ
ものと精神のカップリングから来る自己——リン・マルギュリス
実在と自己同一性——西田幾多郎
分化と統一、意識
ビッグバン理論と認識の問題、「自」の発生
「アウトス」と「自」のアクチュアリティ
第IV部 未来風土とそのカテゴリー——計算機言語、予測、不確実性から考える
[総論]第1章 未来風土とそのカテゴリー——だれが〈非=人間〉のフューチャー風土を語るのか(寺田匡宏)
1 風土と宇宙、時間
2 持続可能性と未来
3 歴史、予言、未来史
4 プレゼンティズム——マクタガート
5 可能態と現実態——アリストテレスとプラトン
6 兆候、手がかり、存在のグラデーション、ナチュラリズム
7 未来の確からしさと制度
8 だれが〈非=人間〉のフューチャー風土を語るのか
[各論]第2章 風土を構造的知識として記述する——オントロジー工学はいかに風土にアプローチするか(熊澤輝一)
1 オントロジー工学で風土を記述すること
2 構造的知識(オントロジー工学)という道具
風土と道具
オントロジー工学とは
3 概念を記述する——「寒さ」をオントロジー工学で記述する
「寒さ」とは何かを記述するにはどうすればよいか
寒さと気温五℃を区別する
4 関係を記述する——連関の中で「寒さ」を捉える523
連関の中で「寒さ」を捉える
時間軸の観点から関係記述を考える
5 風土における背景の解釈に向けて
[各論]第3章 予測社会の風土論——「不確実性」への関心は人間に何をもたらすか(小野聡)
1 「不確実性」への関心と「予測」
2 不確実性の「動態的な表象」——「台風の上陸」にまつわる試論
3 先端技術は不確定性の表象を提供する「眼」であり続けるのか
4 先端技術が提供する表象と自己——一〇個のクラスターが問いかけるもの
信頼する予測情報と年齢の相関
各クラスターにおける信頼する予測情報の特徴
リスク判断の場面を想定した信頼する予測情報とクラスター1の特色
クラスター1の存在は何を物語るのか
動態的な表象の向こうに映る自己
5 自らの価値観の反映としての「予測」への態度——風土論と社会システムに対する示唆
[各論]第4章 火星風土記(寺田匡宏)
1 二酸化炭素の風、酸化した赤い砂——火星の風気水土
2 土地の名、産物——火星探査
3 名所、聖地、ロボット
4 「ホモ・マルシアンHomo martian」、あるいは人類の新たなタクソノミー
5 一万年後の火星地図——なぜ宇宙が未来なのか
第V部 想像と創造のフューチャー風土——イマジネーションとアートによるコミットメント
[インタビュー]力の文明から慈悲と利他の文明へ——山極壽一、地球と人類の未来を語る (山極壽一)
1 人類進化史的過去を振り返る——我々の現代はいかにしてこのようになったか579
直立二足歩行の開始——七〇〇万年前
集団の拡大と脳の容量の増大——二〇〇万年前
言語の出現——一〇—七万年前
農耕の開始——一万年前
都市の開始——四〇〇〇年前
産業革命——四〇〇年前
2 現在とはどんな時代か——AIと自然観の視点から見る
デカルトの思想が行きついたAI
力の文明から慈悲と利他の文明へ
ひと、山、川、いきものが一体となった美しい風景
第二のジャポニスム
村上春樹のパラレル・ワールド
機械論と結びついたパラレル・ワールドのディストピア
3 コモンズ、シェアと未来の地球588
知識の外部化、中枢神経系から分散神経系へ
中央集中型から、分散型社会へ
第二のノマド時代と社交
ウィルス、細菌と人間
4 一〇〇万年後の未来の地球
力の文明の終焉——一〇〇年後の未来
生態系と都市の調和——一万年後のユートピア・シナリオ
二分化された世界というディストピア——一万年後の惑星移住
人類が滅びた後の地球——一〇万年後の未来
大絶滅を超えて——一〇〇万年後の未来
生物の多様化の方向性と、譲るという人間の本質
共感という人間の精神性の復活に向かって
[写真ギャラリー]身土(和出伸一)
身土と風土
[対談]〈非=人間〉的身土・景——現実、外部、言語 (和出伸一×寺田匡宏)
外に触れたい
人のいない世界
境界と内と外
ものの世界とアレゴリー、メタファー
時間と物語
〈非=人間〉の未来
物語という罪
他者をどうとらえるか
自己以前の自己
科学の言語、メタファーの言語
[特論]風土、身土、国土、浄土——不二とモニズム(寺田匡宏)
1 仏教における浄土と国土
浄土と浄土教
浄土経典
国土と浄土
風土、国土、浄土を横断する和辻の著書たち
2 日本中世における「身土」——親鸞と日蓮
真のブッダにどうアクセスするか——親鸞
身土不二——日蓮/中世日本におけるエンボディメント(身体化)
3 モニズムと「不二」——『善の研究』以前の西田幾多郎と鈴木大拙
西田幾多郎における「見仏性」
寸心幾多郎と大拙貞太郎
オープン・コート社と雑誌『モニスト』
モニズムからの仏教への期待
西田の書斎のスピノザとブッダ
[掌編小説]砂の上のコレオグラフィー(ジェイソン・リュス・パリー、マンガ=和出伸一)
[掌編小説]電気羊はアンドロイドの夢を見るのか(ステファン・グルンバッハ、マンガ=和出伸一)
[掌編小説]とぅ みーと ふどき(黄桃、マンガ=和出伸一)
[掌編小説]火星の穴(黄桃、マンガ=和出伸一)
[掌編小説]天空の蜘蛛の網(ブレイズ・セールス、マンガ=和出伸一)
[掌編小説]粘菌とアストロサイコロジー(黄桃、マンガ=和出伸一)
終章 フューチャー風土学綱領(寺田匡宏)
1 フューチャー風土学の論理
2 ひと、いきもの、もの、機械を含む学としての
フューチャー風土学
3 未来への学としてのフューチャー風土学
4 コミットメントと運動体としてのフューチャー風土学
助成一覧
索引
英文著者紹介・英文要旨
著者紹介