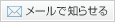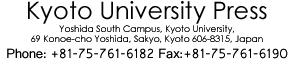Home > Book Detail Page

社会的動物と言われる種はヒト以外にもたくさんある。しかし、満員電車すなわち外敵からの防衛でも効率的な採餌でもない、適応的意味などどこにもないように見えるのに、身動きも取れない狭い空間で全く関わりのない他個体と数時間を過ごすようなことに耐えられるのはヒト以外にない。そうした独特な集団形成を可能にしたものの本質とは何か? しかしその問いを発した途端、新たな問題が現れる。「ヒトにしかない社会性」とは何なのか? そもそもそれを問う意味があるのか? 半世紀を超えて人類社会の進化について考え続けてきた著者たちが、いま、新たな議論のスタート地点に立つ。
*は編者
足立 薫(あだち かおる)
京都産業大学現代社会学部准教授
1968年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程単位取得後退学、博士(理学)。西アフリカでオナガザル類の混群を研究したのち、香港のマカクザルと人間の軋轢を通してエスノプライマトロジー研究に従事している。
主な著作に「環境の生成と消滅─人新世とエスノプライマトロジー」伊藤詞子編『生態人類学は挑む』(たえる・きざすSession6)(分担執筆、京都大学学術出版会、2022年)、「極限としての〈いきおい〉──移動する群れの社会性」河合香吏編『極限──人間社会の進化』(分担執筆、京都大学学術出版会、2020年)。
五十嵐 由里子(いがらし ゆりこ)
日本大学松戸歯学部解剖学講座准教授
1963年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。ヒトの骨や歯の形態とそれらに影響を与える因子の関連を分析し、先史社会の生活を復元する研究を行っている。
主な著作に、“Mandibular premolar identification system based on a deep learning model.” Journal of Oral Biosciences, 64(3): 321–328(分担執筆、2022年、DOI 10.1016/j.job.2022.05.005)、“Pregnancy parturition scars in the preauricular area and the association with the total number of pregnancies and parturitions”, American Journal of Physical Anthropology, 171(2): 260–274(分担執筆、2020年、DOI 10.1002/ajpa.23961)、 “A New Method for Estimation of Adult Skeletal Age at Death From the Morphology of the Auricular Surface of the Ilium.”, American Journal of Physical Anthropology, 128(2): 324–339(2005年 DOI 10.1002/ajpa.20081)など。
伊藤 詞子(いとう のりこ)
一般社団法人AKARH代表、京都大学アフリカ地域研究資料センター特任研究員
1971年生まれ。京都大学大学理学研究科単位取得退学。博士(理学)。生息環境を含む野生チンパンジーの研究を専門とする。
主な著作に、『たえる・きざす(生態人類学は挑む SESSION 6)』(編著、京都大学学術出版会、2022年)、『極限──人類社会の進化』(分担執筆、京都大学学術出版会、2020年)など。
内堀 基光(うちぼり もとみつ)
一橋大学名誉教授・放送大学名誉教授
1948年生まれ。オーストラリア国立大学太平洋地域研究所Ph.D.(人類学)取得。ボルネオ島の諸民族社会、とくにマレーシア・サラワク州のイバン人の宗教儀礼、世界観・存在論の研究を進めてきた。
主な著作に、『死の人類学』(共著、弘文堂/講談社、1986年/2006年)、『森の食べ方』(東京大学出版会、1996年)、『資源人類学(全9巻)』(総合編集、弘文堂、2007年)など。
大村 敬一(おおむら けいいち)
放送大学教養学部教授
1966年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科考古学専攻博士後期課程修了、博士(文学)。主にカナダ・イヌイトを対象に、その生業や在来知、社会関係について文化人類学的研究を進める。
主な著作に、Self and Other Images of Hunter-Gatherers(編著、National Museum of Ethnology、2002年)、『カナダ・イヌイトの民族誌──日常的実践のダイナミクス』(大阪大学出版会、2013年)、『宇宙人類学の挑戦──人類の未来を問う』(共編著、昭和堂、2014年)、The World Multiple: The Quotidian Politics of Knowing and Generating Entangled Worlds(共編著、Routledge、2018年)、『「人新世」時代の文化人類学』(共編著、放送大学教育振興会、2020年)、『「人新世」時代の文化人類学の挑戦──よみがえる対話の力』(共編著、以文社、2023年)、『新・方法序説──人類社会の進化に迫る認識と方法』(共編著、京都大学学術出版会、2023年)、『フィールドワークと民族誌』(共編著、放送大学教育振興会、2024年)など。
春日 直樹(かすが なおき)
一橋大学名誉教授
1953年生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程中退、博士(人間科学)。オセアニアを中心に、経済・歴史・文化・思考様式について人類学的な研究をおこなう。サントリー学芸賞(2001年)、第16回日本文化人類学会賞(2021年)を受賞。
主な論文に、「呪術、隠喩、同型──21世紀の構造主義へ」『文化人類学』86(4): 527-542)(2022年)。編著に、『現実批判の人類学──新世代のエスノグラフィへ』(世界思想社、2011年)、『科学と文化をつなぐ──アナロジーという思考様式』(東京大学出版会、2016年)、『文化人類学のエッセンス──世界をみる/変える』(竹沢尚一郎との共編、有斐閣、2021年)。
河合 香吏(かわい かおり)*
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授
1961年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。主に東アフリカの牧畜社会を対象に、その生業や集団間関係について生態人類学的研究を進める。第1回日本ナイル・エチオピア学会高島賞(1995年)を受賞。
主な著作に、『関わる・認める(生態人類学は挑む SESSION 5)』(編著、京都大学学術出版会、2022年)、Extremes: The Evolution of Human Sociality(編著、Kyoto university press and Trans Pacific Press、2023年)、「敵と友のはざまで──ドドスと隣接民族トゥルカナとの関係」太田至・曽我亨編『遊牧の思想──人類学がみる激動のアフリカ』(分担執筆、昭和堂、2019年)など。
近藤 祉秋(こんどう しあき)
屋号:知犬ラボ
1986年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程中退。後に論文博士(文学)を取得。内陸アラスカ先住民の間で現地調査をおこない、人間と動物の関係などに関して研究を進めている。
著作に、『犬に話しかけてはいけない──内陸アラスカのマルチスピーシーズ民族誌』(慶應義塾大学出版会、2022年)。主な論文に、「先住民とデジタル化する社会──先住民研究の新しい枠組みに向けて」『国立民族学博物館研究報告』48巻1号(共著、2023年)、「危機の「予言」が生み出す異種集合体──内陸アラスカ先住民の過去回帰言説を事例として」『文化人類学』86巻3号(2021年)がある。
杉山 祐子(すぎやま ゆうこ)
弘前大学名誉教授
1958年生まれ。筑波大学大学院歴史人類学研究科単位取得退学。博士(地域研究)。ザンビア、タンザニアの地方農村を対象にジェンダーの視点から生態人類学的研究をおこなっている。
主な著作に『アフリカから農を問い直す──自然社会の農学を求めて』(共著、京都大学学術出版会、2023年)、『サバンナの林を豊かに生きる──母系社会の人類学』(京都大学学術出版会、2022年)、『地方都市とローカリティー』(共著、弘前大学出版会、2016年)など。
スプレイグ,デイビッド S.(David S. Sprague)
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所フェロー
1958年生まれ。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構を経て現職。エール大学人類学 Ph.D.
主な著作に、Primates Face to Face: Humans and Non-Human Primate Interconnections and Conservation(分担執筆、Cambridge University Press、2002年)、『サルの生涯、ヒトの生涯──人生計画の生物学』(京都大学学術出版会、2004年)、The Macaque Connection(分担執筆、Springer、2012年)、『極限──人類社会の進化』(分担執筆、京都大学学術出版会、2020年)など。
曽我 亨(そが とおる)
弘前大学人文社会科学部教授
1964年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。
主な著作に、「東アフリカのラクダ牧畜民」今村薫編『ラクダ、苛烈な自然で人と生きる』(分担執筆、風響社、2023年)、Between Ethnic Favoritism and Ethnic Hatred, In: Kaori Kawai ed., Extremes: The Evolution of Human Sociality(分担執筆、Kyoto University Press and Trans Pacific Press、2023)、『遊牧の思想──人類学がみる激動のアフリカ』(共編著、昭和堂、2019年)など。
竹ノ下 祐二(たけのした ゆうじ)
岡山理科大学理学部動物学科教授
1970年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。主に大型類人猿とニホンザルを中心に、ヒト以外の霊長類の社会関係や生活史について社会生態学的研究を進める。
主な著作に、『新・方法序説──人類社会の進化に迫る認識と方法』(共編著、京都大学学術出版会、2023年)、『セックスの人類学(シリーズ来るべき人類学)』(共編著、春風社、2009年)、『たえる・きざす(生態人類学は挑む SESSION 6)』(分担執筆、京都大学学術出版会、2022年)など。
田中 雅一(たなか まさかず)
国際ファッション専門職大学副学長、京都大学名誉教授
1955年生まれ。ロンドン大学経済政治学院(LSE)博士課程修了、Ph.D.(Anthropology)。専門は文化人類学、南アジア民族誌、ジェンダー・セクシュアリティ研究。日本文化人類学会賞(2017年)を受賞。
主な著作に、『癒やしとイヤラシ──エロスの文化人類学』(筑摩書房、2010年)、『誘惑する文化人類学』(世界思想社、2018年)、『フェティシズム研究(全3巻)』(編著、京都大学学術出版会、2009/2014/2017年)、『トラウマ研究(全2巻)』(共編著、京都大学学術出版会、2018/2019年)など。
谷口 晴香(たにぐち はるか)
公立鳥取環境大学環境学部・講師
京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。専門は霊長類学。主にニホンザルを対象に環境がアカンボウの伴食関係や社会化の過程に与える影響について研究を進めている。
主な著作に、「ヤクシマザルの離乳期のアカンボウの伴食行動──アカンボウの集まりに着目して」『生態人類学会ニュースレター』28: 18-24(2022年)、“How the physical properties of food influence its selection by infant Japanese macaques inhabiting a snow‐covered area.”, American Journal of Primatology, 77: 285–295(2015年)、「積雪地域のニホンザルにおける採食品目の母子間不一致がもたらすアカンボウの採食行動」『生態人類学会ニュースレター』16: 2-4(2010年)など。
田村 大也(たむら まさや)
京都大学大学院理学研究科助教
1992年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。主に中央アフリカ西部に生息する野生ニシローランドゴリラを対象に、その社会や生態について行動生態学的研究を進める。
主な著作に、“Does kinship with the silverback matter?: Intragroup social relationships of immature wild western lowland gorillas after social upheaval.” Primates, 65: 397–410(共著、2024年)、“Protection service of a leading silverback male from external threats in wild western gorillas.”, Folia Primatologica, 95: 251–260(共著、2024年)、“Hand preference in unimanual and bimanual coordinated tasks in wild western lowland gorillas (Gorilla gorilla gorilla) feeding on African ginger (Zingiberaceae)”, American Journal of Physical Anthropology, 175: 531–545(2021年)。
外川 昌彦(とがわ まさひこ)
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授
慶應義塾大学大学院社会学研究科博士課程修了、博士(社会学)。専門は宗教人類学、南アジア研究。1992-97年にインドに留学、ベンガル農村社会で現地調査を行う。
主な著作に、An Abode of the Goddess: Kingship, Caste and Sacrificial Organization in a Bengal Village(Manohar Publishers、2006年)、『岡倉天心とインド──「アジアは一つ」が生まれるまで』(慶應義塾大学出版会、2023年)、Minorities and the State: Changing Social and Political Landscape of Bengal(共編著、SAGE Publications、2011年)、『アジアの社会参加仏教──政教関係の視座から』(共編著、北海道大学出版会、2015年)など。
床呂 郁哉(ところ いくや)
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授
専門は文化人類学、東南アジア地域研究。
主な著作に、『越境──スールー海域世界から』(岩波書店、1999年)、『東南アジアのイスラーム』(共著、東京外国語大学出版会、2012年)、『ものの人類学』及び『ものの人類学2』(共編著、京都大学学術出版会、2011/2019年)、『わざの人類学』(編著、京都大学学術出版会、2021年)など。
中川 尚史(なかがわ なおふみ)
京都大学大学院理学研究科教授
1960年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。国内では主に宮城県・金華山島と鹿児島県・屋久島のニホンザル、海外では主にガーナ・モレとカメルーン・カラマルエのパタスモンキーを対象に、社会・生態学的研究を進めてきた。日本霊長類学会前会長、ニホンザル管理協会代表理事。日本霊長類学会学術奨励賞受賞。
主な著作に、『霊長類学の百科事典』(編著、丸善書店、2023年)、『日本のサル──哺乳類学としてのニホンザル研究』(編著、東京大学出版会、2017年)、『〝ふつう〟のサルが語るヒトの起源と進化』(ぷねうま書房、2015年)、The Japanese Macaques(編著、Springer、2010年)など。
中村 美知夫(なかむら みちお)
京都大学大学院理学研究科准教授
京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。主にタンザニアの野生チンパンジーを対象に、その社会や文化についての研究を進める。
主な著作に、『「サル学」の系譜──人とチンパンジーの50年』(中公叢書、2015年)、『インタラクションの境界と接続──サル・人・会話研究から』(共編、昭和堂、2010年)、『チンパンジー──ことばのない彼らが語ること』(中公新書、2009年) など。
西井 凉子(にしい りょうこ)
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授
1959年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程中途退学。博士(文学)。
主な著作に、『情動のエスノグラフィ──南タイの村で感じる*つながる*生きる』(京都大学学術出版会、2013年)、『アフェクトゥス──生の外側に触れる』(共編著、京都大学学術出版会、2020年)、Community Movements in Southeast Asia: An Anthropological Perspective of Assemblages(共編著、Silkworm Books、2022年)、Affectus: A Journey on the Outside of Life(共編著、Kyoto University Press and Trans Pacific Press、2024年)など。
西江 仁德(にしえ ひとなる)
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科研究員、京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系研究員
1976年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程単位取得退学、博士(理学)。
主な著作に、「〈新・動物記〉シリーズ」(共編、京都大学学術出版会、2021年~)、『わざの人類学』(共著、京都大学学術出版会、2021年)、『極限──人類社会の進化』(共著、京都大学学術出版会、2020年)、『出会いと別れ──「あいさつ」をめぐる相互行為論』(共著、ナカニシヤ出版、2021年)など。
花村 俊吉(はなむら しゅんきち)
京都大学アフリカ地域研究資料センター研究員
1980年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程研究指導認定退学、修士(理学)。ヒトの相対化を目指して非ヒト霊長類の社会を参与観察してきたほか、両者の関係や、フォトエスノグラフィーについても調査している。
主な著作に、『出会いと別れ──「あいさつ」をめぐる相互行為論』(共編著、ナカニシヤ出版、2021年)、「ルビー一家の闘病記──野生チンパンジーの「病い」の経験と病原体を介した「人間」との混淆」稲岡司編『病む・癒す(生態人類学は挑む SESSION 3)』(分担執筆、京都大学学術出版会、2021年)、「偶有性にたゆたうチンパンジー──長距離音声を介した相互行為と共在のあり方」木村大治・中村美知夫・高梨克也編『インタラクションの境界と接続──サル・人・会話研究から』(分担執筆、昭和堂、2010年)など。
船曳 建夫(ふなびき たけお)
東京大学大学院総合文化研究科名誉教授
1948年生まれ。ケンブリッジ大学大学院社会人類学、博士(Ph. D.)。人間の自然性と文化性の相互干渉、近代化の過程で起こる変化について文化人類学的研究を進める。
主な編著書に、『国民文化が生れる時』(リブロポート、1994年)、『「日本人論」再考』(講談社学術文庫、2003年)、LIVING FIELD(The University Museum・The University of Tokyo、2012年)など。
森下 翔(もりした しょう)
山梨県立大学地域人材養成センター特任助教
1987年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程単位取得退学。修士(人間・環境学)。科学技術の人類学を専門とする。
主な著作に、『アクターネットワーク理論入門』(共著、ナカニシヤ出版、2022年)、「「融合」としての認識=存在論──「非-自然主義的」な科学実践を構成する「観測データへの不信」と「ア・プリオリなデータ」の概念」『文化人類学』85巻1号(2020年)、「不可視の世界を畳み込む──固体地球物理学の実践における「観測」と「モデリング」」『文化人類学』78巻4号(2014年)など。
森光 由樹(もりみつ よしき)
兵庫県立大学自然・環境科学研究所准教授、兵庫県森林動物研究センター主任研究員
1967年生まれ。日本獣医生命科学大学博士課程修了、博士(獣医学)。主に獣医師の立場から野生動物の保全や管理に関係する研究を進める。
主な著作に、『ニホンザルの自然誌』(共著、東海大学出版会、2002年)、『動物たちの反乱』(共著、PHP研究所、2009年)、『コアカリ 野生動物学』(共著、文永堂出版、2015年)、『野生動物管理──理論と技術』増補版(共著、文永堂出版、2016年)、『霊長類学の百科事典』(共著、丸善出版、2023年)など。
足立 薫(あだち かおる)
京都産業大学現代社会学部准教授
1968年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程単位取得後退学、博士(理学)。西アフリカでオナガザル類の混群を研究したのち、香港のマカクザルと人間の軋轢を通してエスノプライマトロジー研究に従事している。
主な著作に「環境の生成と消滅─人新世とエスノプライマトロジー」伊藤詞子編『生態人類学は挑む』(たえる・きざすSession6)(分担執筆、京都大学学術出版会、2022年)、「極限としての〈いきおい〉──移動する群れの社会性」河合香吏編『極限──人間社会の進化』(分担執筆、京都大学学術出版会、2020年)。
五十嵐 由里子(いがらし ゆりこ)
日本大学松戸歯学部解剖学講座准教授
1963年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。ヒトの骨や歯の形態とそれらに影響を与える因子の関連を分析し、先史社会の生活を復元する研究を行っている。
主な著作に、“Mandibular premolar identification system based on a deep learning model.” Journal of Oral Biosciences, 64(3): 321–328(分担執筆、2022年、DOI 10.1016/j.job.2022.05.005)、“Pregnancy parturition scars in the preauricular area and the association with the total number of pregnancies and parturitions”, American Journal of Physical Anthropology, 171(2): 260–274(分担執筆、2020年、DOI 10.1002/ajpa.23961)、 “A New Method for Estimation of Adult Skeletal Age at Death From the Morphology of the Auricular Surface of the Ilium.”, American Journal of Physical Anthropology, 128(2): 324–339(2005年 DOI 10.1002/ajpa.20081)など。
伊藤 詞子(いとう のりこ)
一般社団法人AKARH代表、京都大学アフリカ地域研究資料センター特任研究員
1971年生まれ。京都大学大学理学研究科単位取得退学。博士(理学)。生息環境を含む野生チンパンジーの研究を専門とする。
主な著作に、『たえる・きざす(生態人類学は挑む SESSION 6)』(編著、京都大学学術出版会、2022年)、『極限──人類社会の進化』(分担執筆、京都大学学術出版会、2020年)など。
内堀 基光(うちぼり もとみつ)
一橋大学名誉教授・放送大学名誉教授
1948年生まれ。オーストラリア国立大学太平洋地域研究所Ph.D.(人類学)取得。ボルネオ島の諸民族社会、とくにマレーシア・サラワク州のイバン人の宗教儀礼、世界観・存在論の研究を進めてきた。
主な著作に、『死の人類学』(共著、弘文堂/講談社、1986年/2006年)、『森の食べ方』(東京大学出版会、1996年)、『資源人類学(全9巻)』(総合編集、弘文堂、2007年)など。
大村 敬一(おおむら けいいち)
放送大学教養学部教授
1966年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科考古学専攻博士後期課程修了、博士(文学)。主にカナダ・イヌイトを対象に、その生業や在来知、社会関係について文化人類学的研究を進める。
主な著作に、Self and Other Images of Hunter-Gatherers(編著、National Museum of Ethnology、2002年)、『カナダ・イヌイトの民族誌──日常的実践のダイナミクス』(大阪大学出版会、2013年)、『宇宙人類学の挑戦──人類の未来を問う』(共編著、昭和堂、2014年)、The World Multiple: The Quotidian Politics of Knowing and Generating Entangled Worlds(共編著、Routledge、2018年)、『「人新世」時代の文化人類学』(共編著、放送大学教育振興会、2020年)、『「人新世」時代の文化人類学の挑戦──よみがえる対話の力』(共編著、以文社、2023年)、『新・方法序説──人類社会の進化に迫る認識と方法』(共編著、京都大学学術出版会、2023年)、『フィールドワークと民族誌』(共編著、放送大学教育振興会、2024年)など。
春日 直樹(かすが なおき)
一橋大学名誉教授
1953年生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程中退、博士(人間科学)。オセアニアを中心に、経済・歴史・文化・思考様式について人類学的な研究をおこなう。サントリー学芸賞(2001年)、第16回日本文化人類学会賞(2021年)を受賞。
主な論文に、「呪術、隠喩、同型──21世紀の構造主義へ」『文化人類学』86(4): 527-542)(2022年)。編著に、『現実批判の人類学──新世代のエスノグラフィへ』(世界思想社、2011年)、『科学と文化をつなぐ──アナロジーという思考様式』(東京大学出版会、2016年)、『文化人類学のエッセンス──世界をみる/変える』(竹沢尚一郎との共編、有斐閣、2021年)。
河合 香吏(かわい かおり)*
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授
1961年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。主に東アフリカの牧畜社会を対象に、その生業や集団間関係について生態人類学的研究を進める。第1回日本ナイル・エチオピア学会高島賞(1995年)を受賞。
主な著作に、『関わる・認める(生態人類学は挑む SESSION 5)』(編著、京都大学学術出版会、2022年)、Extremes: The Evolution of Human Sociality(編著、Kyoto university press and Trans Pacific Press、2023年)、「敵と友のはざまで──ドドスと隣接民族トゥルカナとの関係」太田至・曽我亨編『遊牧の思想──人類学がみる激動のアフリカ』(分担執筆、昭和堂、2019年)など。
近藤 祉秋(こんどう しあき)
屋号:知犬ラボ
1986年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程中退。後に論文博士(文学)を取得。内陸アラスカ先住民の間で現地調査をおこない、人間と動物の関係などに関して研究を進めている。
著作に、『犬に話しかけてはいけない──内陸アラスカのマルチスピーシーズ民族誌』(慶應義塾大学出版会、2022年)。主な論文に、「先住民とデジタル化する社会──先住民研究の新しい枠組みに向けて」『国立民族学博物館研究報告』48巻1号(共著、2023年)、「危機の「予言」が生み出す異種集合体──内陸アラスカ先住民の過去回帰言説を事例として」『文化人類学』86巻3号(2021年)がある。
杉山 祐子(すぎやま ゆうこ)
弘前大学名誉教授
1958年生まれ。筑波大学大学院歴史人類学研究科単位取得退学。博士(地域研究)。ザンビア、タンザニアの地方農村を対象にジェンダーの視点から生態人類学的研究をおこなっている。
主な著作に『アフリカから農を問い直す──自然社会の農学を求めて』(共著、京都大学学術出版会、2023年)、『サバンナの林を豊かに生きる──母系社会の人類学』(京都大学学術出版会、2022年)、『地方都市とローカリティー』(共著、弘前大学出版会、2016年)など。
スプレイグ,デイビッド S.(David S. Sprague)
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所フェロー
1958年生まれ。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構を経て現職。エール大学人類学 Ph.D.
主な著作に、Primates Face to Face: Humans and Non-Human Primate Interconnections and Conservation(分担執筆、Cambridge University Press、2002年)、『サルの生涯、ヒトの生涯──人生計画の生物学』(京都大学学術出版会、2004年)、The Macaque Connection(分担執筆、Springer、2012年)、『極限──人類社会の進化』(分担執筆、京都大学学術出版会、2020年)など。
曽我 亨(そが とおる)
弘前大学人文社会科学部教授
1964年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。
主な著作に、「東アフリカのラクダ牧畜民」今村薫編『ラクダ、苛烈な自然で人と生きる』(分担執筆、風響社、2023年)、Between Ethnic Favoritism and Ethnic Hatred, In: Kaori Kawai ed., Extremes: The Evolution of Human Sociality(分担執筆、Kyoto University Press and Trans Pacific Press、2023)、『遊牧の思想──人類学がみる激動のアフリカ』(共編著、昭和堂、2019年)など。
竹ノ下 祐二(たけのした ゆうじ)
岡山理科大学理学部動物学科教授
1970年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。主に大型類人猿とニホンザルを中心に、ヒト以外の霊長類の社会関係や生活史について社会生態学的研究を進める。
主な著作に、『新・方法序説──人類社会の進化に迫る認識と方法』(共編著、京都大学学術出版会、2023年)、『セックスの人類学(シリーズ来るべき人類学)』(共編著、春風社、2009年)、『たえる・きざす(生態人類学は挑む SESSION 6)』(分担執筆、京都大学学術出版会、2022年)など。
田中 雅一(たなか まさかず)
国際ファッション専門職大学副学長、京都大学名誉教授
1955年生まれ。ロンドン大学経済政治学院(LSE)博士課程修了、Ph.D.(Anthropology)。専門は文化人類学、南アジア民族誌、ジェンダー・セクシュアリティ研究。日本文化人類学会賞(2017年)を受賞。
主な著作に、『癒やしとイヤラシ──エロスの文化人類学』(筑摩書房、2010年)、『誘惑する文化人類学』(世界思想社、2018年)、『フェティシズム研究(全3巻)』(編著、京都大学学術出版会、2009/2014/2017年)、『トラウマ研究(全2巻)』(共編著、京都大学学術出版会、2018/2019年)など。
谷口 晴香(たにぐち はるか)
公立鳥取環境大学環境学部・講師
京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。博士(理学)。専門は霊長類学。主にニホンザルを対象に環境がアカンボウの伴食関係や社会化の過程に与える影響について研究を進めている。
主な著作に、「ヤクシマザルの離乳期のアカンボウの伴食行動──アカンボウの集まりに着目して」『生態人類学会ニュースレター』28: 18-24(2022年)、“How the physical properties of food influence its selection by infant Japanese macaques inhabiting a snow‐covered area.”, American Journal of Primatology, 77: 285–295(2015年)、「積雪地域のニホンザルにおける採食品目の母子間不一致がもたらすアカンボウの採食行動」『生態人類学会ニュースレター』16: 2-4(2010年)など。
田村 大也(たむら まさや)
京都大学大学院理学研究科助教
1992年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。主に中央アフリカ西部に生息する野生ニシローランドゴリラを対象に、その社会や生態について行動生態学的研究を進める。
主な著作に、“Does kinship with the silverback matter?: Intragroup social relationships of immature wild western lowland gorillas after social upheaval.” Primates, 65: 397–410(共著、2024年)、“Protection service of a leading silverback male from external threats in wild western gorillas.”, Folia Primatologica, 95: 251–260(共著、2024年)、“Hand preference in unimanual and bimanual coordinated tasks in wild western lowland gorillas (Gorilla gorilla gorilla) feeding on African ginger (Zingiberaceae)”, American Journal of Physical Anthropology, 175: 531–545(2021年)。
外川 昌彦(とがわ まさひこ)
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授
慶應義塾大学大学院社会学研究科博士課程修了、博士(社会学)。専門は宗教人類学、南アジア研究。1992-97年にインドに留学、ベンガル農村社会で現地調査を行う。
主な著作に、An Abode of the Goddess: Kingship, Caste and Sacrificial Organization in a Bengal Village(Manohar Publishers、2006年)、『岡倉天心とインド──「アジアは一つ」が生まれるまで』(慶應義塾大学出版会、2023年)、Minorities and the State: Changing Social and Political Landscape of Bengal(共編著、SAGE Publications、2011年)、『アジアの社会参加仏教──政教関係の視座から』(共編著、北海道大学出版会、2015年)など。
床呂 郁哉(ところ いくや)
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授
専門は文化人類学、東南アジア地域研究。
主な著作に、『越境──スールー海域世界から』(岩波書店、1999年)、『東南アジアのイスラーム』(共著、東京外国語大学出版会、2012年)、『ものの人類学』及び『ものの人類学2』(共編著、京都大学学術出版会、2011/2019年)、『わざの人類学』(編著、京都大学学術出版会、2021年)など。
中川 尚史(なかがわ なおふみ)
京都大学大学院理学研究科教授
1960年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。国内では主に宮城県・金華山島と鹿児島県・屋久島のニホンザル、海外では主にガーナ・モレとカメルーン・カラマルエのパタスモンキーを対象に、社会・生態学的研究を進めてきた。日本霊長類学会前会長、ニホンザル管理協会代表理事。日本霊長類学会学術奨励賞受賞。
主な著作に、『霊長類学の百科事典』(編著、丸善書店、2023年)、『日本のサル──哺乳類学としてのニホンザル研究』(編著、東京大学出版会、2017年)、『〝ふつう〟のサルが語るヒトの起源と進化』(ぷねうま書房、2015年)、The Japanese Macaques(編著、Springer、2010年)など。
中村 美知夫(なかむら みちお)
京都大学大学院理学研究科准教授
京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。主にタンザニアの野生チンパンジーを対象に、その社会や文化についての研究を進める。
主な著作に、『「サル学」の系譜──人とチンパンジーの50年』(中公叢書、2015年)、『インタラクションの境界と接続──サル・人・会話研究から』(共編、昭和堂、2010年)、『チンパンジー──ことばのない彼らが語ること』(中公新書、2009年) など。
西井 凉子(にしい りょうこ)
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授
1959年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程中途退学。博士(文学)。
主な著作に、『情動のエスノグラフィ──南タイの村で感じる*つながる*生きる』(京都大学学術出版会、2013年)、『アフェクトゥス──生の外側に触れる』(共編著、京都大学学術出版会、2020年)、Community Movements in Southeast Asia: An Anthropological Perspective of Assemblages(共編著、Silkworm Books、2022年)、Affectus: A Journey on the Outside of Life(共編著、Kyoto University Press and Trans Pacific Press、2024年)など。
西江 仁德(にしえ ひとなる)
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科研究員、京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系研究員
1976年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程単位取得退学、博士(理学)。
主な著作に、「〈新・動物記〉シリーズ」(共編、京都大学学術出版会、2021年~)、『わざの人類学』(共著、京都大学学術出版会、2021年)、『極限──人類社会の進化』(共著、京都大学学術出版会、2020年)、『出会いと別れ──「あいさつ」をめぐる相互行為論』(共著、ナカニシヤ出版、2021年)など。
花村 俊吉(はなむら しゅんきち)
京都大学アフリカ地域研究資料センター研究員
1980年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程研究指導認定退学、修士(理学)。ヒトの相対化を目指して非ヒト霊長類の社会を参与観察してきたほか、両者の関係や、フォトエスノグラフィーについても調査している。
主な著作に、『出会いと別れ──「あいさつ」をめぐる相互行為論』(共編著、ナカニシヤ出版、2021年)、「ルビー一家の闘病記──野生チンパンジーの「病い」の経験と病原体を介した「人間」との混淆」稲岡司編『病む・癒す(生態人類学は挑む SESSION 3)』(分担執筆、京都大学学術出版会、2021年)、「偶有性にたゆたうチンパンジー──長距離音声を介した相互行為と共在のあり方」木村大治・中村美知夫・高梨克也編『インタラクションの境界と接続──サル・人・会話研究から』(分担執筆、昭和堂、2010年)など。
船曳 建夫(ふなびき たけお)
東京大学大学院総合文化研究科名誉教授
1948年生まれ。ケンブリッジ大学大学院社会人類学、博士(Ph. D.)。人間の自然性と文化性の相互干渉、近代化の過程で起こる変化について文化人類学的研究を進める。
主な編著書に、『国民文化が生れる時』(リブロポート、1994年)、『「日本人論」再考』(講談社学術文庫、2003年)、LIVING FIELD(The University Museum・The University of Tokyo、2012年)など。
森下 翔(もりした しょう)
山梨県立大学地域人材養成センター特任助教
1987年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程単位取得退学。修士(人間・環境学)。科学技術の人類学を専門とする。
主な著作に、『アクターネットワーク理論入門』(共著、ナカニシヤ出版、2022年)、「「融合」としての認識=存在論──「非-自然主義的」な科学実践を構成する「観測データへの不信」と「ア・プリオリなデータ」の概念」『文化人類学』85巻1号(2020年)、「不可視の世界を畳み込む──固体地球物理学の実践における「観測」と「モデリング」」『文化人類学』78巻4号(2014年)など。
森光 由樹(もりみつ よしき)
兵庫県立大学自然・環境科学研究所准教授、兵庫県森林動物研究センター主任研究員
1967年生まれ。日本獣医生命科学大学博士課程修了、博士(獣医学)。主に獣医師の立場から野生動物の保全や管理に関係する研究を進める。
主な著作に、『ニホンザルの自然誌』(共著、東海大学出版会、2002年)、『動物たちの反乱』(共著、PHP研究所、2009年)、『コアカリ 野生動物学』(共著、文永堂出版、2015年)、『野生動物管理──理論と技術』増補版(共著、文永堂出版、2016年)、『霊長類学の百科事典』(共著、丸善出版、2023年)など。
はしがき──人類社会の研究の新たな一歩のために
keynote 社会性について議論する前に
1 「社会性」とは何か、そしてその「起原」とは [中村 美知夫]
1 霊長類研究における「社会性」という語
2 「社会性」の辞書的な意味
3 専門用語としての「社会性」
4 霊長類学とその周辺分野における「社会性」
5 向社会性
6 なぜ「社会性」は頻繁に使われるようになったのか
7 「社会性」の共通理解は可能か
8 社会性の起原と進化の探究へ向けて
2 カミと孤独、また世捨て人──「延長された社会性」の進化史的意義についての覚書 [内堀 基光]
1 ドーキンス「延長された表現型」
2 社会性の議論における「延長」の位置づけ
3 社会性の二つの延長軸
4 延長された社会性の〈場としての「宗教」〉
5 延長された社会性の彼方へ
3 「車輪の再発明」は避けられるのか──生物学と社会科学の協働による社会進化論 [デイビッド・S・スプレイグ]
1 「利他主義」「互酬性」再考
2 ソシオバイオロジーの論理
3 古典に触れて
4 引用履歴
5 相利共生による社会の進化
6 利他行動と利益の交換に伴う時間差
7 協力関係の総合理論を求めて
PART I 社会性の「核」とは何か?
第1章 社会の糸、社会の神秘──伊谷純一郎以来の探究をめぐって [森下 翔]
1 方法をめぐる問い
2 社会の神秘
3 ダイアグラム的思考:経験の「根源」へ
4 根源
5 サルを見るようにヒトを見て、ヒトを見るようにサルを見る
6 近代への拡張
7 臨界
第2章 ただ近くにいる 同所性の根源的意味──何もしない父親の子育て [田村 大也]
1 多様で柔軟なヒトの父親の子育て
2 日本の霊長類学者が予見した父親
3 やはり子育てに献身的だったゴリラの父親
4 子育てに献身的ではないシルバーバック?
5 「父親の世話」の定義
6 「父親の世話」という行動の機能の曖昧さ
7 子供の近くにただいるだけという世話
8 ニダイの保護行動
9 子供を守るヒトの父親
10 近くにいることから始まる多様な父親役割
11 「ただ一緒にいる」ことの重要性を問い直す
第3章 人類の「宗教」史を捉えなおす──心的基盤と社会性の進化の観点から [外川 昌彦]
1 「チンパンジー性」を問う
2 世界の宗教史を描く
3 エリアーデとルロワ=グーラン
4 認知考古学から見た人類の心的基盤
5 宗教の「起源」論を問う
第4章 チンパンジーは死なず、ただ消え去るのみ──社会における死と「別れ」[西江 仁德]
1 他者の/他者としての死と社会性
2 チンパンジー死生学の興隆
3 「死ぬこと」と「死」
4 死と「別れ」
5 非在と社会
コラム(1) ヒトにとって「直立」が重要であること──直立二足歩行は「直立面」を保つための結果であり、派生的に起きた進化であること [船曳 建夫]
この試論の性格
1 「直立」と「二足歩行」を分けて考えること
2 「直立」と「二足歩行」のあいだの論理的先後関係は「直立」がまずあって、「直立二足歩行」はその結果であり、派生的であること
PART II 社会性が現れる場のエスノグラフィー
第5章 他者から/へのまなざしと集合的技術の生成──チテメネ開墾作業を支える社会性 [杉山 祐子]
1 二次的自然を生み出す集合的な技術と他者のまなざし
2 ベンバの土地と生業
3 ライフコースと樹上伐採、伐採技術の幅広い差異
4 樹上伐採
5 個人のわざが集合的な「技術」になるとき
第6章 離合集散しづらくなったらどうするか?──社会性からみる飲酒と移動 [近藤 祉秋]
1 社会性からみる飲酒と移動
2 ディチナニクの飲酒実践と社会性
3 移動実践とストレスの緩和
4 飲酒と移動にまつわる社会変化
5 アラスカ先住民の飲酒論再考
第7章 将来の共存を可能にする所作としての交尾妨害──「寛容性」が育むその発達と進化 [中川 尚史]
1 社会性の起原と進化を探る焦点と対象種
2 特異な行動─コドモオスによる交尾妨害
3 コドモオスによる交尾妨害の機能解明へのヒント
4 コドモオスによる交尾妨害の機能
5 ハラスメントの進化
6 平等原則への移行と寛容性
第8章 身体装飾からヒトの社会性の進化を考える──「拡張された社会性」へ向かって [床呂 郁哉]
1 身体装飾への関心
2 身体装飾に関する「認知革命」理論の批判的再検討
3 身体装飾と「正直なシグナル」理論
4 人間社会における身体装飾
5 身体変工と変形の実践
6 ケーススタディ
7 衣装と身体装飾の変容機能
8 拡張された社会性の創造=想像へ向かって
コラム(2) 自助努力を否定する社会 [曽我 亨]
お前を訴えてやる
自助努力を否定する社会
砂漠の保険
自助努力の誕生
他者にみずからを委ねる
自助努力をする者の末路
補論 1 縄文時代と弥生時代の人口構造 [五十嵐 由里子]
1 縄文時代と弥生時代を対象とし、人口構造に注目することの方法論的意義
2 資料と方法
3 推定された諸要素
4 人口構造の復元と社会性研究における意義
5 先史時代、非産業化社会を知ることの意味
PART III 「社会性の差分」を見つけ出すために
第9章 社会性のオントロギー──イヌイトの共食が拓く人類の社会性の起原と進化をめぐる問い [大村 敬一]
1 出発点
2 イヌイトの共食の現在
3 「共食」のエチケットを身につける
4 「共食」のエチケットに気づく
5 「共食」のエチケットを推定する
6 「共食」のエチケットの仮説を説明で検証する
7 社会性のオントロギー
第10章 ニホンザルのアカンボウの集まり──地域間比較の試み [谷口 晴香]
1 霊長類の離乳期における社会関係の発達
2 ニホンザルの北限と南限
3 ニホンザルの育児行動
4 離乳期のアカンボウの伴食関係
5 相互行為素を用いた分析
6 社会性の地域間比較
第11章 群れ生活における公共性と配慮 [竹ノ下 祐二]
1 ブロードキャストな社会行動
2 公共性の水準と公私の区別
3 公共性と配慮
4 ニシローランドゴリラの群れにおけるオス間のいさかい
5 今後の展開
第12章 「対称性」という観点で社会性の進化を考える [春日 直樹]
1 夫方集団と妻型集団の対称性
2 夫と妻についての対称性
3 写像と逆写像
4 互酬は対称性である
5 二者間関係を網羅する同型・対称性の増殖
6 結
コラム(3) フィールドワークにおける「変身」について [西井 凉子]
補論 2 霊長類研究における研究手法の発展──GPS・活動センサーからビックデータAI分析時代へ[森光 由樹]
1 GPSを用いたニホンザル研究の例
2 GPS・加速度計を用いたヒトの研究の例
3 GPS研究の課題
4 GPS・活動センサー研究の今後
PART IV 「ヒトの社会性の起原と進化」を越えて
第13章 世界の終わりと動物のエスノグラフィー[足立 薫]
1 動物のエスノグラフィーは可能か
2 エスノグラフィーのアポリア
3 霊長類学のエスノグラフィー
4 ハビチュエーション
5 調査者のハビチュエーション
6 エスノプライマトロジー(民族霊長類学)とエスノグラフィー
7 意味の生成という実践
8 何を知り、何を為すのか
第14章 サルを観察する人、人を観察するサル──大水無瀬島と情島におけるサルと人の異種間相互行為 [花村 俊吉]
1 動物の「視点」をめぐって
2 異種間相互行為を支える社会性
3 観察と語りのあわいで
4 他種生物とともにある社会性
第15章 モンキーからキンキーへ──セクシュアリティから考える社会性の出現 [田中 雅一]
1 人間のセクシュアリティ
2 女性における二つのセクシュアリティとペアボンド
3 月経周期の同期と女性の団結
4 月経の模倣と男性支配
5 新たな社会性へ
第16章 開かれた社会性へ──あるいは人間中心主義と擬人化をめぐって [伊藤 詞子]
1 社会性について考えるものの社会性が問われている
2 ホンモノ×マガイノモノ
3 「私が」が薄まる場所、あるいはどこまでも異なっていることとどこまでも似ていることの共立
4 サルする×ヒトする:私がサルを覚えるのかサルが私に名乗るのか
5 部分と全体
あとがき
索引
著者紹介
keynote 社会性について議論する前に
1 「社会性」とは何か、そしてその「起原」とは [中村 美知夫]
1 霊長類研究における「社会性」という語
2 「社会性」の辞書的な意味
3 専門用語としての「社会性」
4 霊長類学とその周辺分野における「社会性」
5 向社会性
6 なぜ「社会性」は頻繁に使われるようになったのか
7 「社会性」の共通理解は可能か
8 社会性の起原と進化の探究へ向けて
2 カミと孤独、また世捨て人──「延長された社会性」の進化史的意義についての覚書 [内堀 基光]
1 ドーキンス「延長された表現型」
2 社会性の議論における「延長」の位置づけ
3 社会性の二つの延長軸
4 延長された社会性の〈場としての「宗教」〉
5 延長された社会性の彼方へ
3 「車輪の再発明」は避けられるのか──生物学と社会科学の協働による社会進化論 [デイビッド・S・スプレイグ]
1 「利他主義」「互酬性」再考
2 ソシオバイオロジーの論理
3 古典に触れて
4 引用履歴
5 相利共生による社会の進化
6 利他行動と利益の交換に伴う時間差
7 協力関係の総合理論を求めて
PART I 社会性の「核」とは何か?
第1章 社会の糸、社会の神秘──伊谷純一郎以来の探究をめぐって [森下 翔]
1 方法をめぐる問い
2 社会の神秘
3 ダイアグラム的思考:経験の「根源」へ
4 根源
5 サルを見るようにヒトを見て、ヒトを見るようにサルを見る
6 近代への拡張
7 臨界
第2章 ただ近くにいる 同所性の根源的意味──何もしない父親の子育て [田村 大也]
1 多様で柔軟なヒトの父親の子育て
2 日本の霊長類学者が予見した父親
3 やはり子育てに献身的だったゴリラの父親
4 子育てに献身的ではないシルバーバック?
5 「父親の世話」の定義
6 「父親の世話」という行動の機能の曖昧さ
7 子供の近くにただいるだけという世話
8 ニダイの保護行動
9 子供を守るヒトの父親
10 近くにいることから始まる多様な父親役割
11 「ただ一緒にいる」ことの重要性を問い直す
第3章 人類の「宗教」史を捉えなおす──心的基盤と社会性の進化の観点から [外川 昌彦]
1 「チンパンジー性」を問う
2 世界の宗教史を描く
3 エリアーデとルロワ=グーラン
4 認知考古学から見た人類の心的基盤
5 宗教の「起源」論を問う
第4章 チンパンジーは死なず、ただ消え去るのみ──社会における死と「別れ」[西江 仁德]
1 他者の/他者としての死と社会性
2 チンパンジー死生学の興隆
3 「死ぬこと」と「死」
4 死と「別れ」
5 非在と社会
コラム(1) ヒトにとって「直立」が重要であること──直立二足歩行は「直立面」を保つための結果であり、派生的に起きた進化であること [船曳 建夫]
この試論の性格
1 「直立」と「二足歩行」を分けて考えること
2 「直立」と「二足歩行」のあいだの論理的先後関係は「直立」がまずあって、「直立二足歩行」はその結果であり、派生的であること
PART II 社会性が現れる場のエスノグラフィー
第5章 他者から/へのまなざしと集合的技術の生成──チテメネ開墾作業を支える社会性 [杉山 祐子]
1 二次的自然を生み出す集合的な技術と他者のまなざし
2 ベンバの土地と生業
3 ライフコースと樹上伐採、伐採技術の幅広い差異
4 樹上伐採
5 個人のわざが集合的な「技術」になるとき
第6章 離合集散しづらくなったらどうするか?──社会性からみる飲酒と移動 [近藤 祉秋]
1 社会性からみる飲酒と移動
2 ディチナニクの飲酒実践と社会性
3 移動実践とストレスの緩和
4 飲酒と移動にまつわる社会変化
5 アラスカ先住民の飲酒論再考
第7章 将来の共存を可能にする所作としての交尾妨害──「寛容性」が育むその発達と進化 [中川 尚史]
1 社会性の起原と進化を探る焦点と対象種
2 特異な行動─コドモオスによる交尾妨害
3 コドモオスによる交尾妨害の機能解明へのヒント
4 コドモオスによる交尾妨害の機能
5 ハラスメントの進化
6 平等原則への移行と寛容性
第8章 身体装飾からヒトの社会性の進化を考える──「拡張された社会性」へ向かって [床呂 郁哉]
1 身体装飾への関心
2 身体装飾に関する「認知革命」理論の批判的再検討
3 身体装飾と「正直なシグナル」理論
4 人間社会における身体装飾
5 身体変工と変形の実践
6 ケーススタディ
7 衣装と身体装飾の変容機能
8 拡張された社会性の創造=想像へ向かって
コラム(2) 自助努力を否定する社会 [曽我 亨]
お前を訴えてやる
自助努力を否定する社会
砂漠の保険
自助努力の誕生
他者にみずからを委ねる
自助努力をする者の末路
補論 1 縄文時代と弥生時代の人口構造 [五十嵐 由里子]
1 縄文時代と弥生時代を対象とし、人口構造に注目することの方法論的意義
2 資料と方法
3 推定された諸要素
4 人口構造の復元と社会性研究における意義
5 先史時代、非産業化社会を知ることの意味
PART III 「社会性の差分」を見つけ出すために
第9章 社会性のオントロギー──イヌイトの共食が拓く人類の社会性の起原と進化をめぐる問い [大村 敬一]
1 出発点
2 イヌイトの共食の現在
3 「共食」のエチケットを身につける
4 「共食」のエチケットに気づく
5 「共食」のエチケットを推定する
6 「共食」のエチケットの仮説を説明で検証する
7 社会性のオントロギー
第10章 ニホンザルのアカンボウの集まり──地域間比較の試み [谷口 晴香]
1 霊長類の離乳期における社会関係の発達
2 ニホンザルの北限と南限
3 ニホンザルの育児行動
4 離乳期のアカンボウの伴食関係
5 相互行為素を用いた分析
6 社会性の地域間比較
第11章 群れ生活における公共性と配慮 [竹ノ下 祐二]
1 ブロードキャストな社会行動
2 公共性の水準と公私の区別
3 公共性と配慮
4 ニシローランドゴリラの群れにおけるオス間のいさかい
5 今後の展開
第12章 「対称性」という観点で社会性の進化を考える [春日 直樹]
1 夫方集団と妻型集団の対称性
2 夫と妻についての対称性
3 写像と逆写像
4 互酬は対称性である
5 二者間関係を網羅する同型・対称性の増殖
6 結
コラム(3) フィールドワークにおける「変身」について [西井 凉子]
補論 2 霊長類研究における研究手法の発展──GPS・活動センサーからビックデータAI分析時代へ[森光 由樹]
1 GPSを用いたニホンザル研究の例
2 GPS・加速度計を用いたヒトの研究の例
3 GPS研究の課題
4 GPS・活動センサー研究の今後
PART IV 「ヒトの社会性の起原と進化」を越えて
第13章 世界の終わりと動物のエスノグラフィー[足立 薫]
1 動物のエスノグラフィーは可能か
2 エスノグラフィーのアポリア
3 霊長類学のエスノグラフィー
4 ハビチュエーション
5 調査者のハビチュエーション
6 エスノプライマトロジー(民族霊長類学)とエスノグラフィー
7 意味の生成という実践
8 何を知り、何を為すのか
第14章 サルを観察する人、人を観察するサル──大水無瀬島と情島におけるサルと人の異種間相互行為 [花村 俊吉]
1 動物の「視点」をめぐって
2 異種間相互行為を支える社会性
3 観察と語りのあわいで
4 他種生物とともにある社会性
第15章 モンキーからキンキーへ──セクシュアリティから考える社会性の出現 [田中 雅一]
1 人間のセクシュアリティ
2 女性における二つのセクシュアリティとペアボンド
3 月経周期の同期と女性の団結
4 月経の模倣と男性支配
5 新たな社会性へ
第16章 開かれた社会性へ──あるいは人間中心主義と擬人化をめぐって [伊藤 詞子]
1 社会性について考えるものの社会性が問われている
2 ホンモノ×マガイノモノ
3 「私が」が薄まる場所、あるいはどこまでも異なっていることとどこまでも似ていることの共立
4 サルする×ヒトする:私がサルを覚えるのかサルが私に名乗るのか
5 部分と全体
あとがき
索引
著者紹介