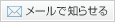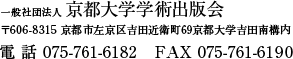ホーム > 書籍詳細ページ
本書は、日本の教育改革について日本側研究者が提示したの諸論点を、中国側の研究者が、中国の教育改革を踏まえ比較検討しながら論じる。教育改革をめぐる日中の研究者の相互「対話」によって、ともすれば一国単位で閉じられがちな教育研究を脱して、国際共同研究からそれぞれの国が教育をめぐる新たな自己認識を目ざす。
『東方』378号(2012年8月)、26-29頁、評者:諏訪哲郎氏
執筆者紹介(日本側) 執筆順
辻本 雅史(つじもと まさし)監修 序1
京都大学大学院教育学研究科・研究科長,教授
『近世教育思想史の研究—日本における「公教育」思想の源流—』(思文閣出版,1990年),『「学び」の復権』(角川書店,1999年),『知の伝達メディアの歴史研究—教育史像の再構築—』(編著,思文閣出版,2010年),『思想と教育のメディア史—近世日本の知の伝達—』(ぺりかん社,2011年)
南部 広孝(なんぶ ひろたか)編者 第1章 第8章 年表[中国] 翻訳〈序2 第3章 第5章 第7章 第9章 第11章 第13章 第15章〉
京都大学大学院教育学研究科・准教授
『中国高等教育独学試験制度の展開』(東信堂,2009年),『現代教育改革論—世界の動向と日本のゆくえ—』(江原武一と共編著,(財)放送大学教育振興会,2011年),「東アジア諸国における高大接続—大学入学者選抜方法の改革に焦点をあてて—」(『高等教育研究』14,2011年),「香港におけるトランスナショナル高等教育の展開」(『比較教育学研究』43,2011年)
鄭 谷心(Zheng Guxin)翻訳〈第2章〉
京都大学大学院教育学研究科・大学院生
「用語解説」(田中耕治編著『パフォーマンス評価—思考力・判断力・表現力を育む授業づくり—』ぎょうせい,2011年),「大正期の随意選題論に関する一考察」(『関西教育学会年報』35,2011年)
高見 茂(たかみ しげる) 第4章
京都大学大学院教育学研究科・教授
「学校と大学のガバナンス改革」(日本教育行政学会研究推進委員会編『地方財政危機とリスク管理』教育開発研究所,2009年),『教育法規スタートアップver. 2.0』(開沼太郎・宮村裕子との共編著,昭和堂,2012年)
杉本 均(すぎもと ひとし) 第4章
京都大学大学院教育学研究科・教授
『マレーシアにおける国際教育関係—教育へのグローバル・インパクト—』(東信堂,2005年),「トランスナショナル高等教育—新たな留学概念の登場—」(『比較教育学研究』43,2011年)
田中 耕治(たなか こうじ) 第6章 あとがき
京都大学大学院教育学研究科・教授
『時代を拓いた教師たち』Ⅰ・Ⅱ(編著,日本標準,2005年・2009年),『教育評価』(岩波書店,2008年。2011年,中国語版(高峡・田輝・項純訳,北京師範大学出版社)刊行)
西岡 加名恵(にしおか かなえ) 第6章
京都大学大学院教育学研究科・准教授
『教科と総合に活かすポートフォリオ評価法—新たな評価基準の創出に向けて—』(図書文化,2003年),『「逆向き設計」で確かな学力を保障する』(編著,明治図書,2008年)
赤沢 真世(あかざわ まさよ) 第6章
立命館大学スポーツ健康科学部・准教授
「英語科の学力と実践的コミュニケーション能力—表現の能力に注目して—」(田中耕治編著『新しい学力テストを読み解く』日本標準,2008年),「外国語活動 子どもの実態を踏まえ,伝え合うコミュニケーション場面を設定する」(田中耕治編著『小学校新指導要録改訂のポイント』日本標準,2010年)
渡邊 洋子(わたなべ ようこ) 第10章
京都大学大学院教育学研究科・准教授
『近代日本女子社会教育成立史—処女会の全国組織化と指導思想—』(明石書店,1997年),『生涯学習時代の成人教育学—学習者支援へのアドヴォカシー—』(明石書店,2002年)
吉田 正純(よしだ まさずみ) 第10章
京都大学大学院教育学研究科・助教
『生涯学習支援の理論と実践—教えることの現在—』(P.ジャーヴィス編著,渡邊洋子と監訳,明石書店,2011年),「多文化共生と『ローカル・ノレッジ』—京都における在日コリアン地域活動を事例に—」(『〈ローカルな知〉の可能性』,東洋館出版社,2008年)
八田 幸恵(はった さちえ) 第12章
福井大学教育地域科学部・講師
「カリキュラム研究と教師教育—アメリカにおけるPCK研究の展開—」(岩田康之・三石初雄編著『現代の教育改革と教師—これからの教師教育研究のために—』東京学芸大学出版会,2011年),「リー・ショーマンにおける教師の知識と学習過程に関する理論の展開」(『教育方法学研究』35,2010年)
中池 竜一(なかいけ りゅういち) 第14章
京都大学大学院教育学研究科・助教
「理科における『本質的な問い』とパフォーマンス課題」(『指導と評価』58—3(No. 687),2012年),「認知科学の入門的授業に供するWeb-basedプロダクションシステムの開発」(三輪和久らと共著,『人工知能学会論文誌』26,2011年)
楠見 孝(くすみ たかし) 第14章
京都大学大学院教育学研究科・教授
『批判的思考力を育む—学士力と社会人基礎力の基盤形成—』(子安増生・道田泰司と共編著,有斐閣,2011年),『実践知—エキスパートの知性—』(金井壽宏と共編著,有斐閣,2012年)
森(柴本) 枝美(もり(しばもと) えみ) 第16章
奈良教育大学・准教授
「庄司和晃と仮説実験授業—科学教育における討論の可能性」(田中耕治編著『時代を拓いた教師たち』日本標準,2005年),「理科の学力と科学的リテラシー—遺伝にかかわる問題に注目して—」(田中耕治編著『新しい学力テストを読み解く』日本標準,2008年)
楠山 研(くすやま けん) 第18章 翻訳〈第17章〉
長崎大学大学院教育学研究科・准教授
『現代中国初中等教育の多様化と制度改革』(東信堂,2010年),「中国(北京)—新しい観点による教育実践を率先—」(橋本健夫・鶴岡義彦・川上昭吾編著『現代理科教育改革の特色とその具現化』東洋館出版社,2010年)
ベー・シュウキー(べー しゅうきー) 第18章
長崎大学大学教育機能開発センター等・非常勤講師
「日方視点:以英語教育為中心」(楠山研と共著,田慧生・田中耕治主編『21世紀的日本教育改革—中日学者的視点—』教育科学出版社,2009年),「台湾における小学校英語教員の養成—その現状と課題—」(『京都大学大学院教育学研究科紀要』53,2007年)
森本 洋介(もりもと ようすけ) 年表[日本]
京都大学大学院教育学研究科・研究員
“Creating Media Literacy in Japan: Initiatives for New Citizenship”(Drotner, K., Jensen, H. S. and Schroder, K. C (eds.), Informal Learning and Digital Media, Cambridge Scholars Publishing,2008年),「メディア・リテラシー教育を通じた『批判的』な思考力育成に関する考察—トロント地区X高校における授業観察から—」(『カナダ教育研究』8,2010年)
執筆者紹介(中国側) 執筆順
袁 振国(Yuan Zhenguo)監修 序2 第2章
中国教育科学研究院・院長,教授
『教育政策学』(江蘇教育出版社,1996年。2010年に台湾高等教育出版社より刊行),『縮小差距—中国教育政策重大命題—』(人民教育出版社,2006年),『教育新理論』(改訂版)(教育科学出版社,2009年),『当代教育学』(第4版)(主編,教育科学出版社,2010年)
田 輝(Tian Hui) 第3章
中国教育科学研究院国際比較教育研究中心・副研究員
「日本“全納教育”政策的確立—従“特殊教育”走向“特別支援教育”」(『中国民族教育』2011—6,2011年),「終身学習背景下的literacy」(『中国成人教育』2009—5,2009年)
高 峡(Gao Xia)編者 第5章
中国教育科学研究院課程教学研究中心・研究員
『活動課程的理論与実践』(康健・叢立新・高洪源と共著,上海科技教育出版社,1997年),『新課程新教学的探索』(主編,北京師範大学出版社,2003年),『小学社会課研究与実験』(北京師範大学,2004年),『〈品徳与社会〉教学基本概念解読』(主編,教育科学出版社,2007年)
項 純(Xiang Chun) 第5章
中国教育科学研究院課程教学研究中心・助理研究員
「『素質教育』をめざす中国の教育評価改革—政府公文書の検討を通して—」(『教育目標・評価学会紀要』16,2006年),「中国における素質教育をめざす基礎教育改革をめぐる論争」(『京都大学大学院教育学研究科紀要』56,2010年)
方 勇(Fang Yong) 第7章
中国教育科学研究院国際比較教育研究中心・副研究員
『科学計量学的方法論研究』(西南師範大学出版社,2006年),“Lattices in citation networks: An investigation into the structure of citation graphs”(Scientometrics, Vol. 50, No. 2, 2001)
張 偉(Zhang Wei) 第7章
国家教育発展研究中心・助理研究員
「我国高等教育中間組織発展現状与趨勢」(『北京教育』2007—9,2007年),「日本的国立大学法人化」(国家教育発展研究中心編著『2006年中国教育緑皮書』教育科学出版社,2006年)
李 尚波(Li Shangbo) 第7章
桜美林大学法学・政治学系・准教授
『女子大学生の就職意識と行動』(御茶の水書房,2006年),「雇用均等時代と大卒女性の雇用に関する研究」(独立行政法人労働政策・研修機構『日本労働研究雑誌』NO. 615,2011年)
孫 誠(Sun Cheng) 第9章
中国教育科学研究院高等教育研究中心・研究員
『人力資源与西部開発』(経済科学出版社,2007年),「関注職成学校在農村労働力轉移培訓中的作用」(『教育与職業』2007—6,2007年)
王 暁燕(Wang Xiaoyan) 第11章
国家教育発展研究中心・副研究員
『市場化の中の教師達』(櫂歌書房,2008年),「中国における改革開放以降の教師教育改革について—ここ30年の変革と今後—」(望田研吾編『21世紀の教育改革と教育交流』東信堂,2010年)
張 傑夫(Zhang Jiefu) 第13章
中国教育科学研究院基礎教育研究中心・副研究員
「『賈君鵬事件』透射出網絡時代教育的使命」(『中国徳育』2009—12,2009年)「以信息化促進西部義務教育薄弱校跨越式発展」『中国徳育』(2010—11,2010年)
尚 大鵬(Shang Dapeng) 第15章
中国教育科学研究院体育衛生芸術教育研究中心・副研究員
「清朝末期における体操科教員養成機関の成立—日本体育会体操学校卒業生鄧頴詩の役割—」(『アジア教育史研究』11,2002年),「明治後期における中国人留学生に対する軍事教育」(広島東洋史学会研究会『広島東洋史学報』7,2002年)
李 協京(Li Xiejing) 第17章
中国教育科学研究院国際比較教育研究中心・副研究員
「新自由主義和新保守主義路線指導下的日本教育改革」(『教育研究』2005—8,2005年),「明治初期的『学制』与日本的近代義務教育」(『教育史研究』2009—6,2009年)
辻本 雅史(つじもと まさし)監修 序1
京都大学大学院教育学研究科・研究科長,教授
『近世教育思想史の研究—日本における「公教育」思想の源流—』(思文閣出版,1990年),『「学び」の復権』(角川書店,1999年),『知の伝達メディアの歴史研究—教育史像の再構築—』(編著,思文閣出版,2010年),『思想と教育のメディア史—近世日本の知の伝達—』(ぺりかん社,2011年)
南部 広孝(なんぶ ひろたか)編者 第1章 第8章 年表[中国] 翻訳〈序2 第3章 第5章 第7章 第9章 第11章 第13章 第15章〉
京都大学大学院教育学研究科・准教授
『中国高等教育独学試験制度の展開』(東信堂,2009年),『現代教育改革論—世界の動向と日本のゆくえ—』(江原武一と共編著,(財)放送大学教育振興会,2011年),「東アジア諸国における高大接続—大学入学者選抜方法の改革に焦点をあてて—」(『高等教育研究』14,2011年),「香港におけるトランスナショナル高等教育の展開」(『比較教育学研究』43,2011年)
鄭 谷心(Zheng Guxin)翻訳〈第2章〉
京都大学大学院教育学研究科・大学院生
「用語解説」(田中耕治編著『パフォーマンス評価—思考力・判断力・表現力を育む授業づくり—』ぎょうせい,2011年),「大正期の随意選題論に関する一考察」(『関西教育学会年報』35,2011年)
高見 茂(たかみ しげる) 第4章
京都大学大学院教育学研究科・教授
「学校と大学のガバナンス改革」(日本教育行政学会研究推進委員会編『地方財政危機とリスク管理』教育開発研究所,2009年),『教育法規スタートアップver. 2.0』(開沼太郎・宮村裕子との共編著,昭和堂,2012年)
杉本 均(すぎもと ひとし) 第4章
京都大学大学院教育学研究科・教授
『マレーシアにおける国際教育関係—教育へのグローバル・インパクト—』(東信堂,2005年),「トランスナショナル高等教育—新たな留学概念の登場—」(『比較教育学研究』43,2011年)
田中 耕治(たなか こうじ) 第6章 あとがき
京都大学大学院教育学研究科・教授
『時代を拓いた教師たち』Ⅰ・Ⅱ(編著,日本標準,2005年・2009年),『教育評価』(岩波書店,2008年。2011年,中国語版(高峡・田輝・項純訳,北京師範大学出版社)刊行)
西岡 加名恵(にしおか かなえ) 第6章
京都大学大学院教育学研究科・准教授
『教科と総合に活かすポートフォリオ評価法—新たな評価基準の創出に向けて—』(図書文化,2003年),『「逆向き設計」で確かな学力を保障する』(編著,明治図書,2008年)
赤沢 真世(あかざわ まさよ) 第6章
立命館大学スポーツ健康科学部・准教授
「英語科の学力と実践的コミュニケーション能力—表現の能力に注目して—」(田中耕治編著『新しい学力テストを読み解く』日本標準,2008年),「外国語活動 子どもの実態を踏まえ,伝え合うコミュニケーション場面を設定する」(田中耕治編著『小学校新指導要録改訂のポイント』日本標準,2010年)
渡邊 洋子(わたなべ ようこ) 第10章
京都大学大学院教育学研究科・准教授
『近代日本女子社会教育成立史—処女会の全国組織化と指導思想—』(明石書店,1997年),『生涯学習時代の成人教育学—学習者支援へのアドヴォカシー—』(明石書店,2002年)
吉田 正純(よしだ まさずみ) 第10章
京都大学大学院教育学研究科・助教
『生涯学習支援の理論と実践—教えることの現在—』(P.ジャーヴィス編著,渡邊洋子と監訳,明石書店,2011年),「多文化共生と『ローカル・ノレッジ』—京都における在日コリアン地域活動を事例に—」(『〈ローカルな知〉の可能性』,東洋館出版社,2008年)
八田 幸恵(はった さちえ) 第12章
福井大学教育地域科学部・講師
「カリキュラム研究と教師教育—アメリカにおけるPCK研究の展開—」(岩田康之・三石初雄編著『現代の教育改革と教師—これからの教師教育研究のために—』東京学芸大学出版会,2011年),「リー・ショーマンにおける教師の知識と学習過程に関する理論の展開」(『教育方法学研究』35,2010年)
中池 竜一(なかいけ りゅういち) 第14章
京都大学大学院教育学研究科・助教
「理科における『本質的な問い』とパフォーマンス課題」(『指導と評価』58—3(No. 687),2012年),「認知科学の入門的授業に供するWeb-basedプロダクションシステムの開発」(三輪和久らと共著,『人工知能学会論文誌』26,2011年)
楠見 孝(くすみ たかし) 第14章
京都大学大学院教育学研究科・教授
『批判的思考力を育む—学士力と社会人基礎力の基盤形成—』(子安増生・道田泰司と共編著,有斐閣,2011年),『実践知—エキスパートの知性—』(金井壽宏と共編著,有斐閣,2012年)
森(柴本) 枝美(もり(しばもと) えみ) 第16章
奈良教育大学・准教授
「庄司和晃と仮説実験授業—科学教育における討論の可能性」(田中耕治編著『時代を拓いた教師たち』日本標準,2005年),「理科の学力と科学的リテラシー—遺伝にかかわる問題に注目して—」(田中耕治編著『新しい学力テストを読み解く』日本標準,2008年)
楠山 研(くすやま けん) 第18章 翻訳〈第17章〉
長崎大学大学院教育学研究科・准教授
『現代中国初中等教育の多様化と制度改革』(東信堂,2010年),「中国(北京)—新しい観点による教育実践を率先—」(橋本健夫・鶴岡義彦・川上昭吾編著『現代理科教育改革の特色とその具現化』東洋館出版社,2010年)
ベー・シュウキー(べー しゅうきー) 第18章
長崎大学大学教育機能開発センター等・非常勤講師
「日方視点:以英語教育為中心」(楠山研と共著,田慧生・田中耕治主編『21世紀的日本教育改革—中日学者的視点—』教育科学出版社,2009年),「台湾における小学校英語教員の養成—その現状と課題—」(『京都大学大学院教育学研究科紀要』53,2007年)
森本 洋介(もりもと ようすけ) 年表[日本]
京都大学大学院教育学研究科・研究員
“Creating Media Literacy in Japan: Initiatives for New Citizenship”(Drotner, K., Jensen, H. S. and Schroder, K. C (eds.), Informal Learning and Digital Media, Cambridge Scholars Publishing,2008年),「メディア・リテラシー教育を通じた『批判的』な思考力育成に関する考察—トロント地区X高校における授業観察から—」(『カナダ教育研究』8,2010年)
執筆者紹介(中国側) 執筆順
袁 振国(Yuan Zhenguo)監修 序2 第2章
中国教育科学研究院・院長,教授
『教育政策学』(江蘇教育出版社,1996年。2010年に台湾高等教育出版社より刊行),『縮小差距—中国教育政策重大命題—』(人民教育出版社,2006年),『教育新理論』(改訂版)(教育科学出版社,2009年),『当代教育学』(第4版)(主編,教育科学出版社,2010年)
田 輝(Tian Hui) 第3章
中国教育科学研究院国際比較教育研究中心・副研究員
「日本“全納教育”政策的確立—従“特殊教育”走向“特別支援教育”」(『中国民族教育』2011—6,2011年),「終身学習背景下的literacy」(『中国成人教育』2009—5,2009年)
高 峡(Gao Xia)編者 第5章
中国教育科学研究院課程教学研究中心・研究員
『活動課程的理論与実践』(康健・叢立新・高洪源と共著,上海科技教育出版社,1997年),『新課程新教学的探索』(主編,北京師範大学出版社,2003年),『小学社会課研究与実験』(北京師範大学,2004年),『〈品徳与社会〉教学基本概念解読』(主編,教育科学出版社,2007年)
項 純(Xiang Chun) 第5章
中国教育科学研究院課程教学研究中心・助理研究員
「『素質教育』をめざす中国の教育評価改革—政府公文書の検討を通して—」(『教育目標・評価学会紀要』16,2006年),「中国における素質教育をめざす基礎教育改革をめぐる論争」(『京都大学大学院教育学研究科紀要』56,2010年)
方 勇(Fang Yong) 第7章
中国教育科学研究院国際比較教育研究中心・副研究員
『科学計量学的方法論研究』(西南師範大学出版社,2006年),“Lattices in citation networks: An investigation into the structure of citation graphs”(Scientometrics, Vol. 50, No. 2, 2001)
張 偉(Zhang Wei) 第7章
国家教育発展研究中心・助理研究員
「我国高等教育中間組織発展現状与趨勢」(『北京教育』2007—9,2007年),「日本的国立大学法人化」(国家教育発展研究中心編著『2006年中国教育緑皮書』教育科学出版社,2006年)
李 尚波(Li Shangbo) 第7章
桜美林大学法学・政治学系・准教授
『女子大学生の就職意識と行動』(御茶の水書房,2006年),「雇用均等時代と大卒女性の雇用に関する研究」(独立行政法人労働政策・研修機構『日本労働研究雑誌』NO. 615,2011年)
孫 誠(Sun Cheng) 第9章
中国教育科学研究院高等教育研究中心・研究員
『人力資源与西部開発』(経済科学出版社,2007年),「関注職成学校在農村労働力轉移培訓中的作用」(『教育与職業』2007—6,2007年)
王 暁燕(Wang Xiaoyan) 第11章
国家教育発展研究中心・副研究員
『市場化の中の教師達』(櫂歌書房,2008年),「中国における改革開放以降の教師教育改革について—ここ30年の変革と今後—」(望田研吾編『21世紀の教育改革と教育交流』東信堂,2010年)
張 傑夫(Zhang Jiefu) 第13章
中国教育科学研究院基礎教育研究中心・副研究員
「『賈君鵬事件』透射出網絡時代教育的使命」(『中国徳育』2009—12,2009年)「以信息化促進西部義務教育薄弱校跨越式発展」『中国徳育』(2010—11,2010年)
尚 大鵬(Shang Dapeng) 第15章
中国教育科学研究院体育衛生芸術教育研究中心・副研究員
「清朝末期における体操科教員養成機関の成立—日本体育会体操学校卒業生鄧頴詩の役割—」(『アジア教育史研究』11,2002年),「明治後期における中国人留学生に対する軍事教育」(広島東洋史学会研究会『広島東洋史学報』7,2002年)
李 協京(Li Xiejing) 第17章
中国教育科学研究院国際比較教育研究中心・副研究員
「新自由主義和新保守主義路線指導下的日本教育改革」(『教育研究』2005—8,2005年),「明治初期的『学制』与日本的近代義務教育」(『教育史研究』2009—6,2009年)
序1
新たな教育研究の創造をめざして
京都大学大学院教育学研究科 研究科長 辻本 雅史
序2
深く対話し,手を携えてともに前へ進もう
中国教育科学研究院 院長 袁 振国
総 論
第1章 日本教育を見る中国の視点 [南部広孝]
1.本書の目的と構成
2.視点の背景としての中国教育
3.中国の教育制度
第2章 中国の教育改革構想—これからの十年 [袁 振国]
1.改革は「教育計画要綱」の主旋律
2.現在わが国が教育体制の改革を深化させる切迫性
3.教育体制改革の内容と目標
4.教育体制改革を推進するルートと方法
Ⅰ.政策・法規
第3章 方針・政策とその推進施策 [田 輝]
1.改革の方針
2.改革の促進措置
3.「教育基本法」の改正
4.今後10年の教育改革
5.改革の示唆
第4章 教育政策とその基本理念 [杉本 均・高見 茂]
1.21世紀教育新生プラン
2.「教育基本法」の改正
3.まとめ
Ⅱ.基礎教育
第5章 生きる力の育成を目標とする課程改革 [高 峡・項 純]
1.21世紀の基礎教育改革の背景と出発点
2.21世紀における基礎教育課程改革の模索過程
3.比較,示唆と考察
4.おわりに
第6章 日本における教育課程をめぐる課題と展望 [赤沢真世・西岡加名恵・田中耕治]
1.教育課程改革における「振り子」現象の回避
2.学校における教育課程改善の可能性
3.道徳教育への提案
4.まとめ
Ⅲ.高等教育
第7章 制度保障と国際化の進展 [方 勇・張 偉・李 尚波]
1.21世紀日本における高等教育改革の背景
2.国立大学法人化—制度創造の試み
3.第三者評価制度の確立—質の監督の模索
4.「21世紀COEプログラム」—高水準の研究拠点を作り上げる新たな措置
5.高等教育の国際化に向けた歩み
第8章 質向上をめざす高等教育改革の展開 [南部広孝]
1.国立大学法人化の枠組みと展開
2.大学評価活動の進展
3.国際化促進に向けた施策
4.まとめ—中国からの視点に対する応答
Ⅳ.生涯学習
第9章 日本における生涯学習社会構築の経験と示唆 [孫 誠]
1.日本における生涯学習社会構築の時代背景
2.社会教育の生涯学習への転換
3.生涯学習社会を構築するための措置
4.21世紀日本の生涯学習社会構築推進の成果
5.経験と示唆
第10章 戦後社会教育をめぐる論点と生涯学習の現代的課題 [渡邊洋子・吉田正純]
1.戦後社会教育・生涯学習の全体構図をめぐる日中研究者の論点
2.生涯学習社会の構築と「公共性」の行方
3.生涯学習の現代的課題—震災・復興をめぐる実践的課題とネットワークの可能性
4.日中生涯学習の比較研究に向けて
Ⅴ.教師教育
第11章 制度改革を通じた教員の専門性発展の促進 [王 暁燕]
1.21世紀日本の教師教育が直面する課題と挑戦
2.21世紀の日本の教師教育が現在進めている改革
3.日本の教師教育改革が今後長期にわたって注目する政策課題
4.考察と検討,中国への示唆と参考
第12章 21世紀の日本における教師教育改革について [八田幸恵]
1.専門職としての教師の力量形成という課題と改革の方向性
2.21世紀の日本において推進されている教師教育改革
3.中国の視点を踏まえて
4.おわりに
Ⅵ.情報技術教育
第13章 IT立国戦略における教育情報化 [張 傑夫]
1.教育情報化の背景と目標
2.教育情報化の方策と措置
3.教育情報化の現状
4.示唆
5.困惑と課題
第14章 情報教育・ICT活用・IT人材育成 [中池竜一・楠見 孝]
1.政府から民間への主役移行,新たな展開へ
2.小学校・中学校における情報教育
3.高校における情報教育
4.高等教育機関におけるIT人材育成
5.中国側の意見を受けて
Ⅶ.体育・保健体育・食育
第15章 体育を中心とした現状と動向の分析 [尚 大鵬]
1.日本の児童生徒の体力・健康の現状とその増進措置
2.日本の学校の「食育」制度
3.体育科における想定外傷害事故の処理方法
4.日本の学校の保健体育学習指導要領の改訂
第16章 子どもたちの健康と安全を守る—学校保健を中心に [森(柴本)枝美]
1.学校保健について
2.学校保健の歴史
3.現代日本における学校保健
4.おわりに
Ⅷ.国際理解教育
第17章 コミュニケーション能力と国際理解教育を中心に [李 協京]
1.日本における国際理解教育の概要
2.学習指導要領からみる日本の小・中・高等学校における国際理解教育
3.学校を主体とした日本における国際理解教育の実践
4.日本の小・中・高等学校における国際理解教育の経験と示唆
第18章 日本における国際理解教育と英語教育の関係—小学校外国語活動を手がかりに
[楠山 研・ベー シュウキー]
1.日本の外国語教育と国際理解教育
2.日中の小学校の英語教育における国際理解の対象
3.日本における小学校外国語活動の導入経緯
4.日本の小学校外国語活動が抱える課題
5.まとめ—中国側原稿と合わせて
年 表
あとがき
索 引
新たな教育研究の創造をめざして
京都大学大学院教育学研究科 研究科長 辻本 雅史
序2
深く対話し,手を携えてともに前へ進もう
中国教育科学研究院 院長 袁 振国
総 論
第1章 日本教育を見る中国の視点 [南部広孝]
1.本書の目的と構成
2.視点の背景としての中国教育
3.中国の教育制度
第2章 中国の教育改革構想—これからの十年 [袁 振国]
1.改革は「教育計画要綱」の主旋律
2.現在わが国が教育体制の改革を深化させる切迫性
3.教育体制改革の内容と目標
4.教育体制改革を推進するルートと方法
Ⅰ.政策・法規
第3章 方針・政策とその推進施策 [田 輝]
1.改革の方針
2.改革の促進措置
3.「教育基本法」の改正
4.今後10年の教育改革
5.改革の示唆
第4章 教育政策とその基本理念 [杉本 均・高見 茂]
1.21世紀教育新生プラン
2.「教育基本法」の改正
3.まとめ
Ⅱ.基礎教育
第5章 生きる力の育成を目標とする課程改革 [高 峡・項 純]
1.21世紀の基礎教育改革の背景と出発点
2.21世紀における基礎教育課程改革の模索過程
3.比較,示唆と考察
4.おわりに
第6章 日本における教育課程をめぐる課題と展望 [赤沢真世・西岡加名恵・田中耕治]
1.教育課程改革における「振り子」現象の回避
2.学校における教育課程改善の可能性
3.道徳教育への提案
4.まとめ
Ⅲ.高等教育
第7章 制度保障と国際化の進展 [方 勇・張 偉・李 尚波]
1.21世紀日本における高等教育改革の背景
2.国立大学法人化—制度創造の試み
3.第三者評価制度の確立—質の監督の模索
4.「21世紀COEプログラム」—高水準の研究拠点を作り上げる新たな措置
5.高等教育の国際化に向けた歩み
第8章 質向上をめざす高等教育改革の展開 [南部広孝]
1.国立大学法人化の枠組みと展開
2.大学評価活動の進展
3.国際化促進に向けた施策
4.まとめ—中国からの視点に対する応答
Ⅳ.生涯学習
第9章 日本における生涯学習社会構築の経験と示唆 [孫 誠]
1.日本における生涯学習社会構築の時代背景
2.社会教育の生涯学習への転換
3.生涯学習社会を構築するための措置
4.21世紀日本の生涯学習社会構築推進の成果
5.経験と示唆
第10章 戦後社会教育をめぐる論点と生涯学習の現代的課題 [渡邊洋子・吉田正純]
1.戦後社会教育・生涯学習の全体構図をめぐる日中研究者の論点
2.生涯学習社会の構築と「公共性」の行方
3.生涯学習の現代的課題—震災・復興をめぐる実践的課題とネットワークの可能性
4.日中生涯学習の比較研究に向けて
Ⅴ.教師教育
第11章 制度改革を通じた教員の専門性発展の促進 [王 暁燕]
1.21世紀日本の教師教育が直面する課題と挑戦
2.21世紀の日本の教師教育が現在進めている改革
3.日本の教師教育改革が今後長期にわたって注目する政策課題
4.考察と検討,中国への示唆と参考
第12章 21世紀の日本における教師教育改革について [八田幸恵]
1.専門職としての教師の力量形成という課題と改革の方向性
2.21世紀の日本において推進されている教師教育改革
3.中国の視点を踏まえて
4.おわりに
Ⅵ.情報技術教育
第13章 IT立国戦略における教育情報化 [張 傑夫]
1.教育情報化の背景と目標
2.教育情報化の方策と措置
3.教育情報化の現状
4.示唆
5.困惑と課題
第14章 情報教育・ICT活用・IT人材育成 [中池竜一・楠見 孝]
1.政府から民間への主役移行,新たな展開へ
2.小学校・中学校における情報教育
3.高校における情報教育
4.高等教育機関におけるIT人材育成
5.中国側の意見を受けて
Ⅶ.体育・保健体育・食育
第15章 体育を中心とした現状と動向の分析 [尚 大鵬]
1.日本の児童生徒の体力・健康の現状とその増進措置
2.日本の学校の「食育」制度
3.体育科における想定外傷害事故の処理方法
4.日本の学校の保健体育学習指導要領の改訂
第16章 子どもたちの健康と安全を守る—学校保健を中心に [森(柴本)枝美]
1.学校保健について
2.学校保健の歴史
3.現代日本における学校保健
4.おわりに
Ⅷ.国際理解教育
第17章 コミュニケーション能力と国際理解教育を中心に [李 協京]
1.日本における国際理解教育の概要
2.学習指導要領からみる日本の小・中・高等学校における国際理解教育
3.学校を主体とした日本における国際理解教育の実践
4.日本の小・中・高等学校における国際理解教育の経験と示唆
第18章 日本における国際理解教育と英語教育の関係—小学校外国語活動を手がかりに
[楠山 研・ベー シュウキー]
1.日本の外国語教育と国際理解教育
2.日中の小学校の英語教育における国際理解の対象
3.日本における小学校外国語活動の導入経緯
4.日本の小学校外国語活動が抱える課題
5.まとめ—中国側原稿と合わせて
年 表
あとがき
索 引