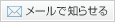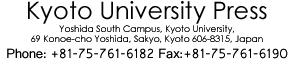Home > Book Detail Page

建築と私
菊変上製, 262 pages
ISBN: 9784876984244
pub. date: 08/01
- Price : JPY 2,900 (with tax: JPY 3,190)
-
Out of Stock
「建築は与条件やプログラム、機能から出来上がっている。したがって、そこに建築家個人の個性を登場させることは難しい」――建築教育の場で語られるこうした言説は果たしてどこまで本当なのか?若い世代に、近代の殻を破る積極的な仕事を期待して、日本を代表する建築家5人が、自らの作品を通し建築における様々な自己表現の形を示す。
高松 伸(たかまつ しん)
1948年 島根県生まれ. 1971年 京都大学工学部建築学科第二学科卒業
1974年 京都大学大学院工学研究科修士課程修了
1980年 京都大学大学院工学研究科博士課程修了
1981年 高松伸建築設計事務所設立
1993年 高松伸建築設計事務所ヨーロッパ事務所設立 1995年 アメリカ建築家協会(AIA)名誉会員
1996年 ドイツ建築家協会(BDA)名誉会員
2001年 英国王立建築協会(RIBA)会員
現在 京都大学工学研究科教授
1984年 第3回日本建築家協会新人賞
1989年 日本建築学会賞 1994年 京都府文化賞功労賞 1996年 芸術選奨文部大臣賞 1999年 第40回BCS賞(建築業協会賞)
■執筆者一覧
山本理顕(やまもと りけん) 1945年 中国北京生まれ. 1968年 日本大学理工学部建築学科卒業
1971年 東京芸術大学大学院美術研究科建築専攻修了
東京大学生産技術研究所 原研究室生を経て、山本理顕設計工場設立.
石田敏明(いしだ としあき) 1950年 広島県生まれ. 1973年 広島工業大学工学部建築学科卒業
伊東豊雄建築設計事務所勤務を経て,石田敏明建築設計事務所設立.
現在,前橋工科大学大学院工学研究科教授
内藤 廣(ないとう ひろし) 1950年 横浜生まれ.
1976年 早稲田大学大学院修士課程修了
フェルナンド・イゲーラス建築設計事務所(マドリッド),菊竹清訓建築設計事務所勤務を経て,内藤廣建築設計事務所設立. 現在,東京大学工学部土木工学科景観研究室助教授
赤坂喜顕(あかさか よしあき) 1952年 仙台市生まれ. 1979年 早稲田大学理工学部大学院修士課程修了,同年株式会社竹中工務店入社.東京本店設計部設計課長を経て
現在,同設計部設計担当副部長,1989年より早稲田大学理工学部建築学科非常勤講師.
隈 研吾(くま けんご)
1954年 横浜生まれ.
1979年 東京大学建築学科大学院修了
コロンビア大学客員研究員を経て,隈研吾建築都市設計事務所主宰.
現在,慶應義塾大学理工学部教授
1948年 島根県生まれ. 1971年 京都大学工学部建築学科第二学科卒業
1974年 京都大学大学院工学研究科修士課程修了
1980年 京都大学大学院工学研究科博士課程修了
1981年 高松伸建築設計事務所設立
1993年 高松伸建築設計事務所ヨーロッパ事務所設立 1995年 アメリカ建築家協会(AIA)名誉会員
1996年 ドイツ建築家協会(BDA)名誉会員
2001年 英国王立建築協会(RIBA)会員
現在 京都大学工学研究科教授
1984年 第3回日本建築家協会新人賞
1989年 日本建築学会賞 1994年 京都府文化賞功労賞 1996年 芸術選奨文部大臣賞 1999年 第40回BCS賞(建築業協会賞)
■執筆者一覧
山本理顕(やまもと りけん) 1945年 中国北京生まれ. 1968年 日本大学理工学部建築学科卒業
1971年 東京芸術大学大学院美術研究科建築専攻修了
東京大学生産技術研究所 原研究室生を経て、山本理顕設計工場設立.
石田敏明(いしだ としあき) 1950年 広島県生まれ. 1973年 広島工業大学工学部建築学科卒業
伊東豊雄建築設計事務所勤務を経て,石田敏明建築設計事務所設立.
現在,前橋工科大学大学院工学研究科教授
内藤 廣(ないとう ひろし) 1950年 横浜生まれ.
1976年 早稲田大学大学院修士課程修了
フェルナンド・イゲーラス建築設計事務所(マドリッド),菊竹清訓建築設計事務所勤務を経て,内藤廣建築設計事務所設立. 現在,東京大学工学部土木工学科景観研究室助教授
赤坂喜顕(あかさか よしあき) 1952年 仙台市生まれ. 1979年 早稲田大学理工学部大学院修士課程修了,同年株式会社竹中工務店入社.東京本店設計部設計課長を経て
現在,同設計部設計担当副部長,1989年より早稲田大学理工学部建築学科非常勤講師.
隈 研吾(くま けんご)
1954年 横浜生まれ.
1979年 東京大学建築学科大学院修了
コロンビア大学客員研究員を経て,隈研吾建築都市設計事務所主宰.
現在,慶應義塾大学理工学部教授
円環の強度――序にかえて ✎ 高松 伸
1 「私」が結びつけるもの ✎ 山本理顕
お前はどこにいるのか?
「私」を消しつつ、それでも残る「私」
業界内の「私」でいいのか?
「私」を昇華させる言語を持つ
人々の参加によって「私」の可能性を広げる
建築の空間がプログラムを刺激していくことも
情報化時代には「建築」は不要か?
「私」が消えていくとき
「透明」である意味
集合住宅を開放的につくる
「二つの評価」を結びつける「私」という主体
2 最近の自作と私 ✎ 石田敏明
どのように「場」を規定するか
建築をめぐる場所と固有性
二二のプロジェクト
床を基本にした〈Aプロジェクト〉と〈富士裾野の山荘〉
生活のスタイルと建築
モノと人の流れを重視した〈有明フェリー長洲港ターミナル〉
「環境連続体」としての建築
都市環境の再生を担う〈小鮒ネーム刺繍店〉
地形を建築化した〈カフェテラス フリーメン〉
〈KUSハウス〉と空間の距離
市民に開かれた場所をめざした〈印西消防署牧ノ原分署〉
3 ルイス・カーンと私 ✎ 内藤 廣
建築をやめようかと思いつつペンシルヴァニアへ
大変身したカーンの〈エシェリック邸〉に出合って
イゲーラスの門をたたき、「旅」をつづけた二〇代
観念ではなくモノについて語ろう
アメリカの建築はカーンで終わった
カーンは凍りついた時間を発明、私たちは……
自己主張を始めたシャフト
キッチンに泣いた〈エシェリック邸〉
見ていて飽きない〈ブリティッシュ・アート・センター〉
人を瞑想的にさせる〈ソーク・インスティテュート〉
砂漠でオアシスに出合う気分の〈キンベル美術館〉
モノは時代を超えていく
その場所に行かなければ始まらない
4 ミース・ファン・デル・ローエと私 ✎ 赤坂喜顕
一 序章
1 はじめに
2 プロローグ ―― ミースとカーン
二 ヨーロッパの夢 ―― 一九二一-一九三七
1 ふたつのスカイスクレーパー
2 シュトゥットガルトの丘
3 〈ル・コルビュジェ棟〉
4 〈ガルシェの家〉
5 〈バルセロナパビリオン〉
6 〈テューゲントハット邸〉
7 〈ガルシェの家〉と〈テューゲントハット邸〉
8 〈ミューラー邸〉
三 アメリカの現実 ―― 一九三八-一九六八
1 〈ファンズワース邸〉
2 アメリカにおける第一の型
3 アメリカにおける第二の型
4 アメリカにおける第三の型
5 シンケルとジョンソン
6 〈ガラスの家〉と〈テューゲントハット邸〉
7 エピローグ ―― ミース・ファン・デル・ローエと私
5 オブジェクトと私 ✎ 隈 研吾
オブジェクト作りにとりつかれた二〇世紀
カオスによるオブジェクトの解体は成功したか
地上的視点とメタレベルの視点で世界につながる
海と自分との関係性をデザインしたい
シークエンスとして出現したベネチア・ビエンナーレ〈日本館〉
写真家泣かせの〈北上川運河交流館〉
頼りないもののあり方にも魅力
広重にならって形の無いものを表現した〈馬頭町広重美術館〉
リアルスペースとサイバースペースに境界はない
「反オブジェクト」のこれから
1 「私」が結びつけるもの ✎ 山本理顕
お前はどこにいるのか?
「私」を消しつつ、それでも残る「私」
業界内の「私」でいいのか?
「私」を昇華させる言語を持つ
人々の参加によって「私」の可能性を広げる
建築の空間がプログラムを刺激していくことも
情報化時代には「建築」は不要か?
「私」が消えていくとき
「透明」である意味
集合住宅を開放的につくる
「二つの評価」を結びつける「私」という主体
2 最近の自作と私 ✎ 石田敏明
どのように「場」を規定するか
建築をめぐる場所と固有性
二二のプロジェクト
床を基本にした〈Aプロジェクト〉と〈富士裾野の山荘〉
生活のスタイルと建築
モノと人の流れを重視した〈有明フェリー長洲港ターミナル〉
「環境連続体」としての建築
都市環境の再生を担う〈小鮒ネーム刺繍店〉
地形を建築化した〈カフェテラス フリーメン〉
〈KUSハウス〉と空間の距離
市民に開かれた場所をめざした〈印西消防署牧ノ原分署〉
3 ルイス・カーンと私 ✎ 内藤 廣
建築をやめようかと思いつつペンシルヴァニアへ
大変身したカーンの〈エシェリック邸〉に出合って
イゲーラスの門をたたき、「旅」をつづけた二〇代
観念ではなくモノについて語ろう
アメリカの建築はカーンで終わった
カーンは凍りついた時間を発明、私たちは……
自己主張を始めたシャフト
キッチンに泣いた〈エシェリック邸〉
見ていて飽きない〈ブリティッシュ・アート・センター〉
人を瞑想的にさせる〈ソーク・インスティテュート〉
砂漠でオアシスに出合う気分の〈キンベル美術館〉
モノは時代を超えていく
その場所に行かなければ始まらない
4 ミース・ファン・デル・ローエと私 ✎ 赤坂喜顕
一 序章
1 はじめに
2 プロローグ ―― ミースとカーン
二 ヨーロッパの夢 ―― 一九二一-一九三七
1 ふたつのスカイスクレーパー
2 シュトゥットガルトの丘
3 〈ル・コルビュジェ棟〉
4 〈ガルシェの家〉
5 〈バルセロナパビリオン〉
6 〈テューゲントハット邸〉
7 〈ガルシェの家〉と〈テューゲントハット邸〉
8 〈ミューラー邸〉
三 アメリカの現実 ―― 一九三八-一九六八
1 〈ファンズワース邸〉
2 アメリカにおける第一の型
3 アメリカにおける第二の型
4 アメリカにおける第三の型
5 シンケルとジョンソン
6 〈ガラスの家〉と〈テューゲントハット邸〉
7 エピローグ ―― ミース・ファン・デル・ローエと私
5 オブジェクトと私 ✎ 隈 研吾
オブジェクト作りにとりつかれた二〇世紀
カオスによるオブジェクトの解体は成功したか
地上的視点とメタレベルの視点で世界につながる
海と自分との関係性をデザインしたい
シークエンスとして出現したベネチア・ビエンナーレ〈日本館〉
写真家泣かせの〈北上川運河交流館〉
頼りないもののあり方にも魅力
広重にならって形の無いものを表現した〈馬頭町広重美術館〉
リアルスペースとサイバースペースに境界はない
「反オブジェクト」のこれから