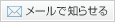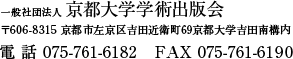ホーム > 書籍詳細ページ

変異するダーウィニズム
進化論と社会
A5上製・650頁
ISBN: 9784876986217
発行年月: 2003/11
- 本体: 5,200円(税込 5,720円)
-
在庫なし
ダーウィニズム=進化論の登場によって、人文・社会科学も大変革を迫られた。「進化」を導きの糸として、さまざまな領域で「新しい学問」が誕生した。その一世紀半の軌跡を、総合的に追究する論集。初期の概念をめぐる論争、社会学をはじめとする諸科学への影響、とりわけ優生学などを促進した課程をたどり、現代における最新到達点を示す。
編 者:
阪上 孝(さかがみ たかし)
[現 職] 中部大学中部高等学術研究所教授・京都大学名誉教授
1939年 神戸市生まれ。
1966年 京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。
1966年 京都大学人文科学研究所助手。
1973年 大阪市立大学経済学部講師。
1976年 京都大学人文科学研究所助教授。
1988年 京都大学人文科学研究所教授。
2003年より現職。
[主な著書]
『フランス社会主義』(新評論、1981年)
『一八四八 国家装置と民衆』(編著、ミネルヴァ書房、1985年)
『人文学のアナトミー』(共編著、岩波書店、1995年)
『近代的統治の誕生』(岩波書店、1999年)
執筆者:
阪上 孝(さかがみ たかし) 中部大学中部高等学術研究所/社会思想史
北垣 徹(きたがき とおる) 西南学院大学文学部/知識社会学・社会思想史
小林 博行(こばやし ひろゆき) 京都大学人文科学研究所/科学史
大東 祥孝(おおひがし よしたか)京都大学留学生センター/精神医学
田中 雅一(たなか まさかず) 京都大学人文科学研究所/文化人類学
小山 哲(こやま さとし) 京都大学大学院文学研究科/西洋史
白鳥 義彦(しらとり よしひこ) 神戸大学文学部/社会学
武田 時昌(たけだ ときまさ) 京都大学人文科学研究所/中国科学思想史
上野 成利(うえの なりとし) 神戸大学国際文化学部/政治・社会思想史
斎藤 光(さいとう ひかる) 京都精華大学人文学部/科学史
宇城 輝人(うしろ てるひと) 福井県立大学学術教養センター/社会学・社会思想史
竹沢 泰子(たけざわ やすこ) 京都大学人文科学研究所/人権・エスニシティ論
小林 清一(こばやし きよかず) 滋賀県立大学人間文化学部/社会政策・社会思想史
横山 輝雄(よこやま てるお) 南山大学人文学部/科学哲学・科学技術論
加藤 和人(かとう かずと) 京都大学人文科学研究所/現代生命科学論
八木 紀一郎(やぎ きいちろう) 京都大学大学院経済学研究科/経済学・経済学史
阪上 孝(さかがみ たかし)
[現 職] 中部大学中部高等学術研究所教授・京都大学名誉教授
1939年 神戸市生まれ。
1966年 京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。
1966年 京都大学人文科学研究所助手。
1973年 大阪市立大学経済学部講師。
1976年 京都大学人文科学研究所助教授。
1988年 京都大学人文科学研究所教授。
2003年より現職。
[主な著書]
『フランス社会主義』(新評論、1981年)
『一八四八 国家装置と民衆』(編著、ミネルヴァ書房、1985年)
『人文学のアナトミー』(共編著、岩波書店、1995年)
『近代的統治の誕生』(岩波書店、1999年)
執筆者:
阪上 孝(さかがみ たかし) 中部大学中部高等学術研究所/社会思想史
北垣 徹(きたがき とおる) 西南学院大学文学部/知識社会学・社会思想史
小林 博行(こばやし ひろゆき) 京都大学人文科学研究所/科学史
大東 祥孝(おおひがし よしたか)京都大学留学生センター/精神医学
田中 雅一(たなか まさかず) 京都大学人文科学研究所/文化人類学
小山 哲(こやま さとし) 京都大学大学院文学研究科/西洋史
白鳥 義彦(しらとり よしひこ) 神戸大学文学部/社会学
武田 時昌(たけだ ときまさ) 京都大学人文科学研究所/中国科学思想史
上野 成利(うえの なりとし) 神戸大学国際文化学部/政治・社会思想史
斎藤 光(さいとう ひかる) 京都精華大学人文学部/科学史
宇城 輝人(うしろ てるひと) 福井県立大学学術教養センター/社会学・社会思想史
竹沢 泰子(たけざわ やすこ) 京都大学人文科学研究所/人権・エスニシティ論
小林 清一(こばやし きよかず) 滋賀県立大学人間文化学部/社会政策・社会思想史
横山 輝雄(よこやま てるお) 南山大学人文学部/科学哲学・科学技術論
加藤 和人(かとう かずと) 京都大学人文科学研究所/現代生命科学論
八木 紀一郎(やぎ きいちろう) 京都大学大学院経済学研究科/経済学・経済学史
はしがき
ダーウィニズムと人文・社会科学 阪上 孝
一 ダーウィニズムと人文・社会科学 ――その二つの局面
二 第一局面におけるダーウィニズム
三 累積的変化の理論 ――ソースティン・ヴェブレン
四 「文化進化論」
I 概念と論争
ダーウィンを消した女 ――クレマンス・ロワイエと仏訳『種の起源』 北垣 徹
一 知の広がりの諸様態
二 『種の起源』の進化と変異
三 翻訳のダイナミズムとポリティクス
四 フェミニズムとレイシズムのあいだ
五 一元論的唯物論
六 ダーウィンの威光
カプセルのなかの科学 ――スペンサー=ヴァイスマン論争 小林 博行
一 舞台と発端
二 争点――三つのレベル
三 基本的対立
四 余波と副産物
「変質」と「解体」 ――精神医学と進化論 大東 祥孝
一 変質論と進化論
二 「解体」学説と進化論
三 「変質」と「解体」の精神医学における進化論的意義
四 ダーウィニズムと精神医学
親族研究に置ける進化概念の受容 ――進化から変容へ 田中 雅一
一 進化から歴史へ
二 類別的名称とは? ――ドラヴィダ型親族名称体系
三 『人類の血族と婚姻の諸体系』の初稿
四 進化主義の導入
五 『古代社会』における家族と親族
六 モーガン以後の親族研究 ――レヴィ=ストロースとニーダム
七 進化を決定する要因 ――スリランカの漁村から
II 進化論から見た社会
闘争する社会 ――ルドヴィク・ダンプロヴィチの社会学大系 小山 哲
一 「ファシズムへの予備工作」?
二 ポーランド・ポジティヴィズムと進化論の受容
三 グンプロヴィチのプロフィール
四 グンプロヴィチの社会学大系 ――進化論との関連を中心に
五 「ポーランドの土壌」から生まれたもの
『動物社会』と進化論 ――アルフレッド・エスピナスをめぐって 白鳥 義彦
一 エスピナスの位置づけ
二 エスピナスの経歴
三 『動物社会』について
四 社会学への道
五 動物社会への視点
加藤弘之の進化学事始 武田 時昌
一 近代日本に置ける進化論の啓蒙活動
二 バックル文明史観からダーウィン進化論へ
三 人口論とダーウィン説
四 人種論における進化説
五 ドイツ進化主義者の影響
六 加藤弘之の進化論理解
七 『日本之開化』の進化学
八 社会ダーウィニズムへの傾斜
九 科学知識としての進化論
群体としての社会 ――丘浅次郎における「社会」の発見をめぐって 上野 成利
一 丘浅次郎と「社会」の発見
二 生存競争と適者生存 ――生物の進化
三 団体生活と服従西神 ――人類の滅亡
四 自然淘汰と人類改良 ――社会の進化
五 生存競争と相互扶助 ――生物の階級
六 有機体国家から群体社会へ
個体としての生物、個体としての社会 斎藤 光
――石川千代松における進化と人間社会
一 石川千代松の位置
二 石川の進化思想を測る二つの水準点
三 『進化新論』におけるダーウィン的構図と個体論的構成
四 進化と社会
III 人種と優生学
人口とその徴候 ――優生学批判のために 宇城 輝人
一 統計
二 写真
三 優生学の視点
アメリカ人類学に見る進化論と人種 竹沢 泰子
一 『種の起源』以前のアメリカ人類学 ――モートンとアメリカ人類学派
二 ダーウィンと人類学
三 進化論とアメリカ人類学者 ――ブリントン、パウエル、クロッソン
四 シカゴ世界大博覧会と人種の展示 ――パットナム
五 人類学にとっての進化論
人種主義と優生学 ――進化の科学と人間の「改造」(アメリカの場合)小林 清一
一 心理学の展開と遺伝の科学
二 移民問題と人種主義
三 遺伝の科学と優生学
四 優生運動 ――断種と移民制限
五 優生運動の転換と遺伝の科学
IV ダーウィニズムの現在
「ダーウィン革命」とは何であったか 横山 輝雄
一 コペルニクス革命とダーウィン革命
二 ダーウィン革命についての二つの解釈
三 ダーウィン革命と世界観の問題
四 ダーウィン革命と歴史性の問題
五 ダーウィン革命と目的論の問題
必然としての「進化の操作」 加藤 和人
――現代社会における人と自然の行方を考える
一 現代における進化の科学と思想
二 実験生物学と「進化の操作」の可能性
三 生態系の変化 ――すでに操作されている自然
四 人と自然の見方について ――「文化としての自然」を考える
進化経済学の現在 八木 紀一郎
一 進化的な科学革命の構造
二 再生した進化経済学 ――諸潮流
三 出現しつつあるコア構造
四 岐路か統合か ――進化経済学の現在の課題
ダーウィニズムの展開 関連年表
人名索引
執筆者一覧
ダーウィニズムと人文・社会科学 阪上 孝
一 ダーウィニズムと人文・社会科学 ――その二つの局面
二 第一局面におけるダーウィニズム
三 累積的変化の理論 ――ソースティン・ヴェブレン
四 「文化進化論」
I 概念と論争
ダーウィンを消した女 ――クレマンス・ロワイエと仏訳『種の起源』 北垣 徹
一 知の広がりの諸様態
二 『種の起源』の進化と変異
三 翻訳のダイナミズムとポリティクス
四 フェミニズムとレイシズムのあいだ
五 一元論的唯物論
六 ダーウィンの威光
カプセルのなかの科学 ――スペンサー=ヴァイスマン論争 小林 博行
一 舞台と発端
二 争点――三つのレベル
三 基本的対立
四 余波と副産物
「変質」と「解体」 ――精神医学と進化論 大東 祥孝
一 変質論と進化論
二 「解体」学説と進化論
三 「変質」と「解体」の精神医学における進化論的意義
四 ダーウィニズムと精神医学
親族研究に置ける進化概念の受容 ――進化から変容へ 田中 雅一
一 進化から歴史へ
二 類別的名称とは? ――ドラヴィダ型親族名称体系
三 『人類の血族と婚姻の諸体系』の初稿
四 進化主義の導入
五 『古代社会』における家族と親族
六 モーガン以後の親族研究 ――レヴィ=ストロースとニーダム
七 進化を決定する要因 ――スリランカの漁村から
II 進化論から見た社会
闘争する社会 ――ルドヴィク・ダンプロヴィチの社会学大系 小山 哲
一 「ファシズムへの予備工作」?
二 ポーランド・ポジティヴィズムと進化論の受容
三 グンプロヴィチのプロフィール
四 グンプロヴィチの社会学大系 ――進化論との関連を中心に
五 「ポーランドの土壌」から生まれたもの
『動物社会』と進化論 ――アルフレッド・エスピナスをめぐって 白鳥 義彦
一 エスピナスの位置づけ
二 エスピナスの経歴
三 『動物社会』について
四 社会学への道
五 動物社会への視点
加藤弘之の進化学事始 武田 時昌
一 近代日本に置ける進化論の啓蒙活動
二 バックル文明史観からダーウィン進化論へ
三 人口論とダーウィン説
四 人種論における進化説
五 ドイツ進化主義者の影響
六 加藤弘之の進化論理解
七 『日本之開化』の進化学
八 社会ダーウィニズムへの傾斜
九 科学知識としての進化論
群体としての社会 ――丘浅次郎における「社会」の発見をめぐって 上野 成利
一 丘浅次郎と「社会」の発見
二 生存競争と適者生存 ――生物の進化
三 団体生活と服従西神 ――人類の滅亡
四 自然淘汰と人類改良 ――社会の進化
五 生存競争と相互扶助 ――生物の階級
六 有機体国家から群体社会へ
個体としての生物、個体としての社会 斎藤 光
――石川千代松における進化と人間社会
一 石川千代松の位置
二 石川の進化思想を測る二つの水準点
三 『進化新論』におけるダーウィン的構図と個体論的構成
四 進化と社会
III 人種と優生学
人口とその徴候 ――優生学批判のために 宇城 輝人
一 統計
二 写真
三 優生学の視点
アメリカ人類学に見る進化論と人種 竹沢 泰子
一 『種の起源』以前のアメリカ人類学 ――モートンとアメリカ人類学派
二 ダーウィンと人類学
三 進化論とアメリカ人類学者 ――ブリントン、パウエル、クロッソン
四 シカゴ世界大博覧会と人種の展示 ――パットナム
五 人類学にとっての進化論
人種主義と優生学 ――進化の科学と人間の「改造」(アメリカの場合)小林 清一
一 心理学の展開と遺伝の科学
二 移民問題と人種主義
三 遺伝の科学と優生学
四 優生運動 ――断種と移民制限
五 優生運動の転換と遺伝の科学
IV ダーウィニズムの現在
「ダーウィン革命」とは何であったか 横山 輝雄
一 コペルニクス革命とダーウィン革命
二 ダーウィン革命についての二つの解釈
三 ダーウィン革命と世界観の問題
四 ダーウィン革命と歴史性の問題
五 ダーウィン革命と目的論の問題
必然としての「進化の操作」 加藤 和人
――現代社会における人と自然の行方を考える
一 現代における進化の科学と思想
二 実験生物学と「進化の操作」の可能性
三 生態系の変化 ――すでに操作されている自然
四 人と自然の見方について ――「文化としての自然」を考える
進化経済学の現在 八木 紀一郎
一 進化的な科学革命の構造
二 再生した進化経済学 ――諸潮流
三 出現しつつあるコア構造
四 岐路か統合か ――進化経済学の現在の課題
ダーウィニズムの展開 関連年表
人名索引
執筆者一覧