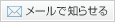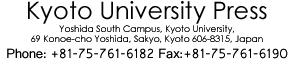Home > Book Detail Page

明治期以来のフランス象徴詩のインパクト、パリ画壇を襲ったジャポニスムの衝撃——文学をはじめ、美術・音楽などの諸分野で色濃い日仏交感が行われてきた。江戸末期から昭和初期にかけて、それぞれの近代化を促進した二つの文化のアイデンテティ形成にとっての「交感」の意味を、豊富な作品事例、作家の創作意図などを分析することにより論じる。
■編著者略歴
宇佐美 斉(うさみ ひとし)
京都大学名誉教授
1942年 愛知県生まれ
1967年 京都大学大学院文学研究科修士課程修了
関西学院大学文学部助手 同専任講師 同助教授を経て
1980年 京都大学人文科学研究所助教授
1993年 同教授
2006年 定年により同退職
主要著書
『落日論』(筑摩書房、1989年)、『詩人の変奏』(小沢書店、1992年)、『作家の恋文』(筑摩書房、2004年)
主要編著書
『フランス・ロマン主義と現代』(筑摩書房、1991年)、『象徴主義の光と影』(ミネルヴァ書房、1997年)、『アヴァンギャルドの世紀』(京都大学学術出版会、2001年)
主要訳書
『ランボー全詩集』(筑摩書房、1996年)
●執筆者一覧
鵜飼敦子(うかい あつこ)京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程
*宇佐美斉(うさみ ひとし)京都大学名誉教授
大浦康介(おおうら やすすけ)京都大学人文科学研究所教授
岡田暁生(おかだ あけお)京都大学人文科学研究所助教授
柏木隆雄(かしわぎ たかお)大阪大学大学院文学研究科教授
北村 卓(きたむら たかし)大阪大学大学院言語文化研究科教授
小西嘉幸(こにし よしゆき)大阪市立大学名誉教授
小山俊輔(こやま しゅんすけ)奈良女子大学文学部教授
近藤秀樹(こんどう ひでき)大阪教育大学非常勤講師
阪村圭英子(さかむら けえこ)京都市立芸術大学非常勤講師
佐野仁美(さの ひとみ)佛教大学非常勤講師
高木博志(たかぎ ひろし)京都大学人文科学研究所教授
高階絵里加(たかしな えりか)京都大学人文科学研究所助教授
内藤 高(ないとう たかし)大阪大学大学院文学研究科教授
袴田麻祐子(はかまだ まゆこ)早稲田大学21世紀COE演劇研究センター特別研究生
松島 征(まつしま ただし)京都大学名誉教授
三野博司(みの ひろし)奈良女子大学文学部教授
森本淳生(もりもと あつお)一橋大学大学院言語社会研究科助教授
吉川順子(よしかわ じゅんこ)京都大学大学院文学研究科博士後期課程
吉田 城(よしだ じょう)故人(元京都大学大学院文学研究科教授)
(50音順、*は編者)
宇佐美 斉(うさみ ひとし)
京都大学名誉教授
1942年 愛知県生まれ
1967年 京都大学大学院文学研究科修士課程修了
関西学院大学文学部助手 同専任講師 同助教授を経て
1980年 京都大学人文科学研究所助教授
1993年 同教授
2006年 定年により同退職
主要著書
『落日論』(筑摩書房、1989年)、『詩人の変奏』(小沢書店、1992年)、『作家の恋文』(筑摩書房、2004年)
主要編著書
『フランス・ロマン主義と現代』(筑摩書房、1991年)、『象徴主義の光と影』(ミネルヴァ書房、1997年)、『アヴァンギャルドの世紀』(京都大学学術出版会、2001年)
主要訳書
『ランボー全詩集』(筑摩書房、1996年)
●執筆者一覧
鵜飼敦子(うかい あつこ)京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程
*宇佐美斉(うさみ ひとし)京都大学名誉教授
大浦康介(おおうら やすすけ)京都大学人文科学研究所教授
岡田暁生(おかだ あけお)京都大学人文科学研究所助教授
柏木隆雄(かしわぎ たかお)大阪大学大学院文学研究科教授
北村 卓(きたむら たかし)大阪大学大学院言語文化研究科教授
小西嘉幸(こにし よしゆき)大阪市立大学名誉教授
小山俊輔(こやま しゅんすけ)奈良女子大学文学部教授
近藤秀樹(こんどう ひでき)大阪教育大学非常勤講師
阪村圭英子(さかむら けえこ)京都市立芸術大学非常勤講師
佐野仁美(さの ひとみ)佛教大学非常勤講師
高木博志(たかぎ ひろし)京都大学人文科学研究所教授
高階絵里加(たかしな えりか)京都大学人文科学研究所助教授
内藤 高(ないとう たかし)大阪大学大学院文学研究科教授
袴田麻祐子(はかまだ まゆこ)早稲田大学21世紀COE演劇研究センター特別研究生
松島 征(まつしま ただし)京都大学名誉教授
三野博司(みの ひろし)奈良女子大学文学部教授
森本淳生(もりもと あつお)一橋大学大学院言語社会研究科助教授
吉川順子(よしかわ じゅんこ)京都大学大学院文学研究科博士後期課程
吉田 城(よしだ じょう)故人(元京都大学大学院文学研究科教授)
(50音順、*は編者)
序文 宇佐美斉
Ⅰ出会いと触発
「フランス」との邂逅 柏木隆雄
一「西洋」との邂逅──新井白石、青木昆陽とその門下、渡辺華山など
二フランス語への架け橋──村上英俊の『三語便覧』
三海波を越えて──初めて踏むヨーロッパ
四ヨーロッパへの視線──『米歐回覧實記』と『八十日間世界一周』
『懺悔録』の翻訳と日本近代の自伝小説──藤村の『新生』 小西嘉幸
一『懺悔録』全訳の刊行をめぐって
二『懺悔録』と藤村の『新生』
木下杢太郎とフランス文化 吉田城
一フランス芸術との出会い
二フランス文学の魅惑
三美食文学の開拓
おわりに──医学的文学と仏印体験
「反語的精神」の共振──林達夫とジャンケレヴィッチ 近藤秀樹
一引用符なき引用──「反語的精神」
二庭と迷宮──「反語」の周辺
三反語家の孤独──古代支那の刺客
四フォークロアとユーモア──「反語」の戦後
おわりに
Ⅱ受容と創造
岩野泡鳴とフランス象徴詩 北村卓
一明治期から大正期にかけてのボードレールとヴェルレーヌの受容
二『神秘的半獣主義』まで
三フランス象徴主義の導入
四『表象派の文学運動』から小説へ
五ボードレールと「描写」の問題
六泡鳴と『表象派の文学運動』の影響
近代詩の移入から創造へ 宇佐美斉
はじめに
一ひとつの受容史
二咀嚼から創造へ
おわりに
九鬼周造の押韻論とフランス文学 小山俊輔
一遊民
二『文学概論』
三押韻論
結び
創造的フランス──竹内勝太郎のヴァレリー 森本淳生
一静的な万物照応──『室内』まで
二飛散する金剛石──「贋造の空」と「海辺の墓地」
三詩人を襲う創作力──「黒豹」、「水蛇」、「虎」
四創造的フランス──ヴァレリー受容における勝太郎の位置
Ⅲ虫と花のジャポニスム
フランスから来た「日本」──『蜻蛉集』挿絵について 高階絵里加
一「装飾芸術」としての『蜻蛉集』
二自然観と造形美
三詩と絵の出会い
『蜻蛉集』における実りと萌芽──和歌とフランス詩の接点 吉川順子
一フランスにもたらされた大和の言の葉
二東洋の短詩とフランスの文学的土壌
三花を植えるジュディットの手
四異国に咲いた和歌の花々、そして萌芽
高島北海の日本再発見──フランス滞在がもたらしたもの 鵜飼敦子
はじめに
一ナンシーの日本人
二『仏文詩画帖』をめぐって
三高島北海の位置
おわりに
『失われた時を求めて』にみる菊の花──愛の憂いと嫉妬を秘める
ジャポニスムの花 阪村圭英子
一フランスにおける菊の位置
二ジャポニスムの菊受容
三『失われた時を求めて』における菊
Ⅳもう一つのオリエンタリズム
世紀末フランスにおける日本趣味とフロベール 柏木加代子
一オリエントから極東へ/二日本趣味と晩年のフロベール
「日本」を書く──ピエール・ロティ『お菊さん』の位置 大浦康介
一恋物語
二異国の表象
マルロー『人間の条件』と日本──「静謐」srnitの夢 三野博司
一混血児
二日本人画家
三神戸
四「静謐」srnit
媒介者としての「水の風景」──日本近代文学を中心にして 内藤高
はじめに
一都市の中の閑雅
二荷風の場合──郷愁を準備するもの
三批評者としての「水」──荷風から藤村、堀口大學へ
四反復される水の風景──竹中郁、林芙美子、岡本かの子
Ⅴ幻のパリ
ドイツ音楽からの脱出?──戦前日本におけるフランス音楽受容の
幾つかのモード 岡田暁生
一「ドイツ音楽にあらずば音楽にあらず」──フランス音楽受容の前提
二「官=ドイツ音楽vs民=フランス音楽」という二項対立
三「ドイツ古典は演奏するものvs作曲の手本は近代フランス」
四ハイカラ/フォークロア/技術──近代フランス音楽の中に見出されたもの
ドビュッシーと日本近代の文学者たち 佐野仁美
一「最先端の」西洋音楽──上田敏と永井荷風
二「日本人の心に近い」音楽──島崎藤村
三民族主義への傾斜──柳沢健と九鬼周造
憧れはフランス、花のパリ 袴田麻祐子
一白井鐵造の「パリ」レビュー
二寶塚外への広がり
三幻想の「西洋人化」
日本人にとってシャンソンとは何か?──シャンソン受容史の試み 松島征
一日本におけるシャンソンの受容史(戦前)
二日本におけるシャンソンの受容史(戦後)
三シャンソン・フランセーズとは何か(シャンソンの実像)
四シャンソンの虚像(日本の場合)
五誤解する権利──歌詞テクストの翻訳の問題
結語に代えて
コラム〈fentre〉
1淫らな告白──日仏翻訳事情の一断面 大浦康介
2中原中也の使った仏和辞典 宇佐美斉
3ブルターニュの「日本」 高階絵里加
4パリ万博と古都 高木博志
5大澤寿人と戦前関西山の手モダニズム 岡田暁生
人名索引(逆頁)
Ⅰ出会いと触発
「フランス」との邂逅 柏木隆雄
一「西洋」との邂逅──新井白石、青木昆陽とその門下、渡辺華山など
二フランス語への架け橋──村上英俊の『三語便覧』
三海波を越えて──初めて踏むヨーロッパ
四ヨーロッパへの視線──『米歐回覧實記』と『八十日間世界一周』
『懺悔録』の翻訳と日本近代の自伝小説──藤村の『新生』 小西嘉幸
一『懺悔録』全訳の刊行をめぐって
二『懺悔録』と藤村の『新生』
木下杢太郎とフランス文化 吉田城
一フランス芸術との出会い
二フランス文学の魅惑
三美食文学の開拓
おわりに──医学的文学と仏印体験
「反語的精神」の共振──林達夫とジャンケレヴィッチ 近藤秀樹
一引用符なき引用──「反語的精神」
二庭と迷宮──「反語」の周辺
三反語家の孤独──古代支那の刺客
四フォークロアとユーモア──「反語」の戦後
おわりに
Ⅱ受容と創造
岩野泡鳴とフランス象徴詩 北村卓
一明治期から大正期にかけてのボードレールとヴェルレーヌの受容
二『神秘的半獣主義』まで
三フランス象徴主義の導入
四『表象派の文学運動』から小説へ
五ボードレールと「描写」の問題
六泡鳴と『表象派の文学運動』の影響
近代詩の移入から創造へ 宇佐美斉
はじめに
一ひとつの受容史
二咀嚼から創造へ
おわりに
九鬼周造の押韻論とフランス文学 小山俊輔
一遊民
二『文学概論』
三押韻論
結び
創造的フランス──竹内勝太郎のヴァレリー 森本淳生
一静的な万物照応──『室内』まで
二飛散する金剛石──「贋造の空」と「海辺の墓地」
三詩人を襲う創作力──「黒豹」、「水蛇」、「虎」
四創造的フランス──ヴァレリー受容における勝太郎の位置
Ⅲ虫と花のジャポニスム
フランスから来た「日本」──『蜻蛉集』挿絵について 高階絵里加
一「装飾芸術」としての『蜻蛉集』
二自然観と造形美
三詩と絵の出会い
『蜻蛉集』における実りと萌芽──和歌とフランス詩の接点 吉川順子
一フランスにもたらされた大和の言の葉
二東洋の短詩とフランスの文学的土壌
三花を植えるジュディットの手
四異国に咲いた和歌の花々、そして萌芽
高島北海の日本再発見──フランス滞在がもたらしたもの 鵜飼敦子
はじめに
一ナンシーの日本人
二『仏文詩画帖』をめぐって
三高島北海の位置
おわりに
『失われた時を求めて』にみる菊の花──愛の憂いと嫉妬を秘める
ジャポニスムの花 阪村圭英子
一フランスにおける菊の位置
二ジャポニスムの菊受容
三『失われた時を求めて』における菊
Ⅳもう一つのオリエンタリズム
世紀末フランスにおける日本趣味とフロベール 柏木加代子
一オリエントから極東へ/二日本趣味と晩年のフロベール
「日本」を書く──ピエール・ロティ『お菊さん』の位置 大浦康介
一恋物語
二異国の表象
マルロー『人間の条件』と日本──「静謐」srnitの夢 三野博司
一混血児
二日本人画家
三神戸
四「静謐」srnit
媒介者としての「水の風景」──日本近代文学を中心にして 内藤高
はじめに
一都市の中の閑雅
二荷風の場合──郷愁を準備するもの
三批評者としての「水」──荷風から藤村、堀口大學へ
四反復される水の風景──竹中郁、林芙美子、岡本かの子
Ⅴ幻のパリ
ドイツ音楽からの脱出?──戦前日本におけるフランス音楽受容の
幾つかのモード 岡田暁生
一「ドイツ音楽にあらずば音楽にあらず」──フランス音楽受容の前提
二「官=ドイツ音楽vs民=フランス音楽」という二項対立
三「ドイツ古典は演奏するものvs作曲の手本は近代フランス」
四ハイカラ/フォークロア/技術──近代フランス音楽の中に見出されたもの
ドビュッシーと日本近代の文学者たち 佐野仁美
一「最先端の」西洋音楽──上田敏と永井荷風
二「日本人の心に近い」音楽──島崎藤村
三民族主義への傾斜──柳沢健と九鬼周造
憧れはフランス、花のパリ 袴田麻祐子
一白井鐵造の「パリ」レビュー
二寶塚外への広がり
三幻想の「西洋人化」
日本人にとってシャンソンとは何か?──シャンソン受容史の試み 松島征
一日本におけるシャンソンの受容史(戦前)
二日本におけるシャンソンの受容史(戦後)
三シャンソン・フランセーズとは何か(シャンソンの実像)
四シャンソンの虚像(日本の場合)
五誤解する権利──歌詞テクストの翻訳の問題
結語に代えて
コラム〈fentre〉
1淫らな告白──日仏翻訳事情の一断面 大浦康介
2中原中也の使った仏和辞典 宇佐美斉
3ブルターニュの「日本」 高階絵里加
4パリ万博と古都 高木博志
5大澤寿人と戦前関西山の手モダニズム 岡田暁生
人名索引(逆頁)