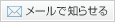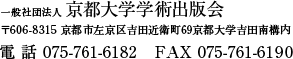ホーム > 書籍詳細ページ
ポスト・ソビエト状況、改革開放政策、都市への移住・開発、生態的変化と文化復興運動、アイデンティティの構築など、さまざまに揺れ動く社会状況の中で生きる北方周極地域の少数民族。圧倒的な力をもつ多数派集団と共生する彼らのエスニシティとアイデンティティの動態を描き出し、人類学的視点から両者の関係を解明する。
執筆者紹介(執筆順、*印は編者)
煎本 孝(いりもと たかし)*
東京大学大学院理学系研究科博士課程単位取得退学。Ph.D.(サイモン・フレーザー大学)。現在, 北海道大学大学院文学研究科教授。専門は生態人類学,文化人類学,自然誌,北方地域研究。
主要著書・論文:『文化の自然誌』(東京大学出版会,1996), 『カナダ・インディアンの世界から』(文庫版,福音館書店,2002),『東北アジア諸民族の文化動態』(編著,北海道大学図書刊行会,2002),『トナカイ遊牧民,循環のフィロソフィー』(明石書店,2006)など。
山田孝子(やまだ たかこ)*
京都大学大学院理学研究科博士課程単位取得退学。京都大学理学博士。現在,京都大学大学院人間・環境学研究科教授。専門は宗教人類学,文化人類学,シャマニズム研究。
主要著書・論文:『アイヌの世界観』(講談社,1994),An Anthropology of Animism and Shamanism (Akad士iai Kiad 1999), The World View of the Ainu (Kegan Paul, 2001), 「現代化とシャマニズムの実践にみる身体」(『文化人類学』70(2),2005)など。
岸上伸啓(きしがみ のぶひろ)
マッギル大学大学院人類学部博士課程単位取得退学。総合研究大学院大学文学博士。現在,国立民族学博物館先端人類科学研究部教授および総合研究大学院大学文化科学研究科教授。専門は文化人類学,北方文化研究。
主要著書・論文:『極北の民 カナダ・イヌイット』(弘文堂,1998),『イヌイット』(中央公論新社,2005),A New Typology of Food-Sharing Practices among Hunter-Gatherers, with a Special Focus on Inuit Examples (Journal of Anthropological Research 60, 2004), 「都市イヌイットのコミュニティー形成運動」(『文化人類学』70(4),2006)など。
井上敏昭(いのうえ としあき)
筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科単位取得退学。筑波大学文学修士。現在,城西国際大学福祉総合学部助教授。専門は文化人類学。北米先住民研究。
主要著書・論文:Hunting as a Symbol of Cultural Tradition: the Cultural Meaning of Subsistence Activities in Gwichユin Athabascan Society of Northern Alaska (Senri Ethnological Studies 56, 2001), 「内陸アラスカ先住民社会におけるサケ資源の利用と管理の諸問題」(『国立民族学博物館調査報告』46,2003),「グイッチン」(富田虎男,スチュアート・ヘンリ編『講座 世界の先住民族 ファースト・ピープルズの現在07 北米』明石書店,2005)など。
大曲佳世(おおまがり かよ)
マニトバ大学大学院人類学部博士課程修了。Ph.D. (マニトバ大学)。現在,財団法人日本鯨類研究所情報文化部社会・経済研究室室長。専門は亜極地方,先住民,捕鯨文化など。
主要論文:The Role of Traditional Food in Identity Development among the Western James Bay Cree (Senri Ethnological Studies 66, 2004), Whaling Conflicts: International Debate (Senri Ethnological Studies 67, 2005) など。
池谷和信(いけや かずのぶ)
東北大学大学院理学研究科博士後期課程単位取得退学。東北大学理学博士。現在,国立民族学博物館助教授。専門は環境人類学,人文地理学。
主要著書:『国家のなかでの狩猟採集民』(千里文化財団,2002),『山菜採りの社会誌:資源利用とテリトリー』(東北大学出版会,2003),『現代の牧畜民:乾燥地域の暮らし』(古今書院,2006)など。
雲 肖梅(うん しょうばい)
北海道大学大学院文学研究科博士後期課程修了。北海道大学博士(行動科学)。現在,中国内モンゴル大学人文学院講師,北海道大学文学研究科外国人客員研究員。専門はトゥメト文化や中国少数民族政策に関する研究。
主要著書・論文:「世界民族与民族問題」(布赫編『民族理論与民族政策』内蒙古出版社,1995),「民族意識的個案法研究」(『内蒙古社会科学』5,1996),「内モンゴルにおけるトゥメト・モンゴル人のアイデンティティ」(『北方学会報』7,2000),Ethnic Identity of Tumed Mongols in Inner Mongolia (Senri Ethnological Studies 66, 2004) など。
汪 立珍(おう りっちん)
中央民族大学少数民族言語文学系卒業。中央民族大学文学博士。現在,中央民族大学少数民族言語文学系助教授。専門は満州ツングース民族文学研究。
主要著書・論文:『満州ツングース諸民族の民間文学研究』(中央民族大学出版社,2006),『エベンキ族の神話研究』(中央民族大学出版社,2006)など。
津曲敏郎(つまがり としろう)
北海道大学大学院文学研究科博士後期課程中途退学(文学修士)。現在,北海道大学大学院文学研究科教授。専門はツングース諸語を中心とする北方少数民族言語学。
主要著書・論文:『満洲語入門20講』(大学書林,2002),『北のことばフィールド・ノート:18の言語と文化』(編著,北海道大学図書刊行会,2003),「ウデヘの精神文化断章:自伝テキストから」(煎本孝編『東北アジアの文化動態』北海道大学図書刊行会,2002)など。
阿拉坦宝力格(あらたんぼりご)
北海道大学大学院文学研究科博士後期課程修了。北海道大学博士(文学)。現在,中国内モンゴル大学モンゴル学院助教授。専門は文化人類学。
主要論文:「文化人類学的視点からのモンゴル民謡歌詞内容分類の試み」(『北方学会報』8,2001),「モンゴルにおける「カーヴィヤーダルシャ」の影響について」(『日本モンゴル学会紀要』2003),「モンゴルのオボ祭りについて」(『内モンゴル大学学報』2006)など。
佐々木史郎(ささき しろう)
東京大学大学院社会学研究科博士課程中退。東京大学学術博士。現在,国立民族学博物館研究戦略センター教授。専門は文化人類学。シベリア,極東ロシアの先住民族の文化と歴史の研究。
主要著書・論文:『北方から来た交易民:絹と毛皮とサンタン人』(日本放送出版協会,1996),「北東アジアの河川,海上交通とその拠点:「満洲仮府」デレンの繁栄」(歴史学研究会編『港町の世界史1』青木書店,2005)など。
加藤博文(かとう ひろふみ)
筑波大学大学院歴史・人類学研究科博士課程単位取得退学。現在,北海道大学大学院文学研究科助教授。専門は先史考古学研究。
主要著書・論文:「考古学文化の変容とエスニシティの形成」(海交史研究会編『海と考古学』六一書房,2005),Neolithic Culture in Amurland: The Formation Process of a Prehistoric Complex Hunter-Gatherers Society (Journal of Graduate School of Letters 1, Hokkaido University, 2006), 「後期旧石器的世界の出現」(小杉康編『心と形の考古学』同成社,2006)など。
煎本 孝(いりもと たかし)*
東京大学大学院理学系研究科博士課程単位取得退学。Ph.D.(サイモン・フレーザー大学)。現在, 北海道大学大学院文学研究科教授。専門は生態人類学,文化人類学,自然誌,北方地域研究。
主要著書・論文:『文化の自然誌』(東京大学出版会,1996), 『カナダ・インディアンの世界から』(文庫版,福音館書店,2002),『東北アジア諸民族の文化動態』(編著,北海道大学図書刊行会,2002),『トナカイ遊牧民,循環のフィロソフィー』(明石書店,2006)など。
山田孝子(やまだ たかこ)*
京都大学大学院理学研究科博士課程単位取得退学。京都大学理学博士。現在,京都大学大学院人間・環境学研究科教授。専門は宗教人類学,文化人類学,シャマニズム研究。
主要著書・論文:『アイヌの世界観』(講談社,1994),An Anthropology of Animism and Shamanism (Akad士iai Kiad 1999), The World View of the Ainu (Kegan Paul, 2001), 「現代化とシャマニズムの実践にみる身体」(『文化人類学』70(2),2005)など。
岸上伸啓(きしがみ のぶひろ)
マッギル大学大学院人類学部博士課程単位取得退学。総合研究大学院大学文学博士。現在,国立民族学博物館先端人類科学研究部教授および総合研究大学院大学文化科学研究科教授。専門は文化人類学,北方文化研究。
主要著書・論文:『極北の民 カナダ・イヌイット』(弘文堂,1998),『イヌイット』(中央公論新社,2005),A New Typology of Food-Sharing Practices among Hunter-Gatherers, with a Special Focus on Inuit Examples (Journal of Anthropological Research 60, 2004), 「都市イヌイットのコミュニティー形成運動」(『文化人類学』70(4),2006)など。
井上敏昭(いのうえ としあき)
筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科単位取得退学。筑波大学文学修士。現在,城西国際大学福祉総合学部助教授。専門は文化人類学。北米先住民研究。
主要著書・論文:Hunting as a Symbol of Cultural Tradition: the Cultural Meaning of Subsistence Activities in Gwichユin Athabascan Society of Northern Alaska (Senri Ethnological Studies 56, 2001), 「内陸アラスカ先住民社会におけるサケ資源の利用と管理の諸問題」(『国立民族学博物館調査報告』46,2003),「グイッチン」(富田虎男,スチュアート・ヘンリ編『講座 世界の先住民族 ファースト・ピープルズの現在07 北米』明石書店,2005)など。
大曲佳世(おおまがり かよ)
マニトバ大学大学院人類学部博士課程修了。Ph.D. (マニトバ大学)。現在,財団法人日本鯨類研究所情報文化部社会・経済研究室室長。専門は亜極地方,先住民,捕鯨文化など。
主要論文:The Role of Traditional Food in Identity Development among the Western James Bay Cree (Senri Ethnological Studies 66, 2004), Whaling Conflicts: International Debate (Senri Ethnological Studies 67, 2005) など。
池谷和信(いけや かずのぶ)
東北大学大学院理学研究科博士後期課程単位取得退学。東北大学理学博士。現在,国立民族学博物館助教授。専門は環境人類学,人文地理学。
主要著書:『国家のなかでの狩猟採集民』(千里文化財団,2002),『山菜採りの社会誌:資源利用とテリトリー』(東北大学出版会,2003),『現代の牧畜民:乾燥地域の暮らし』(古今書院,2006)など。
雲 肖梅(うん しょうばい)
北海道大学大学院文学研究科博士後期課程修了。北海道大学博士(行動科学)。現在,中国内モンゴル大学人文学院講師,北海道大学文学研究科外国人客員研究員。専門はトゥメト文化や中国少数民族政策に関する研究。
主要著書・論文:「世界民族与民族問題」(布赫編『民族理論与民族政策』内蒙古出版社,1995),「民族意識的個案法研究」(『内蒙古社会科学』5,1996),「内モンゴルにおけるトゥメト・モンゴル人のアイデンティティ」(『北方学会報』7,2000),Ethnic Identity of Tumed Mongols in Inner Mongolia (Senri Ethnological Studies 66, 2004) など。
汪 立珍(おう りっちん)
中央民族大学少数民族言語文学系卒業。中央民族大学文学博士。現在,中央民族大学少数民族言語文学系助教授。専門は満州ツングース民族文学研究。
主要著書・論文:『満州ツングース諸民族の民間文学研究』(中央民族大学出版社,2006),『エベンキ族の神話研究』(中央民族大学出版社,2006)など。
津曲敏郎(つまがり としろう)
北海道大学大学院文学研究科博士後期課程中途退学(文学修士)。現在,北海道大学大学院文学研究科教授。専門はツングース諸語を中心とする北方少数民族言語学。
主要著書・論文:『満洲語入門20講』(大学書林,2002),『北のことばフィールド・ノート:18の言語と文化』(編著,北海道大学図書刊行会,2003),「ウデヘの精神文化断章:自伝テキストから」(煎本孝編『東北アジアの文化動態』北海道大学図書刊行会,2002)など。
阿拉坦宝力格(あらたんぼりご)
北海道大学大学院文学研究科博士後期課程修了。北海道大学博士(文学)。現在,中国内モンゴル大学モンゴル学院助教授。専門は文化人類学。
主要論文:「文化人類学的視点からのモンゴル民謡歌詞内容分類の試み」(『北方学会報』8,2001),「モンゴルにおける「カーヴィヤーダルシャ」の影響について」(『日本モンゴル学会紀要』2003),「モンゴルのオボ祭りについて」(『内モンゴル大学学報』2006)など。
佐々木史郎(ささき しろう)
東京大学大学院社会学研究科博士課程中退。東京大学学術博士。現在,国立民族学博物館研究戦略センター教授。専門は文化人類学。シベリア,極東ロシアの先住民族の文化と歴史の研究。
主要著書・論文:『北方から来た交易民:絹と毛皮とサンタン人』(日本放送出版協会,1996),「北東アジアの河川,海上交通とその拠点:「満洲仮府」デレンの繁栄」(歴史学研究会編『港町の世界史1』青木書店,2005)など。
加藤博文(かとう ひろふみ)
筑波大学大学院歴史・人類学研究科博士課程単位取得退学。現在,北海道大学大学院文学研究科助教授。専門は先史考古学研究。
主要著書・論文:「考古学文化の変容とエスニシティの形成」(海交史研究会編『海と考古学』六一書房,2005),Neolithic Culture in Amurland: The Formation Process of a Prehistoric Complex Hunter-Gatherers Society (Journal of Graduate School of Letters 1, Hokkaido University, 2006), 「後期旧石器的世界の出現」(小杉康編『心と形の考古学』同成社,2006)など。
序章 北の民の民族性と帰属性 [煎本 孝・山田孝子]
第 I 部 共存への道
第1章 アイヌ文化における死の儀礼の復興をめぐる葛藤と帰属性
[煎本 孝]
1 序論——民族間の紛争とその解決
2 アイヌ文化の変化と死の儀礼
3 死の儀礼の復興の準備
4 死の儀礼の実践
5 考察——民族的帰属性と共生関係の形成
6 結論——共生の思考と人類学
第2章 カナダ・イヌイットの文化的アイデンティティと
エスニック・アイデンティティ [岸上伸啓]
1 はじめに——エスニックシティ研究とアイデンティティ
2 アイデンティティの概念と理論的な視座
3 カナダ・イヌイットのアイデンティティの複合性
4 カナダ・ヌナヴィクのアクリヴィク村におけるイヌイットのアイデンティティ
5 カナダ国ケベック州モントリオールのイヌイット・アイデンティティ
6 文化的アイデンティティとエスニック・アイデンティティ
7 結論——文化的アイデンティティとエスニック・アイデンティティの形成と再生産
第 II 部 「自然」のシンボル化
第3章 自然との共生
——サハのエスニシティとアイデンティティ再構築へのメッセージ[山田孝子]
1 はじめに——ポスト・ソビエトと民族的アイデンティティ
2 サハの歴史的背景
3 共和国政府による生態学的国家建設
4 ヤクーチアにおける文化復興
5 おわりに——アイデンティティ再構築の核となる「自然との共生」の哲学
第4章 「我々はカリブーの民である」
——アラスカ・カナダ先住民のアイデンティティと開発運動 [井上敏昭]
1 はじめに
2 現代グィッチンの狩猟採集社会
3 グィッチンの狩猟採集社会とアイデンティティ
4 ANWR開発計画とグィッチンの反対運動
5 考察:強国に生きる先住民社会
第5章 アイデンティティ構築におけるブッシュ・フードおよびブッシュの役割——オマシュケゴ・クリーの事例から [大曲佳世]
1 はじめに
2 クリーの現代的生活
3 多文化適応とアイデンティティ
4 アイデンティティ構築におけるブッシュ・フードの役割
5 おわりに——多文化適応の戦略としてのアイデンティティ
第 III 部 社会変動を生きる
第6章 チュコトカ自治管区におけるトナカイ牧畜の変化の多様性
——危機に対するチュクチの対応 [池谷和信]
1 はじめに
2 チュコトカをめぐる近年の政治経済の動向
3 チュコトカ自治管区におけるトナカイ牧畜の変化(1927-2001年)
4 チュコトカ自治管区内の地区別の変化
5 「急激衰退型」の村の経済変容と最近の先住民運動
6 まとめと考察
第7章 トゥメト・モンゴル人の民族的アイデンティティの変遷
[雲 肖梅]
1 はじめに
2 1940年代におけるトゥメト人の民族的アイデンティティ
3 新中国成立初期におけるトゥメト人の民族的アイデンティティ
4 文化大革命時期におけるアイデンティティ
5 改革時期におけるアイデンティティ
6 考察——激動のなかでの民族的アイデンティティ
第8章 中国満洲族のアイデンティティ——清朝時代と中国成立以降
[汪 立珍]
1 はじめに
2 清朝時代における満洲族の政治・経済・社会の状況とアイデンティティ
3 中国の成立以降における満洲族の社会状況とアイデンティティ
4 おわりに——民族的アイデンティティの核となる満洲文学
第 IV 部 民族性と帰属性の諸相
第9章 デルス・ウザーラの言語に見るアイデンティティ [津曲敏郎]
1 はじめに
2 デルスのアイデンティティ
3 デルスの言語
4 「デルス=ウデヘ」説
5 アルセーニエフの現地語理解
6 フィクションとしての『デルス・ウザーラ』
7 おわりに
第10章 サハ共和国北部における重層するアイデンティティとエスニシティ
[佐々木史郎]
1 はじめに
2 エヴェノ=ブィタンタイ民族地区の成立
3 エヴェノ=ブィタンタイ地区の経済状況
4 エヴェノ=ブィタンタイ地区における民族的状況
5 おわりに——民族の対立軸が見えない理由
第11章 モンゴルの文様から見える民族性——美意識の継続と変化
[阿拉坦宝力格]
1 はじめに
2 モンゴル文様の定義
3 文様から見た物の文化——博物館で見る文様と物の関係
4 文様から見たモンゴル人の美意識
5 おわりに
第12章 「考古学文化」とエスニシティ——極東ロシアにおける民族形成論再考 [加藤博文]
1 はじめに
2 対象地域の特性
3 「文化」と「集団」をめぐる問題
4 極東ロシアにおける「考古学的文化」の展開
5 極東ロシア古代社会における「考古学文化」内部の多様性
6 エスニシティ論から見た「考古学文化」
7 おわりに:エスニシティ,過去から現在へ
終章 未来の民族性と帰属性 [煎本 孝]
1 新しい模範
2 北の民の民族性と帰属性
3 民族性と帰属性の未来
索 引
第 I 部 共存への道
第1章 アイヌ文化における死の儀礼の復興をめぐる葛藤と帰属性
[煎本 孝]
1 序論——民族間の紛争とその解決
2 アイヌ文化の変化と死の儀礼
3 死の儀礼の復興の準備
4 死の儀礼の実践
5 考察——民族的帰属性と共生関係の形成
6 結論——共生の思考と人類学
第2章 カナダ・イヌイットの文化的アイデンティティと
エスニック・アイデンティティ [岸上伸啓]
1 はじめに——エスニックシティ研究とアイデンティティ
2 アイデンティティの概念と理論的な視座
3 カナダ・イヌイットのアイデンティティの複合性
4 カナダ・ヌナヴィクのアクリヴィク村におけるイヌイットのアイデンティティ
5 カナダ国ケベック州モントリオールのイヌイット・アイデンティティ
6 文化的アイデンティティとエスニック・アイデンティティ
7 結論——文化的アイデンティティとエスニック・アイデンティティの形成と再生産
第 II 部 「自然」のシンボル化
第3章 自然との共生
——サハのエスニシティとアイデンティティ再構築へのメッセージ[山田孝子]
1 はじめに——ポスト・ソビエトと民族的アイデンティティ
2 サハの歴史的背景
3 共和国政府による生態学的国家建設
4 ヤクーチアにおける文化復興
5 おわりに——アイデンティティ再構築の核となる「自然との共生」の哲学
第4章 「我々はカリブーの民である」
——アラスカ・カナダ先住民のアイデンティティと開発運動 [井上敏昭]
1 はじめに
2 現代グィッチンの狩猟採集社会
3 グィッチンの狩猟採集社会とアイデンティティ
4 ANWR開発計画とグィッチンの反対運動
5 考察:強国に生きる先住民社会
第5章 アイデンティティ構築におけるブッシュ・フードおよびブッシュの役割——オマシュケゴ・クリーの事例から [大曲佳世]
1 はじめに
2 クリーの現代的生活
3 多文化適応とアイデンティティ
4 アイデンティティ構築におけるブッシュ・フードの役割
5 おわりに——多文化適応の戦略としてのアイデンティティ
第 III 部 社会変動を生きる
第6章 チュコトカ自治管区におけるトナカイ牧畜の変化の多様性
——危機に対するチュクチの対応 [池谷和信]
1 はじめに
2 チュコトカをめぐる近年の政治経済の動向
3 チュコトカ自治管区におけるトナカイ牧畜の変化(1927-2001年)
4 チュコトカ自治管区内の地区別の変化
5 「急激衰退型」の村の経済変容と最近の先住民運動
6 まとめと考察
第7章 トゥメト・モンゴル人の民族的アイデンティティの変遷
[雲 肖梅]
1 はじめに
2 1940年代におけるトゥメト人の民族的アイデンティティ
3 新中国成立初期におけるトゥメト人の民族的アイデンティティ
4 文化大革命時期におけるアイデンティティ
5 改革時期におけるアイデンティティ
6 考察——激動のなかでの民族的アイデンティティ
第8章 中国満洲族のアイデンティティ——清朝時代と中国成立以降
[汪 立珍]
1 はじめに
2 清朝時代における満洲族の政治・経済・社会の状況とアイデンティティ
3 中国の成立以降における満洲族の社会状況とアイデンティティ
4 おわりに——民族的アイデンティティの核となる満洲文学
第 IV 部 民族性と帰属性の諸相
第9章 デルス・ウザーラの言語に見るアイデンティティ [津曲敏郎]
1 はじめに
2 デルスのアイデンティティ
3 デルスの言語
4 「デルス=ウデヘ」説
5 アルセーニエフの現地語理解
6 フィクションとしての『デルス・ウザーラ』
7 おわりに
第10章 サハ共和国北部における重層するアイデンティティとエスニシティ
[佐々木史郎]
1 はじめに
2 エヴェノ=ブィタンタイ民族地区の成立
3 エヴェノ=ブィタンタイ地区の経済状況
4 エヴェノ=ブィタンタイ地区における民族的状況
5 おわりに——民族の対立軸が見えない理由
第11章 モンゴルの文様から見える民族性——美意識の継続と変化
[阿拉坦宝力格]
1 はじめに
2 モンゴル文様の定義
3 文様から見た物の文化——博物館で見る文様と物の関係
4 文様から見たモンゴル人の美意識
5 おわりに
第12章 「考古学文化」とエスニシティ——極東ロシアにおける民族形成論再考 [加藤博文]
1 はじめに
2 対象地域の特性
3 「文化」と「集団」をめぐる問題
4 極東ロシアにおける「考古学的文化」の展開
5 極東ロシア古代社会における「考古学文化」内部の多様性
6 エスニシティ論から見た「考古学文化」
7 おわりに:エスニシティ,過去から現在へ
終章 未来の民族性と帰属性 [煎本 孝]
1 新しい模範
2 北の民の民族性と帰属性
3 民族性と帰属性の未来
索 引