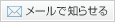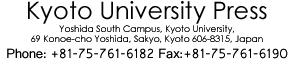Home > Book Detail Page

千年を越え和歌に詠われ、人々に愛でられてきた京都の森。住民にとっては「里山」であると同時に、日本人の美意識と文化を育んだ森は、通常の「里山論」だけでは守れない。都市機能の維持と景観保全、自然の遷移に任せず景観を維持する最適管理、多目的な森林利用の促進など、都市林ならでは伝統景観ならではの保全管理を探る学際的試み。
■編者略歴
田中和博(たなか かずひろ)
昭和28年(1953)生まれ.名古屋大学大学院農学研究科林学専攻満了.
東京大学助手,三重大学講師,助教授,京都府立大学農学研究科教授を経て,平成20年4月より京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授.
専門 森林計画学.GIS(地理情報システム)を応用した森林ゾーニング.
主な著書・論文
田中和博(1996)森林計画学入門.森林計画学会出版局,192pp
田中和博(2000)バイオリージョン研究とGIS.システム農学16:109〜116.
■著者一覧(執筆順)
田中 和博 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授
高田 研一 NPO法人 森林再生支援センター 理事
高原 光 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授
小椋 純一 京都精華大学人文学部 教授
村上幸一郎 林野庁森林整備課 課長補佐
松村 和樹 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授
奥田 賢 京都府立大学大学院農学研究科 博士後期課程
池田 武文 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授
小林 正秀 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 特別講師
深町加津枝 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 准教授
長谷川綉二 NPO法人 大文字保存会 副理事長
石丸 優 京都府立大学 名誉教授
飯田 生穂 元京都府立大学大学院農学研究科 助教授
湊 和也 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授
古田 裕三 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 准教授
川添 正伸 元京都府林業試験場 技師
白石 秀知 京都府南丹広域振興局農林商工部 副室長
渕上 佑樹 京都府地球温暖化防止活動推進センター
成田 真澄 薪く炭くKYOTO 代表
今尾 隆幸 京都モデルフォレスト協会 事務局長
藤下 光伸 長岡京市環境経済部農政課 主幹
高橋 武博 京都市産業観光局農林振興室林業振興課 課長
櫻井 聖悟 京都府立大学大学院農学研究科 博士後期課程
西村 辰也 森なかま 元副代表
田中和博(たなか かずひろ)
昭和28年(1953)生まれ.名古屋大学大学院農学研究科林学専攻満了.
東京大学助手,三重大学講師,助教授,京都府立大学農学研究科教授を経て,平成20年4月より京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授.
専門 森林計画学.GIS(地理情報システム)を応用した森林ゾーニング.
主な著書・論文
田中和博(1996)森林計画学入門.森林計画学会出版局,192pp
田中和博(2000)バイオリージョン研究とGIS.システム農学16:109〜116.
■著者一覧(執筆順)
田中 和博 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授
高田 研一 NPO法人 森林再生支援センター 理事
高原 光 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授
小椋 純一 京都精華大学人文学部 教授
村上幸一郎 林野庁森林整備課 課長補佐
松村 和樹 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授
奥田 賢 京都府立大学大学院農学研究科 博士後期課程
池田 武文 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授
小林 正秀 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 特別講師
深町加津枝 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 准教授
長谷川綉二 NPO法人 大文字保存会 副理事長
石丸 優 京都府立大学 名誉教授
飯田 生穂 元京都府立大学大学院農学研究科 助教授
湊 和也 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 教授
古田 裕三 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 准教授
川添 正伸 元京都府林業試験場 技師
白石 秀知 京都府南丹広域振興局農林商工部 副室長
渕上 佑樹 京都府地球温暖化防止活動推進センター
成田 真澄 薪く炭くKYOTO 代表
今尾 隆幸 京都モデルフォレスト協会 事務局長
藤下 光伸 長岡京市環境経済部農政課 主幹
高橋 武博 京都市産業観光局農林振興室林業振興課 課長
櫻井 聖悟 京都府立大学大学院農学研究科 博士後期課程
西村 辰也 森なかま 元副代表
はじめに(田中和博)
地図
第1章 なぜ古都京都の森の保護が急がれるのか
1—1 「古都の森」とは何か?(田中和博/高田研一)
1—2 京都の三山,特に東山の森林の成立基盤(高田研一)
1—3 「古都の森の変化」とは何か?(高田研一)
1—4 何が求められているのか? —保全の課題と本書の構成—(田中和博)
第1部 古都の森の歴史
第2章 京都の森の変遷
2—1 照葉樹林からマツ林へ —平安時代まで—(高原 光)
2—2 強烈な人間活動の圧力と森林の衰退 —室町後期から江戸末期—(小椋純一)
2—3 近代化の中での古都の森 —明治中期における京都周辺山地—(小椋純一)
2—4 室戸台風被害からの復旧,そして新たな構想へ
—東山国有林風致計画書(昭和11年)とその後の展開—(村上幸一郎)
第3章 京都の森の災害史
3—1 京都における土砂災害 —歴史と現状—(松村和樹)
3—2 京都における風倒木災害(松村和樹)
3—3 京都における地震災害(松村和樹)
第2部 古都の森の現状
第4章 変わりゆく京都の森
4—1 シイノキの分布拡大 —マツ林からシイ林へ—(高原 光・奥田 賢)
4—2 マツ枯れ現象(池田武文)
4—3 ナラ枯れ現象(小林正秀)
第5章 景観保全の現状
5—1 植生の遷移と景観の保全(池田武文)
5—2 森林景観の歴史的な変遷に向き合う
—嵐山における対策の方向性—(深町加津枝)
5—3 天橋立における景観保全の取り組み(池田武文)
第3部 活用による森の保護
第6章 木質系材料の利用技術
6—1 木材の基礎知識(石丸 優)
6—2 樹木及び木材中の物質移動(飯田生穂)
6—3 化学加工による木材用途の拡大(湊 和也)
6—4 国産スギ材の合板利用について(古田裕三)
6—5 高温熱処理によるスギ圧密単板製造技術開発(古田裕三)
6—6 スギ間伐材を活用した木製ガードレールの開発(川添正伸)
6—7 立木染色法の開発と実用化(飯田生穂)
6—8 化学処理木材の楽器への応用(湊 和也)
6—9 和紙に学ぶ —和紙の機能化と利用—(湊 和也)
6—10 新機能性材料としての炭(石丸 優)
第7章 流通と消費の革新
7—1 木材の地産地消の必要性(田中和博)
7—2 ウッドマイレージ(田中和博/白石秀知/渕上佑樹)
7—3 京都府における木材利用の取り組み(古田裕三)
7—4 生産と消費をつなげる森林バイオマス絵巻(成田真澄)
第4部 協働の森づくり
第8章 モデルフォレスト運動と森林情報の共有
8—1 バイオリージョンとモデルフォレスト(田中和博)
8—2 府民みんなで進める京都の森林づくり
—京都モデルフォレスト運動—(今尾隆幸)
8—3 流域森林情報の共有化(松村和樹)
8—4 京都府自然環境情報収集・発信システム(田中和博)
第9章 市民・企業参加による森づくり
9—1 企業と地元が連携した森林整備 —長岡京市西山地域—(藤下光伸)
9—2 京都伝統文化の森推進協議会の取り組みについて(高橋武博)
9—3 森の健康診断(田中和博)
9—4 京都府における森林ボランティア活動の現状(櫻井聖悟・田中和博)
9—5 京都三山の変化に関する市民意識(田中和博)
おわりに(田中和博)
引用文献
索 引
地図
第1章 なぜ古都京都の森の保護が急がれるのか
1—1 「古都の森」とは何か?(田中和博/高田研一)
1—2 京都の三山,特に東山の森林の成立基盤(高田研一)
1—3 「古都の森の変化」とは何か?(高田研一)
1—4 何が求められているのか? —保全の課題と本書の構成—(田中和博)
第1部 古都の森の歴史
第2章 京都の森の変遷
2—1 照葉樹林からマツ林へ —平安時代まで—(高原 光)
2—2 強烈な人間活動の圧力と森林の衰退 —室町後期から江戸末期—(小椋純一)
2—3 近代化の中での古都の森 —明治中期における京都周辺山地—(小椋純一)
2—4 室戸台風被害からの復旧,そして新たな構想へ
—東山国有林風致計画書(昭和11年)とその後の展開—(村上幸一郎)
第3章 京都の森の災害史
3—1 京都における土砂災害 —歴史と現状—(松村和樹)
3—2 京都における風倒木災害(松村和樹)
3—3 京都における地震災害(松村和樹)
第2部 古都の森の現状
第4章 変わりゆく京都の森
4—1 シイノキの分布拡大 —マツ林からシイ林へ—(高原 光・奥田 賢)
4—2 マツ枯れ現象(池田武文)
4—3 ナラ枯れ現象(小林正秀)
第5章 景観保全の現状
5—1 植生の遷移と景観の保全(池田武文)
5—2 森林景観の歴史的な変遷に向き合う
—嵐山における対策の方向性—(深町加津枝)
5—3 天橋立における景観保全の取り組み(池田武文)
第3部 活用による森の保護
第6章 木質系材料の利用技術
6—1 木材の基礎知識(石丸 優)
6—2 樹木及び木材中の物質移動(飯田生穂)
6—3 化学加工による木材用途の拡大(湊 和也)
6—4 国産スギ材の合板利用について(古田裕三)
6—5 高温熱処理によるスギ圧密単板製造技術開発(古田裕三)
6—6 スギ間伐材を活用した木製ガードレールの開発(川添正伸)
6—7 立木染色法の開発と実用化(飯田生穂)
6—8 化学処理木材の楽器への応用(湊 和也)
6—9 和紙に学ぶ —和紙の機能化と利用—(湊 和也)
6—10 新機能性材料としての炭(石丸 優)
第7章 流通と消費の革新
7—1 木材の地産地消の必要性(田中和博)
7—2 ウッドマイレージ(田中和博/白石秀知/渕上佑樹)
7—3 京都府における木材利用の取り組み(古田裕三)
7—4 生産と消費をつなげる森林バイオマス絵巻(成田真澄)
第4部 協働の森づくり
第8章 モデルフォレスト運動と森林情報の共有
8—1 バイオリージョンとモデルフォレスト(田中和博)
8—2 府民みんなで進める京都の森林づくり
—京都モデルフォレスト運動—(今尾隆幸)
8—3 流域森林情報の共有化(松村和樹)
8—4 京都府自然環境情報収集・発信システム(田中和博)
第9章 市民・企業参加による森づくり
9—1 企業と地元が連携した森林整備 —長岡京市西山地域—(藤下光伸)
9—2 京都伝統文化の森推進協議会の取り組みについて(高橋武博)
9—3 森の健康診断(田中和博)
9—4 京都府における森林ボランティア活動の現状(櫻井聖悟・田中和博)
9—5 京都三山の変化に関する市民意識(田中和博)
おわりに(田中和博)
引用文献
索 引