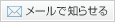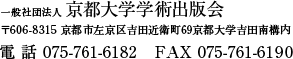ホーム > 書籍詳細ページ
何よりも、死なずに、食べられずにどう成長するか?稚魚の体の構造とその生態の本然は、これにつきる。か弱い存在に見える稚魚だが、その生残戦略には、生命の本質が凝縮しているのだ。困難とされた魚類の生活環の解明に成功した著者が、分子レベルの知見も加え、今世紀の食料生産の柱である水産学と、それを支える生物学に新風を吹き込む。
『日本生態学会ニュースレター』'10年5月、15頁、評者:鈴木秀彌氏
田中 克(たなか まさる)
京都大学名誉教授.農学博士
NPO法人 森は海の恋人 理事・副代表,NPO法人 ものづくり生命文明機構 理事.マレーシアサバ大学持続農学研究科客員教授,
1943年滋賀県大津市生まれ.コタキナバル市在住.
京都大学大学院農学研究科ならびに(元)水産庁西海区水産研究所に在学・在職した四十数年にわたり,主に日本海のヒラメ・マダイならびに有明海のスズキ仔稚魚の初期生活史研究に従事.この研究から沿岸浅海域と陸域,特に森林生態系との不可分のつながりを実感し,2003年京都大学フィールド科学教育研究センターの設置とともに「森里海連環学」を提唱,自然再生の教育研究に取り組んでいる.
主な著書
『魚類学 下』(分担執筆 恒星社厚生閣,1998),『森川海のつながりと河口・沿岸域の生物生産 水産学シリーズ157』(分担編著 恒星社厚生閣,2008).『森里海連環学への道』(旬報社,2008),『稚魚学 多様な生理生態を探る』(分担執筆・共編 生物研究社,2008),『有明海干潟の生きものたち』(分担執筆 東海大学出版会,2009)など.
田川正朋(たがわ まさとも)
京都大学フィールド科学教育研究センター准教授
1962年大阪府生まれ.東京大学理学研究科・動物学専攻博士課程修了,理学博士.
東京大学海洋研究所助手,米国ロードアイランド大学客員研究員,京都大学農学部助手・助教授を経て,2003年より現職.専門は魚類生理学,特に魚類の卵から稚魚になるまでのホルモンの役割について研究を行っている.ヒラメ・カレイ類の変態に見られる体の左右が異なった色・形へと変化する仕組みや,アユやスズキなどの仔稚魚が川から海へ,海から川へと塩分差を克服して生きる仕組み,未受精卵中に含まれる母親由来のホルモンの役割などを,現在の主要な研究テーマとしている.日本水産学会奨励賞受賞.
主な著書
『魚類の初期発育』(分担執筆 恒星社厚生閣,1991),『海の生物資源 生命は海でどう変動しているか』(分担執筆 東海大学出版会,2005),『ホルモンハンドブック新訂eBook版』(分担執筆 南江堂,2007).
中山耕至(なかやま こうじ)
京都大学フィールド科学教育研究センター助教
1971年生まれ.京都大学農学研究科博士課程修了,博士(農学).
専門は魚類の集団遺伝学,系統学.水産動物の資源管理や増殖のための基礎情報として,種内の集団構造や種間の系統関係をミトコンドリアや核のDNAマーカー等を用いて研究している.
主な著書
『魚の科学事典』(分担執筆 朝倉書店,2005),『稚魚学 多様な生理生態を探る』(分担執筆・共編 生物研究社,2008).
京都大学名誉教授.農学博士
NPO法人 森は海の恋人 理事・副代表,NPO法人 ものづくり生命文明機構 理事.マレーシアサバ大学持続農学研究科客員教授,
1943年滋賀県大津市生まれ.コタキナバル市在住.
京都大学大学院農学研究科ならびに(元)水産庁西海区水産研究所に在学・在職した四十数年にわたり,主に日本海のヒラメ・マダイならびに有明海のスズキ仔稚魚の初期生活史研究に従事.この研究から沿岸浅海域と陸域,特に森林生態系との不可分のつながりを実感し,2003年京都大学フィールド科学教育研究センターの設置とともに「森里海連環学」を提唱,自然再生の教育研究に取り組んでいる.
主な著書
『魚類学 下』(分担執筆 恒星社厚生閣,1998),『森川海のつながりと河口・沿岸域の生物生産 水産学シリーズ157』(分担編著 恒星社厚生閣,2008).『森里海連環学への道』(旬報社,2008),『稚魚学 多様な生理生態を探る』(分担執筆・共編 生物研究社,2008),『有明海干潟の生きものたち』(分担執筆 東海大学出版会,2009)など.
田川正朋(たがわ まさとも)
京都大学フィールド科学教育研究センター准教授
1962年大阪府生まれ.東京大学理学研究科・動物学専攻博士課程修了,理学博士.
東京大学海洋研究所助手,米国ロードアイランド大学客員研究員,京都大学農学部助手・助教授を経て,2003年より現職.専門は魚類生理学,特に魚類の卵から稚魚になるまでのホルモンの役割について研究を行っている.ヒラメ・カレイ類の変態に見られる体の左右が異なった色・形へと変化する仕組みや,アユやスズキなどの仔稚魚が川から海へ,海から川へと塩分差を克服して生きる仕組み,未受精卵中に含まれる母親由来のホルモンの役割などを,現在の主要な研究テーマとしている.日本水産学会奨励賞受賞.
主な著書
『魚類の初期発育』(分担執筆 恒星社厚生閣,1991),『海の生物資源 生命は海でどう変動しているか』(分担執筆 東海大学出版会,2005),『ホルモンハンドブック新訂eBook版』(分担執筆 南江堂,2007).
中山耕至(なかやま こうじ)
京都大学フィールド科学教育研究センター助教
1971年生まれ.京都大学農学研究科博士課程修了,博士(農学).
専門は魚類の集団遺伝学,系統学.水産動物の資源管理や増殖のための基礎情報として,種内の集団構造や種間の系統関係をミトコンドリアや核のDNAマーカー等を用いて研究している.
主な著書
『魚の科学事典』(分担執筆 朝倉書店,2005),『稚魚学 多様な生理生態を探る』(分担執筆・共編 生物研究社,2008).
はじめに:稚魚研究の最先端国,日本
第Ⅰ部 試練を越えて稚魚へと“変態”
第1章 【初期減耗】(死亡)とライフサイクル
1 産卵様式と【初期減耗】
2 親による卵の保護と【初期減耗】
3 孵化時間と【初期減耗】
4 孵化酵素の役割
5 魚卵の採集方法
6 卵黄仔魚と【初期減耗】
7 プランクトンとしての仔魚
8 仔魚の採集方法
9 発育の2型:直接発生と間接発生
10 初期成長と【初期減耗】
11 耳石を用いた成長履歴の解析
12 【初期減耗】研究の重要性
13 Critical Period Hypothesisの100年
column 1 魚の托卵
第2章 姿・形を変える:変態と幼形成熟
1 発育段階と変態
2 形の作り換えとしての変態
3 行動の変化を伴う変態
4 変態の生態的側面
5変態は新しい生活への適応
6 変態の内分泌機構
7 異体類変態の分子機構
column 2 ホルモン分析のための仔稚魚の保存方法
8 形態異常を伴う変態
9 着底減耗
10 幼形成熟と変態
11 稚魚の採集方法
column 3 研究と海や飼育の現場との接点を
第3章 稚魚のゆりかご:成育場
1 成育場とは
2 河口・干潟域の成育場機能
3 砂浜海岸域も成育場?
4 海の草原アマモ場はゆりかごか?
5 海の森林:ガラモ場
6 マングローブ河口域
7 サンゴ礁域の特異な成育場機能
8 ヨシ群落はなぜ重要なのか
第4章 仔稚魚は“回遊”するか?
1 通し回遊
2 輸送の功罪
3 死滅回遊
4 鉛直移動の役割
5 接岸回遊一般論
6 サンゴ礁魚類の接岸着底機構
7 成育に伴う生息場の移動
column 4 レプトケファルス
第Ⅱ部 食べて食べられ……:摂食と被食の間の生き残り
第5章 食べる(摂食)
1 食性の一般性と多様性
2 【初回摂餌】の生き残り上の意味
3 栄養要求
4 “変態”する消化系
5 激しく変動する消化酵素活性
6 消化管ホルモンとは
7 栄養状態の評価法
8 なわばり行動
第6章 食べられる(被食)
1 仔魚を捕食する生き物
2 稚魚の捕食者:稚魚の天敵
3 共食いの発生と生き残り上の意味
4 摂食と被食の関連
column 5 チリメンモンスター
第7章 学習し適応する
1 水温への適応
2 塩分への適応
3 捕食・被食への適応
4 極限環境に生きる適応
5 仔魚には個性がある:個性と適応
6 仔稚魚も学習する
7 日周リズム
第8章 分子分析手法と仔稚魚研究
1 DNAによる種同定・種判別
2 生態研究への応用
3 DNA手法の問題点
4 栽培漁業と種内の個体群構造
5 遺伝的多様性の減少と絶滅危惧
column 6 意外な親子関係
第9章 生死のドラマの背後の多様な連環
1 仔魚の生存を保障する食物連鎖
2 阿蘇山が生かす有明海のスズキ稚魚
3 琵琶湖と水田
4 クラゲが提起する問題
5 連環を解きほぐす安定同位体比
第10章 変動する
1 【初期減耗】と資源変動
2 Stable Ocean説
3 被食による【初期減耗】
4 マイワシに見る資源大変動
5 魚種交替と【初期減耗】
第11章 限りがある:環境収容力
1 志々伎湾におけるマダイ稚魚の例
2 放流による環境収容力推定の試み
3 サケ稚魚放流と環境収容力
第Ⅲ部 人の暮らしと稚魚の叫び
第12章 魚を増やそう
1 養殖漁業の発展
2 栽培漁業の新たな展開
3環境修復:モ場や干潟の造成
column 7 ボウズガレイに魅せられて
第13章 天然魚と飼育魚は似て非なるもの?
1 仔魚の摂食量と飼育水温
2 大きく異なる行動特性
3 形態や質の異なる天然魚と人工飼育魚
第14章 地球温暖化と稚魚研究
1 水温上昇の実際とその影響
2 ユーラシア大陸に見る陸—海系
3 異体類の生態に見る
第15章 稚魚たちの叫び
1 砂浜の消失に戸惑う稚魚たち
2 マングローブ河口域の荒廃
3 稚魚たちの警告
第16章 稚魚研究に学ぶ
1 比較の重要性
2 長期的視点:腰を落ち着けて研究しよう
3 広域的視点:分布の縁辺に注目しよう
4総合的視点:横断的視野を養おう
column 8 漁師のひと言
第17章 仔稚魚研究と森里海連環学
1 森の豊かな恵みの重要性
2 森里海連環学から見た新たな課題
3 マングローブ林再生の教訓
column 9 マングローブ林が取り持つ不思議な縁
あとがき
参照文献
第Ⅰ部 試練を越えて稚魚へと“変態”
第1章 【初期減耗】(死亡)とライフサイクル
1 産卵様式と【初期減耗】
2 親による卵の保護と【初期減耗】
3 孵化時間と【初期減耗】
4 孵化酵素の役割
5 魚卵の採集方法
6 卵黄仔魚と【初期減耗】
7 プランクトンとしての仔魚
8 仔魚の採集方法
9 発育の2型:直接発生と間接発生
10 初期成長と【初期減耗】
11 耳石を用いた成長履歴の解析
12 【初期減耗】研究の重要性
13 Critical Period Hypothesisの100年
column 1 魚の托卵
第2章 姿・形を変える:変態と幼形成熟
1 発育段階と変態
2 形の作り換えとしての変態
3 行動の変化を伴う変態
4 変態の生態的側面
5変態は新しい生活への適応
6 変態の内分泌機構
7 異体類変態の分子機構
column 2 ホルモン分析のための仔稚魚の保存方法
8 形態異常を伴う変態
9 着底減耗
10 幼形成熟と変態
11 稚魚の採集方法
column 3 研究と海や飼育の現場との接点を
第3章 稚魚のゆりかご:成育場
1 成育場とは
2 河口・干潟域の成育場機能
3 砂浜海岸域も成育場?
4 海の草原アマモ場はゆりかごか?
5 海の森林:ガラモ場
6 マングローブ河口域
7 サンゴ礁域の特異な成育場機能
8 ヨシ群落はなぜ重要なのか
第4章 仔稚魚は“回遊”するか?
1 通し回遊
2 輸送の功罪
3 死滅回遊
4 鉛直移動の役割
5 接岸回遊一般論
6 サンゴ礁魚類の接岸着底機構
7 成育に伴う生息場の移動
column 4 レプトケファルス
第Ⅱ部 食べて食べられ……:摂食と被食の間の生き残り
第5章 食べる(摂食)
1 食性の一般性と多様性
2 【初回摂餌】の生き残り上の意味
3 栄養要求
4 “変態”する消化系
5 激しく変動する消化酵素活性
6 消化管ホルモンとは
7 栄養状態の評価法
8 なわばり行動
第6章 食べられる(被食)
1 仔魚を捕食する生き物
2 稚魚の捕食者:稚魚の天敵
3 共食いの発生と生き残り上の意味
4 摂食と被食の関連
column 5 チリメンモンスター
第7章 学習し適応する
1 水温への適応
2 塩分への適応
3 捕食・被食への適応
4 極限環境に生きる適応
5 仔魚には個性がある:個性と適応
6 仔稚魚も学習する
7 日周リズム
第8章 分子分析手法と仔稚魚研究
1 DNAによる種同定・種判別
2 生態研究への応用
3 DNA手法の問題点
4 栽培漁業と種内の個体群構造
5 遺伝的多様性の減少と絶滅危惧
column 6 意外な親子関係
第9章 生死のドラマの背後の多様な連環
1 仔魚の生存を保障する食物連鎖
2 阿蘇山が生かす有明海のスズキ稚魚
3 琵琶湖と水田
4 クラゲが提起する問題
5 連環を解きほぐす安定同位体比
第10章 変動する
1 【初期減耗】と資源変動
2 Stable Ocean説
3 被食による【初期減耗】
4 マイワシに見る資源大変動
5 魚種交替と【初期減耗】
第11章 限りがある:環境収容力
1 志々伎湾におけるマダイ稚魚の例
2 放流による環境収容力推定の試み
3 サケ稚魚放流と環境収容力
第Ⅲ部 人の暮らしと稚魚の叫び
第12章 魚を増やそう
1 養殖漁業の発展
2 栽培漁業の新たな展開
3環境修復:モ場や干潟の造成
column 7 ボウズガレイに魅せられて
第13章 天然魚と飼育魚は似て非なるもの?
1 仔魚の摂食量と飼育水温
2 大きく異なる行動特性
3 形態や質の異なる天然魚と人工飼育魚
第14章 地球温暖化と稚魚研究
1 水温上昇の実際とその影響
2 ユーラシア大陸に見る陸—海系
3 異体類の生態に見る
第15章 稚魚たちの叫び
1 砂浜の消失に戸惑う稚魚たち
2 マングローブ河口域の荒廃
3 稚魚たちの警告
第16章 稚魚研究に学ぶ
1 比較の重要性
2 長期的視点:腰を落ち着けて研究しよう
3 広域的視点:分布の縁辺に注目しよう
4総合的視点:横断的視野を養おう
column 8 漁師のひと言
第17章 仔稚魚研究と森里海連環学
1 森の豊かな恵みの重要性
2 森里海連環学から見た新たな課題
3 マングローブ林再生の教訓
column 9 マングローブ林が取り持つ不思議な縁
あとがき
参照文献