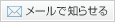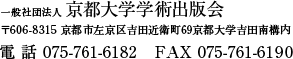ホーム > 書籍詳細ページ

POD版 耐震構造設計論
菊並製・420頁
ISBN: 9784876989034
発行年月: 2005/02
- 本体: 5,200円(税込 5,720円)
-
在庫なし
ライフラインシステムの地震時信頼性を結び糸とし、構造物基礎から上部構造、地中構造物の耐震設計を、動点応答の数値解析、多点入力、制御系相互作用などの問題を基礎づけた上で、各論を展開する。最新の免震設計や免震支承、その効果を測定するハイブリッド実験、サブストラクチュアー法までを考察した大学院生用テキストである。
まえがき
第1章 地震と地盤震動
1-1 構造物の地震被害と耐震設計
1-1-1 構造物の地震被害
1-1-2 構造設計と耐震設計
1-1-3 兵庫県南部地震による構造被害と新しい課題
1-2 地震動の観測
1-2-1 アレー観測
1-2-2 観測システム
1-2-3 観測データの利用
1-2-4 観測データの公開
1-2-5 兵庫県南部地震の観測とその後の観測体制
1-3 地盤震動の予測
1-3-1 理論的予測法
1-3-2 半経験的予測法
1-3-3 統計的予測法
1-3-4 ブラインドプレディクションテスト
1-3-5 兵庫県南部地震の予測法に与えた課題
1-4 地震危険度
1-4-1 地震危険度の解析手法
1-4-2 地震活動の時空間特性
1-4-3 地点地震動の評価
1-4-4 合理的解析モデル
1-4-5 関東地域の地震危険度の解析例
1-4-6 都市の地震災害に着目した耐震信頼性評価
1-4-7 兵庫県南部地震をふまえた今後の課題
第2章 動的応答の数値解析
2-1 動的応答解析法
2-1-1 直接地震応答解析法
2-1-2 モード解析法
2-1-3 応答スペクトル法
2-1-4 弾塑性地震応答解析
2-2 構造物 —基礎— 地盤系の動的相互作用の解析法
2-2-1 概説
2-2-2 地盤と基礎構造物の動的相互作用場
2-2-3 地盤のモデル化手法
2-2-4 構造物のモデル化
2-2-5 地盤—構造物系(地上構造物)
2-2-6 地盤—構造物系(地中構造物)
2-3 構造物 —地盤— りゅたいけいの動的応答解析
2-3-1 流体力の評価
2-3-2 全体系の運動方程式
2-3-3 全体系の動的応答解析
2-4 制御系構造物の動適応答
2-4-1 構造物の振動制御の必要性
2-4-2 制御手法の分類と適用性
2-4-3 最適制御則による構造物の能動的制御
2-4-4 パッシブ、アクティブおよびハイブリッド制振機構の振動台実験
第3章 材料・部材、および構造系・地盤系の耐震性
3-1 材料・構造の基本的動特性
3-1-1 構造材料の特性と試験法
3-1-2 構造部材の特性と試験法
3-1-3 構造体系の特性と試験法
3-2 鋼構造物の基本的動特性
3-2-1 鋼材の強度と伸び
3-2-2 鋼部材の強度とじん性
3-2-3 鋼構造物全体系の強度とじん性
3-2-4 鋼構造物の耐震設計法
3-2-5 鋼構造物の修復・補強法
3-2-6 兵庫県南部地震による鋼構造物の被害と課題
3-3 コンクリート構造物の基本的動特性
3-3-1 繰り返し加重下におけるコンクリート応力—ひずみ関係
3-3-2 コンクリート部材の強度とじん性
3-3-3 コンクリート部材および構造物の変形解析
3-3-4 コンクリート構造物の耐震設計法
3-3-5 コンクリート構造物の耐震補修・補強
3-3-6 兵庫県南部地震によるコンクリート構造物の被害と課題
3-4 基礎—地盤系の動的相互作用の実験
3-4-1 実験法の種類と特徴
3-4-2 室内模型振動実験例
3-4-3 現位置実験例
3-4-4 兵庫県南部地震に見られる基礎—地盤系の動的相互作用
第4章 新しい設計法の基礎理論
4-1 耐震設計における信頼性のレベル
4-1-1 耐震設計における信頼性設計の考え方
4-1-2 耐震設計面からみた構造物の信頼性に関する検討
4-1-3 耐震設計における信頼性設計の展望
4-2 エネルギー規範に基づく設計法
4-2-1 エネルギー規範に基づく耐震設計の考え方
4-2-2 耐震設計におけるエネルギー応答量の定量的評価法
4-2-3 エネルギー規範に基づく損傷度評価指標と耐震設計
4-2-4 今後の課題と将来展望
4-3 最適耐震設計法
4-3-1 耐震設計法における最適化の考え方
4-3-2 ファジィ理論を用いた最適耐震設計法
4-3-3 今後の課題と将来展望
4-4 免震設計法
4-4-1 免震設計の考え方
4-4-2 道路橋の免震設計法
4-4-3 免震装置
4-4-4 免震橋の地震応答特性
4-4-5 免震設計の今後の課題
第5章 ライフラインシステムの地震時信頼性
5-1 ライフライン系の特徴
5-1-1 ライフライン系とは
5-1-2 ライフライン系に共通する特徴
5-1-3 個々のライフライン系に固有な特徴
5-1-4 ライフライン地盤工学
5-2 地震被害事例
5-2-1 設備構造の被害
5-2-2 機能停止の被害
5-3 地震時被害度評価
5-3-1 被害データの分析と既往の被害予測
5-3-2 新たな被害予測法の提案
5-4 地震時信頼性解析
5-4-1 システムの信頼性理論の基礎
5-4-2 ネットワークの地震時信頼性評価
5-5 最適復旧システム
5-5-1 震害復旧の基本的考え方
5-5-2 復旧戦略
5-6 ライフラインと都市地震防災
5-6-1 求められる都市防災の発想の転換
5-6-2 災害に弱い都市機能の維持
5-6-3 都市モニタリングシステム
5-6-4 ライフラインの復旧戦略はどのようにすればよいか
5-6-5 兵庫県南部地震によるライフラインの被害と課題
第6章 橋梁の動的挙動と耐震設計法
6-1 橋梁の耐震設計法の考え方
6-1-1 日本と米国における耐震設計法の変遷
6-1-2 「道路橋示方書」の考え方
6-2 連続高架橋
6-2-1 連続高架橋の力学的特徴と耐震設計の考え方
6-2-2 連続高架橋の耐震設計法
6-2-3 連続高架橋の動的応答特性
6-2-4 連続高架橋の設計法の合理化
6-2-5 兵庫県南部地震による連続高架橋の新しい課題
6-3 斜張橋
6-3-1 斜張橋の力学的特徴と耐震設計の考え方
6-3-2 斜張橋の耐震設計法
6-3-3 斜張橋の動的応答特性
6-3-4 斜張橋の設計法の合理化、耐震性の向上策
6-4 吊橋
6-4-1 吊橋の力学的特徴と耐震設計の考え方
6-4-2 吊橋の耐震設計法
6-4-3 吊橋の動的応答特性
6-4-4 吊橋の設計法の合理化
6-4-5 兵庫県南部地震による吊橋の新しい課題
6-5 下部工
6-5-1 道路橋における基礎形式と安定計算の考え方
6-5-2 杭基礎の耐震設計と問題点
6-5-3 設計法の合理化
6-5-4 兵庫県南部地震による下部工の新しい課題
第7章 各種構造物の動的挙動と耐震設計法
7-1 埋設管路
7-1-1 埋設管路の力学的特徴と耐震設計の考え方
7-1-2 埋設管路の耐震設計法
7-1-3 埋設管路の動的応答特性
7-1-4 埋設管路の耐震設計—今後の課題
7-2 シールドトンネル
7-2-1 シールドトンネルの力学的特徴と耐震設計の考え方
7-2-2 シールドトンネルの耐震設計法
7-2-3 シールドトンネルの動的応答特性
7-2-4 シールドトンネルの耐震設計—今後の課題
7-3 開削洞道および立杭
7-3-1 開削洞道および立杭の力学的特徴
7-3-2 開削洞道および立杭の耐震設計解析法
7-3-3 開削洞道および立杭の動的応答特性
7-3-4 開削洞道および立杭—今後の課題
7-4 地下タンク
7-4-1 地下タンクの力学的特徴と耐震設計の考え方
7-4-2 地下タンクの耐震設計法
7-4-3 地下タンクの動的応答特性
7-4-4 地下タンクの耐震設計—今後の課題
7-5 護岸・岸壁構造物
7-5-1 護岸・岸壁構造物の構造形式と力学的特徴
7-5-2 護岸・岸壁構造物の耐震設計の基本的考え方
7-5-3 護岸・岸壁構造物の動的応答特性
7-5-4 護岸・岸壁構造物の耐震設計—今後の課題
7-6 電気通信設備
7-6-1 電気通信設備の力学的特徴と耐震設計の考え方
7-6-2 電気通信設備の耐震設計法
7-6-3 電気通信設備の動的応答
7-6-4 電気通信設備の耐震設計—今後の課題
あとがき ——まとめと耐震構造の将来展望
引用・参考文献
第1章 地震と地盤震動
1-1 構造物の地震被害と耐震設計
1-1-1 構造物の地震被害
1-1-2 構造設計と耐震設計
1-1-3 兵庫県南部地震による構造被害と新しい課題
1-2 地震動の観測
1-2-1 アレー観測
1-2-2 観測システム
1-2-3 観測データの利用
1-2-4 観測データの公開
1-2-5 兵庫県南部地震の観測とその後の観測体制
1-3 地盤震動の予測
1-3-1 理論的予測法
1-3-2 半経験的予測法
1-3-3 統計的予測法
1-3-4 ブラインドプレディクションテスト
1-3-5 兵庫県南部地震の予測法に与えた課題
1-4 地震危険度
1-4-1 地震危険度の解析手法
1-4-2 地震活動の時空間特性
1-4-3 地点地震動の評価
1-4-4 合理的解析モデル
1-4-5 関東地域の地震危険度の解析例
1-4-6 都市の地震災害に着目した耐震信頼性評価
1-4-7 兵庫県南部地震をふまえた今後の課題
第2章 動的応答の数値解析
2-1 動的応答解析法
2-1-1 直接地震応答解析法
2-1-2 モード解析法
2-1-3 応答スペクトル法
2-1-4 弾塑性地震応答解析
2-2 構造物 —基礎— 地盤系の動的相互作用の解析法
2-2-1 概説
2-2-2 地盤と基礎構造物の動的相互作用場
2-2-3 地盤のモデル化手法
2-2-4 構造物のモデル化
2-2-5 地盤—構造物系(地上構造物)
2-2-6 地盤—構造物系(地中構造物)
2-3 構造物 —地盤— りゅたいけいの動的応答解析
2-3-1 流体力の評価
2-3-2 全体系の運動方程式
2-3-3 全体系の動的応答解析
2-4 制御系構造物の動適応答
2-4-1 構造物の振動制御の必要性
2-4-2 制御手法の分類と適用性
2-4-3 最適制御則による構造物の能動的制御
2-4-4 パッシブ、アクティブおよびハイブリッド制振機構の振動台実験
第3章 材料・部材、および構造系・地盤系の耐震性
3-1 材料・構造の基本的動特性
3-1-1 構造材料の特性と試験法
3-1-2 構造部材の特性と試験法
3-1-3 構造体系の特性と試験法
3-2 鋼構造物の基本的動特性
3-2-1 鋼材の強度と伸び
3-2-2 鋼部材の強度とじん性
3-2-3 鋼構造物全体系の強度とじん性
3-2-4 鋼構造物の耐震設計法
3-2-5 鋼構造物の修復・補強法
3-2-6 兵庫県南部地震による鋼構造物の被害と課題
3-3 コンクリート構造物の基本的動特性
3-3-1 繰り返し加重下におけるコンクリート応力—ひずみ関係
3-3-2 コンクリート部材の強度とじん性
3-3-3 コンクリート部材および構造物の変形解析
3-3-4 コンクリート構造物の耐震設計法
3-3-5 コンクリート構造物の耐震補修・補強
3-3-6 兵庫県南部地震によるコンクリート構造物の被害と課題
3-4 基礎—地盤系の動的相互作用の実験
3-4-1 実験法の種類と特徴
3-4-2 室内模型振動実験例
3-4-3 現位置実験例
3-4-4 兵庫県南部地震に見られる基礎—地盤系の動的相互作用
第4章 新しい設計法の基礎理論
4-1 耐震設計における信頼性のレベル
4-1-1 耐震設計における信頼性設計の考え方
4-1-2 耐震設計面からみた構造物の信頼性に関する検討
4-1-3 耐震設計における信頼性設計の展望
4-2 エネルギー規範に基づく設計法
4-2-1 エネルギー規範に基づく耐震設計の考え方
4-2-2 耐震設計におけるエネルギー応答量の定量的評価法
4-2-3 エネルギー規範に基づく損傷度評価指標と耐震設計
4-2-4 今後の課題と将来展望
4-3 最適耐震設計法
4-3-1 耐震設計法における最適化の考え方
4-3-2 ファジィ理論を用いた最適耐震設計法
4-3-3 今後の課題と将来展望
4-4 免震設計法
4-4-1 免震設計の考え方
4-4-2 道路橋の免震設計法
4-4-3 免震装置
4-4-4 免震橋の地震応答特性
4-4-5 免震設計の今後の課題
第5章 ライフラインシステムの地震時信頼性
5-1 ライフライン系の特徴
5-1-1 ライフライン系とは
5-1-2 ライフライン系に共通する特徴
5-1-3 個々のライフライン系に固有な特徴
5-1-4 ライフライン地盤工学
5-2 地震被害事例
5-2-1 設備構造の被害
5-2-2 機能停止の被害
5-3 地震時被害度評価
5-3-1 被害データの分析と既往の被害予測
5-3-2 新たな被害予測法の提案
5-4 地震時信頼性解析
5-4-1 システムの信頼性理論の基礎
5-4-2 ネットワークの地震時信頼性評価
5-5 最適復旧システム
5-5-1 震害復旧の基本的考え方
5-5-2 復旧戦略
5-6 ライフラインと都市地震防災
5-6-1 求められる都市防災の発想の転換
5-6-2 災害に弱い都市機能の維持
5-6-3 都市モニタリングシステム
5-6-4 ライフラインの復旧戦略はどのようにすればよいか
5-6-5 兵庫県南部地震によるライフラインの被害と課題
第6章 橋梁の動的挙動と耐震設計法
6-1 橋梁の耐震設計法の考え方
6-1-1 日本と米国における耐震設計法の変遷
6-1-2 「道路橋示方書」の考え方
6-2 連続高架橋
6-2-1 連続高架橋の力学的特徴と耐震設計の考え方
6-2-2 連続高架橋の耐震設計法
6-2-3 連続高架橋の動的応答特性
6-2-4 連続高架橋の設計法の合理化
6-2-5 兵庫県南部地震による連続高架橋の新しい課題
6-3 斜張橋
6-3-1 斜張橋の力学的特徴と耐震設計の考え方
6-3-2 斜張橋の耐震設計法
6-3-3 斜張橋の動的応答特性
6-3-4 斜張橋の設計法の合理化、耐震性の向上策
6-4 吊橋
6-4-1 吊橋の力学的特徴と耐震設計の考え方
6-4-2 吊橋の耐震設計法
6-4-3 吊橋の動的応答特性
6-4-4 吊橋の設計法の合理化
6-4-5 兵庫県南部地震による吊橋の新しい課題
6-5 下部工
6-5-1 道路橋における基礎形式と安定計算の考え方
6-5-2 杭基礎の耐震設計と問題点
6-5-3 設計法の合理化
6-5-4 兵庫県南部地震による下部工の新しい課題
第7章 各種構造物の動的挙動と耐震設計法
7-1 埋設管路
7-1-1 埋設管路の力学的特徴と耐震設計の考え方
7-1-2 埋設管路の耐震設計法
7-1-3 埋設管路の動的応答特性
7-1-4 埋設管路の耐震設計—今後の課題
7-2 シールドトンネル
7-2-1 シールドトンネルの力学的特徴と耐震設計の考え方
7-2-2 シールドトンネルの耐震設計法
7-2-3 シールドトンネルの動的応答特性
7-2-4 シールドトンネルの耐震設計—今後の課題
7-3 開削洞道および立杭
7-3-1 開削洞道および立杭の力学的特徴
7-3-2 開削洞道および立杭の耐震設計解析法
7-3-3 開削洞道および立杭の動的応答特性
7-3-4 開削洞道および立杭—今後の課題
7-4 地下タンク
7-4-1 地下タンクの力学的特徴と耐震設計の考え方
7-4-2 地下タンクの耐震設計法
7-4-3 地下タンクの動的応答特性
7-4-4 地下タンクの耐震設計—今後の課題
7-5 護岸・岸壁構造物
7-5-1 護岸・岸壁構造物の構造形式と力学的特徴
7-5-2 護岸・岸壁構造物の耐震設計の基本的考え方
7-5-3 護岸・岸壁構造物の動的応答特性
7-5-4 護岸・岸壁構造物の耐震設計—今後の課題
7-6 電気通信設備
7-6-1 電気通信設備の力学的特徴と耐震設計の考え方
7-6-2 電気通信設備の耐震設計法
7-6-3 電気通信設備の動的応答
7-6-4 電気通信設備の耐震設計—今後の課題
あとがき ——まとめと耐震構造の将来展望
引用・参考文献